従来の日本列島文化論を超えて
新ジャパノロジー覚書 ① New Japanology
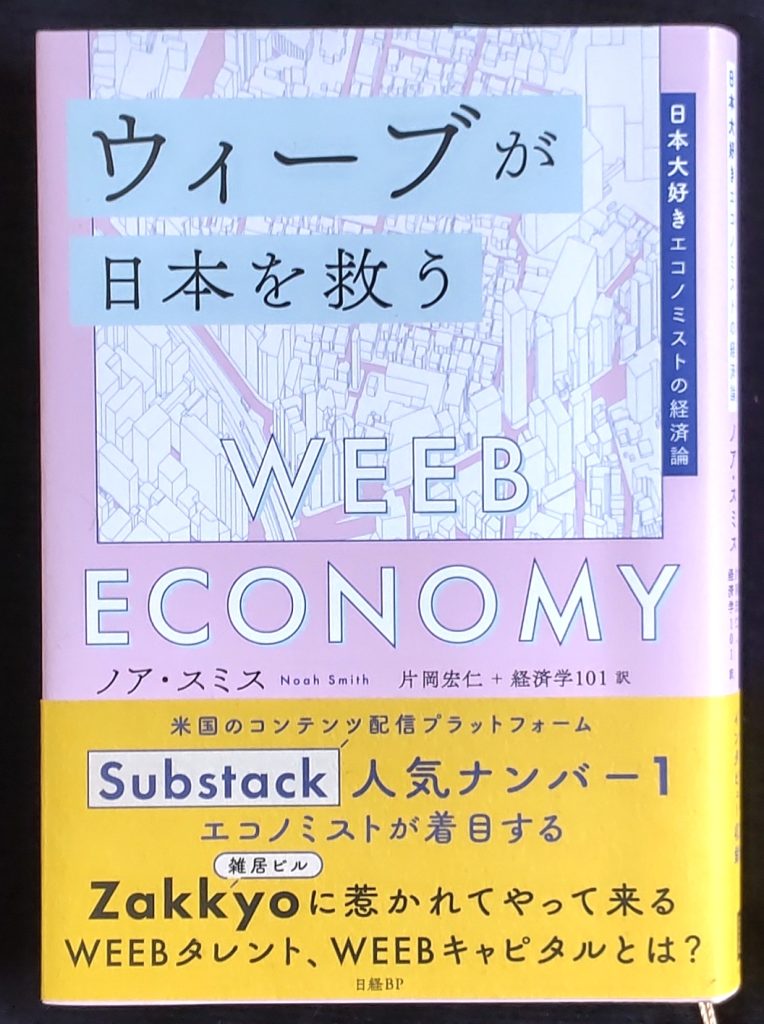
アメリカ人エコノミストのノア・スミスさんは、日本、というより東京を「世界で一番美しい都市、夢と文化とロマンスの流動する場所だ」と賞賛している(『ウィーブが日本を救う』、2025年、日経BP)。
むろん、真逆の声を耳にすることもある。「……東京が世界でも際立って外見が醜い都市である」(コリン・ジョイス『「ニッポン社会」入門』、2006年、NHK出版)。美醜の判断は、人それぞれだ。
◎何もかも詰めこむ「ZAKKYO」

スミス氏によれば、日本の強み、魅力は、安全な都市、素晴らしい交通機関、豊富な住宅物件数、創造的な文化などにある。まあ、これらはしばしば耳にする内容で、珍しい評価ではない。
氏がとくに惹かれるのは、「ZAKKYO(雑居)」。そこに日本の「特別なイノベーション」を見出している。
たとえば雑居ビルであり、横丁だ。「雑居」ビルこそ、日本の消費者の楽園であり、魅力だという。
なるほど、前世紀の映画『ブレードランナー』(1982年)でも雑然と密集する横丁や屋台が描かれていた。監督のリドリー・スコット氏も惹かれたのだろう。
今日では、新宿「想い出横丁」(かつては「しょんべん横丁」と呼んでいた記憶がある)や上野のアメ横、京都の錦小路や先斗町通といった密集・雑居エリアをガイジンさんが占拠するほどの勢いだ。
横丁は「横」に、雑居ビルは「縦」に雑居する。後者の場合、ひとつの建物の中に何もかも詰めこむ。スミス氏は「ZAKKYO」に日本、とりわけ東京の魅力を発見した。

(京都市登録有形文化財)。
かつては新聞社ビルだったが、
今ではカフェ、ギャラリー
などが入る雑居ビルに


こうした分析は、かつて韓国人・李御寧さんが日本文化を「縮み」志向と表したこととも重なる(『「縮み」志向の日本人』、単行本は1982年)。李氏は、折り詰め型弁当箱に「詰める」ことも「縮み文化」の現れとした。
茶室もまた、あえて身を縮めなければ入れない。
いろいろなものを小さくして詰める。それが「縮み志向」である。とすれば、「ZAKKYO」もその現れとみることができる。ちなみに、弁当はBentoとしてすでに国際語化しつつある。

◎「雑居文化」批判
ところで、前世紀すでに自国文化のありようを「雑居」文化と呼び、プラスに評価するのではなく、厳しく批判する学者がいた。政治学の丸山眞男氏。
彼は日本の文化を「タコ壺文化」だと嘆いた。それぞれの専門集団や知識集団、イデオロギー集団、もっと俗っぽくいえば党派的グループが閉鎖的なタコ壺にそれぞれ入りこみ、内輪だけでしゃべり盛りあがるが、壺の外に「共通の広場」が形成されない。ただ、「雑居」しているだけ。それが日本の社会だ、と。
近代より前は中国、朝鮮から、近代に入ると欧米から、さまざまな文化、スタイルを日本は採りいれてきた。
いや、日本にだって万葉、西行、神皇正統記、吉田松陰、岡倉天心、葉隠……ストックはたくさんある。
ところがそれら内外の材料をもとに、日本人は原理的な体系を組み立てられない。数多くのストックは空間的に同時に存在している(並存)けれど、タコ壺のようで、真に交わることがない。「雑居」しているだけで、原理的な体系化ができない。丸山さんはそう厳しく日本文化を批判した(『日本の思想』、1961年)。
◎「きょろきょろしている自分自身は変わらない」
同じく前世紀の前半、哲学者カール・レーヴィットも、次のようにみていた。二階建ての家に住む日本人は、一階では和風で生活しているが、階上にはヨーロッパの学問が紐で通したように並んでいる。ところが一階(和風)と二階(洋風)を往き来する階段が見当たらない。そう疑念を抱いた。いわば、一階と二階がタコ壺化し、「雑居」しているだけだ。
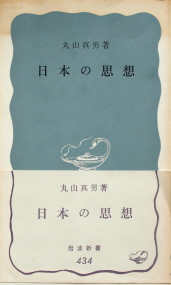
丸山氏からみれば、日本人は「雑居」を「雑種」にまで高められない。そんなエネルギーを主体としてもっていない。だから、日本人の課題を「雑種」として血肉化するため、「主体の確立」を訴えた。それこそが「革命」である、と(同前)。彼なりに、敗戦に至る近代を総括し、戦後民主主義の確立を訴えた。
後年、氏はこう書いている。「私達はたえず外を向いてきょろきょろして新しいものを外なる世界に求めながら、そういうきょろきょろしている自分自身は一向に変わらない」と。そして、その態様を音楽用語「バッソ・オスティナート」(執拗に繰りかえされる低音音型)という表現を用いて批判した。主旋律は外来文化だが、低音部は執拗に同じ音型が繰り返されるだけだ、と。
※丸山氏の論への批評は、別に触れたい。
◎「新しもの好き」
同じ「雑居」(並存)でも、ノア・スミス氏は文化形態として肯定的に、丸山氏は思想構築という視点からは否定的にとらえている。
その是非はここでは措くとして、こうしたありようは、日本人の「新しもの好き」と無縁ではない。
新しいものは、海の向こうからやってくる。日本は海外からいろいろな文化、技術、スタイルを積極的に採りいれてきた。「新しもの好き」である。丸山の言を繰り返せば、「私達はたえず外を向いてきょろきょろして新しいものを外なる世界に求め」てきた。
その姿は外国人たちからもしばしば指摘されている。
エリヴィン・ベルツ博士は、「日本人はなにごとであれ新しいものに夢中になる」と観察している(『ベルツ日本文化論集』)。
キャサリン・サンソムさんは、日本では「今日は目新しかったものが翌日にはもう当り前のものになっている」と驚いている(『東京に暮らす』)。
いずれも二〇世紀前半の印象記だが、一世紀後のいまも、「新しもの好き」傾向は変わらないばかりか、いや増すばかりだ。
日常生活、SNS世界、ビジネスシーン、政治世界、学的世界、批評界……新しいモノやことば(横文字)に飛びつき、何が一番新しいかを競いあう。新しいものにこそ価値がある、と。あるいは、新しい波(流行)の先端に巧みに波乗りすることがよいことであり、お洒落であり、粋である、と。丸山氏が存命だったら、慨嘆をさらに深めることだろう。
ちなみに、列島で「保守」を自認し、古さを守るはずの人たちの多くも、かなり「新しもの好き」である。しかも、「守るべき」とする規範、制度、倫理は、ほとんど「近代」になってつくられたものに依拠している。つまり、一世紀、一世紀半ほど前の「近代」に構築されたものに。だから、多くの「保守」自身、「近代」を相対化できていない。今日、列島の不幸の一因はここにも求められる。
話を戻せば、新しいものを採りいれて熱狂するが、すぐに熱は冷め、捨てられる。それらが血肉化されることなく、消費され、消えていく。これも「雑居」文化の現象であり、それが「雑種」に高められることはない。
他方、スミス氏は「雑居」文化に魅力を感じている。
「雑居」というひとつのキーワードから光を照らすだけでも、日本列島文化の正負両面がみえる。おそらくどんな鍵概念をもってきても、私たちの文化・社会の光と影の両面を映し出すことになるだろう。
◎「もうひとつの近代」
ところで、私が注目したいのは、スミス氏が日本を「もうひとつの近代」を体現している、と表現をしていること。
……、日本という場所は、他の自由で民主的な先進諸国ととてもよく似ていながら、違った感じがする。世界中の人にとって、日本は西ヨーロッパから始まった近代の世界標準バージョンに代わる、<もうひとつの近代>を体現しているのだ。
(『ウィーブが日本を救う』)
日本は欧米と同じように、「近代」を達成した。しかし、どうも「近代」のありようが、どこか異なる。つまり欧米的それとは別の近代をつくりだした、と。彼の目にはそうみえている。
次のような冗談も、氏はよく口にするのだという。「アメリカは今、大転換の真っ只中にある。19世紀から20世紀には、高級品と言えば『何でもフランス風』だったが、21世紀は『なんでも日本風』だね」(同前)。
ずいぶんな持ちあげようだ。
※なお付言しておけば『ウィーブが日本を救う』という本は、半分がタイトルとはつながりにくい経済論で構成されている。
ここまでではなくとも、「もうひとつの近代」として驚き受けとめる感想は、今日、来日するガイジンさん、たとえば知識人たちもよく指摘することだ。
イマヌエル・トッド氏(歴史人口学者・家族人類学者)は、日本を「二つ目の『西洋』」と呼ぶ(『西洋の敗北』)。
哲学者マルクス・ガブリエル氏は、日本を「多層的社会」(『倫理資本主義の時代』)、あるいは「日本にはレイヤーがありモジュールがある」(『マルクス・ガブリエル 日本社会への問い』)と評している。
「もう一つの近代」とは、新しいジャパノロジーを考えるうえで、ひとつの鍵ことばになるだろう。

自分の姿は自分には見えにくい。他人(外国人)が思いがけない見方を指摘してくれるものだ。いや、もしかすると、それは「錯覚」かもしれない。しかし、渡辺京二氏(歴史家・評論家)のことばを借りれば、「錯覚ですら何かについての錯覚」である(『逝きし世の面影』)。
ガイジンさんたちのこういう驚きは、今世紀に入ってから始まったのではない。「もうひとつの~」という印象は、二〇世紀、さらに一九世紀の外国人たちも抱いていた。
いや、さらに「近代」より前、織田信長や豊臣秀吉が存命だった一六世紀に遡っても、「もうひとつの~」(つまりある「達成」状態にはあるが、それが西欧のありようとは異なっている)に驚きを隠さない渡来人たちがいた。たとえば、宣教師アレッサンドロ・ヴァリニャーノもその一人だ。
◎「もうひとつの~」がなぜ重要なのか
いつも、ある達成を形づくっていながら、それは大陸、あるいは西欧とは異なる様相を呈している。それが、近代の場合は「もうひとつの近代」とガイジンさんに言わしめた。
この「もうひとつの~」という意味あいにも、プラス面とマイナス面を見出すことができる。ただ、日本列島文化、日本社会を考察するうえで、とても重要な評価だと思う。
「近代」は欧米が起動させ、推進し牽引してきた。その近代が、今世紀に入り、いよいよどん詰まりを迎えている。人間が生存する地球環境の危機、平等を謳いながらながらも極端にすぎる貧富差の拡大、アメリカに象徴される「自由」や、中国・ロシアらが掲げる「大義」のメッキ剥がれ(すでに前世紀に露わになったはずなのに)の無惨……。それは「近代」を極めた現代の象徴的光景だ。もちろん日本もそれらの小粒化を演じてきたのだが。
「近代」の総括は、すでに前世紀から迫られてきた。しかし、十分になされないまま世紀越えし、今日に至っている。
残念ながら欧米からは、「近代」の抜本的総括がなされにくい。なぜなら彼ら自身牽引者であり、先頭を走り続けてきたからだ。
しかし日本は、近代を達成したものの、それは「もうひとつの近代」であり、欧米的「近代」にどっぷり浸かってない。浸かりきれずに今日に至っている。
とすれば、近代を達成した国でありながら、西欧とは別の「もうひとつの近代」を生み出した日本は、「近代」を相対化する作業を進めるには、好位置に着けている。アドバンテージを得ている。
今日を「近代」のどん詰まりとみて、これを越えよう、このラインから外れようと望むなら、近代を達成しながらも、欧米的近代とは異なる「近代」を実現した(してしまった)日本列島が、その役割の一端を担うことができるはずだ。
◎マルクス・ケインズの予言 ~“暁”の二段階論~
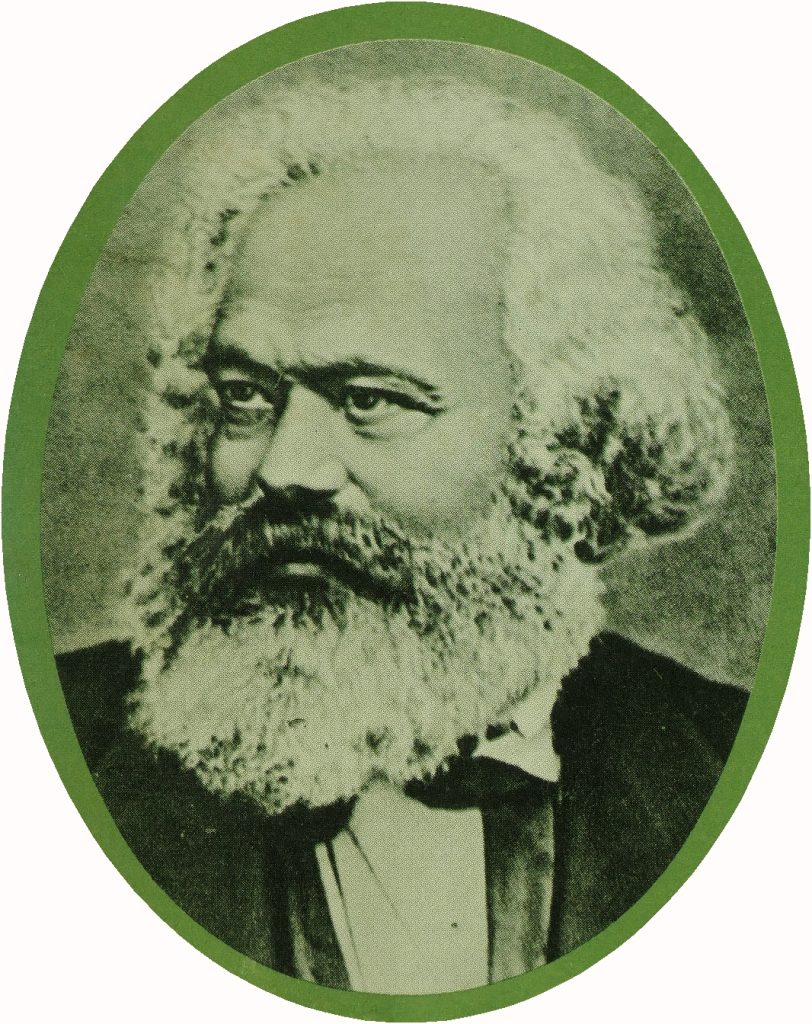
「近代」社会のなかで、私たちが改善・改革を目指すのは大切な作業だ。
と同時に、「近代」を推進してきた原理、力の構造そのものを抜本的に見直す、相対化する作業も切実に求められている。よりよい改善・改革を進めるためにも。
たとえば、経済思想の分野をみてみよう。
一九世紀のカール・マルクス、二〇世紀のケインズは、方法論こそ異なるものに、百年先、二百年先には、「自由の王国」が到来する、と遠望した。生産諸力が飛躍的に向上した“暁”には、経済問題が解決する。食べるために必死に働かなければならない領域(必然性に縛られた領域)から脱し、「自由の王国」が実現する。「経済問題」が解決する“暁”がやってきて、夢のような社会が到来する。人びとは経済問題で頭を悩ますことはなくなる、自由を謳歌できる、と。

しかし、マルクスやケインズの時代から百五十年、百年以上経た二一世紀の今日になっても、どこの国でも「経済」問題がいまも最重要課題とされ続けている。
生産諸力が著しく発展したのに、なぜ「自由の王国」は到来しないのだろう。経済問題が解決されたときに「自由の王国」が到来すると願望する、“暁”の二段階論自体に、思想的な見誤りが潜んでいるからだ。
残念ながら、私たち日本人の多くも、この論にとらわれてきた。たとえば西洋哲学を信奉する日本の哲学者は、マルクスはまったく正しいことを言ったと感嘆し、「そうだ、生産力の向上こそ」と、“暁”の二段階論を持ちあげる。また、「純粋贈与」(という交換様式)を切り札として掲げ、“暁”(ユートピア)を希求する哲学者もいる。いずれも西欧哲学に依拠したものだ。
“暁の二段階論”は、西欧の直線的・進歩主義的歴史観に裏づけられている。また、精神と身体という二元論、もう少しいえば「近代的主体」論に基づいている。だが、それ自体、ひとつの思考型・信仰にすぎず、限界をもつ。
たしかに近代、江戸期までのような大飢饉による大量餓死といった事態を次第に免れるようになった。それは近代が実現した大きな前進であって、先達の営為のお陰だ。
しかし、「自由の王国」を括りだして、必然性(例えば食べること)に縛られることがなくなり、全き「自由」が到来するとする世界観自体、人間のありようを見誤っている。
これに対し、日本列島の基底に流れてきた思考は、そうした西欧的な歴史感、存在観とは異なるものだ。「もう一つの近代」が現出したのも、その影響を受けている。
とすれば、欧米的、いわば“正統”の「近代」とは別の「もう一つの近代」を成し遂げた日本列島の思考のあり方は、西欧的「近代」を相対化しやすいところに位置しているはずだ。たとえば“暁の二段階論”を誤りと指摘できる視線を、日本列島の人びとは持っている。少なくとも欧米人よりは可能性が高い。
◎「半透膜に包まれた国」
なぜ日本列島では、「もうひとつの近代」が可能だったのか。
それは、前述のノア・スミス氏のことばを借りれば、日本が「半透膜に包まれた国」だからだ。
「日本はこれまでずっと外部から選別してあれこれを取り入れることに真価を発揮してきた」(同前)。すべてをそのまま採り入れるのでもなく、すべてをまったく受け入れないのでもなく、海外からやってくるのを取捨選択し、採り入れてきたからだ。半透明の膜に包まれた国だからこそ、全面的に受け入れるのでもなく、全面的に拒絶するのでもなく、「選別」し採りいれ、その後変型させ定着させたりしてきた。
では、なぜ「半透膜に包まれた国」でありえたのか。採り入れたり、採り入れなかったりすることができたのか。取捨選択することができるのか。あるいは変型する余裕をもてたのか。
答えは至って明快だ。日本列島が「島国」であることに負うことが大きい。
これまで大方の評者はそう分析してきたし、私も同意する。もし、海に囲まれない地続き、あるいはそれに近い状態であれば、帝国、大国に制圧され、それまでの文化や言語、政治体制が一掃されたり、抑圧、埋葬された可能性が高い。近代の帝国主義に侵略されたアジア、アフリカ、中南米諸国の歴史をみれば否定できない。
◎「島国」の評価

では、「半透膜に包まれた国」、「島国」であるゆえに出現した、「もうひとつの近代」をどう評価すればよいのか。
評価は、否定と肯定の二つに分けられる。
第一に、これを肯定的にはとらえない立場。単に「島国」という地勢的な理由にすぎないのだから、否定的に評価する。
「島国」であるがゆえに、外国との厳しい争闘にもほとんど遭わず、西欧的な近代的主体を確立し強化することもなく、すませてきた。「もうひとつの近代」は日本人が主体的に形成したのではなく、「島国」であるという偶然ゆえに侵略されず、外来物を取捨選択することを許されてきただけ。むしろ「島国根性」という負性だけが目立つ。
このように、日本列島の文化を冷笑的にとらえる論者も少なくない。日本文化は西欧的な主体を確立できないところに咲いた「遅れた文化」だと。傾向として、おもに左派の人に多い。「標準」をつねに海の向こうに求める。
第二は逆に、「島国」という偶然に求めるのではなく、日本人の“大和魂”、“日本精神”こそが、欧米とは異なる「もうひとつの近代」を実現させたとする見解。日本文化を手放しで絶賛する。日本こそ「世界の真ん中」であるべきだ、と。「保守」を自認する人に多い論である。
◎新しいジャパノロジーへ
私からみれば、これら二者は貧しい対立を構成している。
異なる第三の立場がある。それが新しいジャパノロジーである。
たしかに「もうひとつの近代」がつくられたのは、「島国」という地勢的偶然に負うところが大きい。日本人が確固たる主体性をもってつくりだしたとはいいがたい。そんな強い主体性を日本列島の人びとは有していない(そもそも「主体」、近代的主体性自体が問われている。それはあとで触れよう)。
しかし、だからといって、列島文化を冷笑したり、卑下するべきでもない。「島国」ゆえに許された環境で育まれた列島文化にこそ、欧米的「近代」を相対化し、近代を越える、近代から脱する道標を立てることができるのではないか。
もちろん新しいジャパノロジーは、“大和魂”や“日本精神”を声高に叫び、「世界の真ん中」を妄想するものではない。
では、それはいったいどんなものなのか。この「覚書」連載のなかで、それを示していく。

◎日本列島文化のOS
日本を「辺境」ととらえ、「辺境人」の特性を摘出したのは、内田樹さんだ(『日本辺境論』)。彼は、アメリカ人の国民性格は建国のときに「初期設定されている」とする。たしかにアメリカ人には「国民の物語」が共有されている(にもかかわらず、激しい分断が今日生まれているが)。
ところが、「私たちの国は理念に基づいて作られたものではない」。だから、「私たちには立ち帰るべき初期設定がない」と内田氏はいう。“建国の初期設定”は存在しない。氏のいうとおりだ。
しかし列島に初期設定がないのではない。国家という共同的観念次元ではたしかに存在しない(これに異論を差し挟むひともいるだろうが)。ただし、もっと基底的なオペレーティングシステム(OS)が、日本列島には脈々とはたらき、初期設定の役割を果たしてきた。
パソコンやスマホを起動したとき、あるいは不具合があって再起動するとき、つねに基本ソフト(たとえばパソコンであれば、WindowsやMacOS)に立ち戻って起動し、その上でアプリケーションソフトを動かす。アプリを動かしているのはOS。スマホでも同じだ。
どこの地域、民族にも独自のOSがあるのと同じように、日本列島もまた、独自のオペレーティングシステムを基底ではたらかせながら、その上でアプリを動かしてきた。
繰りかえせば、日本には初期設定がないのではない。重要なことは、アプリケーションソフトを動かす基本ソフトOSが、欧米のそれとは異なる、ということだ。
アプリは、どんな国でも同じように動いているようにみえるが、それを稼働させる基本ソフト、OSの仕様が異なる。そのことがアプリ世界(社会、生活)にも微妙な異なりをもたらす。日本列島を「もうひとつの~」とガイジンさんの眼に映るように現象させているのも、そこから来ている。
◎これまでの日本人・日本文化論を超えて
「日本人とは、日本人とは何かという問いを、頻りに発して倦むことのない国民である」。こう書いたのは二〇世紀の評論家加藤周一さん。氏に限らず、よく指摘することだ。
これまでいくたの日本人論、日本文化論が提示されてきたことだろう。「日本人とは何か」「日本文化の核心は何か」――たくさんの鍵となることば、概念が次々に示されてきた。
たとえば、新渡戸稲造は「武士道」を挙げている。鈴木大拙は「霊性」を、九鬼酒造は「いき」を、岡本太郎や梅原猛は「縄文」を、川端康成は「花鳥風月」を愛でるこころを、西田幾多郎は「絶対無」を、それぞれ挙げている。
徳富蘇峰は日本人を「世界一の田舎者」「世間知らず」「勝手放題の一人よがり」と腐した。
上山春平は日本文化を「凹型文化」と、鈴木孝夫は「他者に学ぶことが恥でない唯一の文明」、「並存文化の国」と、山本七平は「全体空気拘束主義」と、内村剛介は「無原則」と、加藤周一は「みなさん御一緒に」と、柄谷行人は「0記号みたいなもの」と、それぞれ肯定や否定の意味をこめて定義している。
他方、ガイジンさんでは、ルース・ベネディクトは日本文化を「恥の文化」としている。ポール・クローデルは「『あー』ということば」を、キャサリン・ソンサムは「自然との交わり」を、カール・レーヴィットは「シカタガナイ」ということばを、オギュスタン・ベルクは「おのずから」と「すみません」ということばを、ドナルド・キーンは「さだめなさ」の概念を、ロジャー・パルバースは「『どうぞ』と手のひらを上に差し出すしぐさ」や「Self-effacement」を、呉善花は「強固な受け身志向」を、李御寧は「縮み志向」を、それぞれ文化の特徴としてあげている。
むろん、これらガイジンさんは、日本人や日本社会の負の面もたくさん指摘している。
こう並べるだけでも、日本人自身による自己像・自文化像と、ガイジンさんによる日本列島文化・日本人論の違いが明らかで面白い。どうあれ、それぞれが特徴をよく見抜いていることは疑えない。
しかし、それらの分析が日本列島独自のオペレーティングシステムそのものに迫っている、とはいいがたい。これら内外の各論は、一側面をよくとらえていたり、核心近くに迫っているものけれど、列島文化の基底に降りている、とはいいがたい。
本覚書では、これまで俎上に載せられることがなかった、光を当てられることがなかった基本ソフト(OS)、つまり列島の心的な基層領域の「はたらき」を明らかにしたい。それが「新しいジャパノロジー」の使命である。



