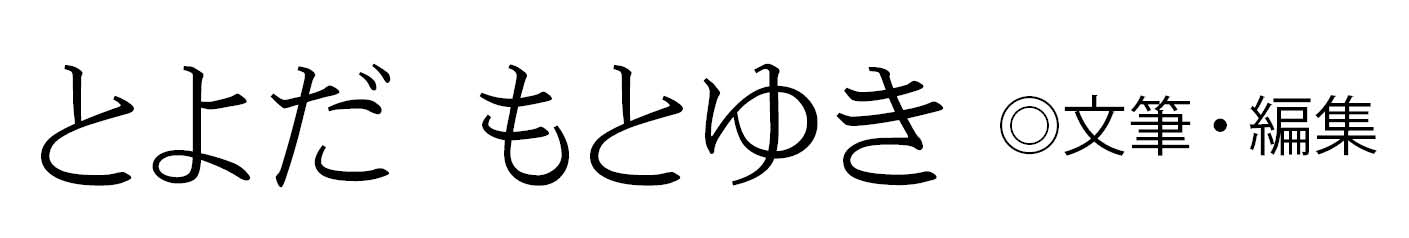家族終焉論にみる思考の躓き
~近代家族の終焉という捏造③~
「ケア」概念の致命的狭さ
「子ども牧場」はコストがかかりすぎるから……?
「家族」と「民主主義」
「愛」と「母性」は支配側のイデオロギー装置か
「再生産」概念に固執する限界
子育ての「支払い労働」化を求める論
「感(はたら)き」から「労働」を見直す
家族終焉論の頓挫を超えて
○家族批判論にみる近代主義の陥穽
上野千鶴子さんの近代家族終焉論には、前々回(①)でみたように、あえて唾して「終焉」を口にしながらも、家族にすがる論の混乱のほか、いくつか思考の躓きがみられる。それは近代主義の陥穽であり、家族論に好ましい影響を与えるとは思えない。
逆にこうした論が、反対側に位置する和辻哲郎のような、共同体絶体主義的な家族論の再生産に寄与することになってしまう。
私は①で、「対をつくることも、つくらないことも自由だ。子をつくることも、つくらないことも自由だ。欲しても子ができないこともある。すべて等価である。しかし、対をつくること、子をつくることを嗤うことが許されるのだろうか」として、上野氏の家族蔑視論への疑問を示した(※対は「婚姻」関係に限定されない)。
さらに②では、加藤登紀子氏の「結婚」に疑義を呈する上野氏自身の発言と実生活(婚姻届提出)の“思想上の矛盾”に触れた。
家族を生きてきたとはいえても、家族論などあまり考えたことがない私は、フェミニズムから糾弾を受けざるをえない事態を多々抱えていることは自覚している。
しかし、上野氏の近代家族終焉論への異議だけは明らかにしておきたい。問題は家族のみならず、自由と束縛、さらには労働(「はたらく」ということ)の領域にまで及ぶことになる。この作業が、西欧近代主義と保守主義という以前から続く不毛な対立を超える道に通じると思うからだ。
ここでは、『近代家族の成立と終焉』だけでなく、氏の他著『家父長制と資本制』(単行本1990年刊、増補文庫本刊2009年)、『ケアの社会学』(2011年)なども参照しながら進めててみよう。

「ケア」概念の致命的狭さ
○女ひとりが担うことになった「ケア」とその「公事化」
『近代家族の成立と終焉』では、次のような問題点が指摘されている。
近代家族(核家族)が成立すると、それ以前は「社会」で支えていた「ケア」(子育て、介護)が、新しく生まれた「専業主婦」である女ひとりで担わねばならなくなってしまった。著者はこれを「ケア」の「私事化」と呼ぶ。女だけが過剰な負担を負わされ、犠牲となる。フェミニズム的視点からの近代家族批判である。
「ケアという重荷は、小規模な近代家族では、たったひとりの成人女性の肩に背負わされていた」。「多くの家族は、ケアの負担に呻吟し、場合によっては崩壊しさえした。そして、その負担のしわよせがもっぱら女性に集中してきた」(同前)。その通りだろう。
それが、主に女性たちの広汎な運動を経て、2000年に介護保険法として結実し、介護の「公事化」が進んでいる。
また、上野氏の次のフレーズも私は全面的に受け容れたい。
女がひとりでも安心して子どもを産み育てることができる社会を。そしてシングルマザーであることに(したがって婚外子にも)どのような社会的なスティグマもペナルティも与えられない社会を。
(『近代家族の成立と終焉』)
これができなければ、「少子化問題の解決」すらありえない。そのとおりだ。ただ、とすれば、たとえば江藤淳を「戦後批評の“正嫡”」などと表現すべきではないだろう。
近代という時代は、「個」の自由追求を推進するのだから、婚姻という制度の倫理的な箍(たが)が弱まる中で、非婚や離婚は自ずと増え、シングルマザーが増加する。男のわがままがそれを加速させ、婚外子も増える。無理矢理、家族共同体的倫理でそれを押さえこもうとするのは転倒である。
こうした中で、介護だけでなく、子育てが女性にだけ負担を強いる現状は理不尽だ。フェミニズムの主張、現に当事者である女性たちの声には耳を傾けなければならない。
○「ケア」の定義
上野氏の家族論の危うさは、その先にある。
氏は介護と子育てを包括する上位概念として「ケア」ということばを使う。
では、「ケア」はどう定義されるのか。アメリカの学者メアリー・デイリーの定義を引用する。
依存的な存在である成人または子どもの身体的かつ情緒的な要求を、それが担われ、遂行される規範的・経済的・社会的枠組みのもとにおいて、充たすことに関わる行為と関係。
(『近代家族の成立と終焉』)
ここで西欧的思考の典型が披露され、上野氏もこの定義にためらいなく同意し、のちに書かれた『ケアの社会学』でもこれを踏襲している。
「依存的な存在」とは高齢者や子どもを指す。
子どもについて考えてみよう。子どもの「身体的かつ情緒的な要求」を「充たす」ことに関わる行為と関係、それが「ケア」とされる。
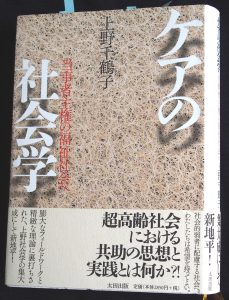
○子育てを「要求充足」だけに絞る思考の偏り
もしこう定義されるなら、「ケア」=「子育て」ではない。あるいは両者を等式で結ぼうとするなら、「ケア」の定義が誤っている。
子どもの要求を「充たす」ことが子育てだという定義は、十分とはとてもいえない。
子育ては、依存的存在の「要求の充足」だけにあるわけではない。子どもの要求に対して、親は修正や停止を求めることも多々ある。
自己の要求が充たされないこともあると体得することも含めて、子は学び育つ。子と親の間では、子(個)の「要求の充足」という一方通行を超えた、心身交流、価値交換に満ちている。そういう過程を経て、親もまた子に学び教えられ、子も育つ(もちろん、ここでの「親」は血縁関係に限定されない)。
そのことを、欧米的思考、いや少なくともメアリー・デイリーや上野氏の視点は欠落させている。上野さんは、ケアとは「相互行為」といいながらも(『ケアの社会学』)、なぜこうした偏った視点を疑わないのだろうか。子どもは独立した人格であるとみる西欧的人間観に無自覚に依拠しているからなのか。子の「要求を実現」することが人格の形成であり「自由」の獲得であり、自立への道である、と理解しているからなのか。
子育ての捉え方から、足を滑らせている。
○「圧倒的に非対称な関係」というなら……
前々稿①でも触れた「没後二〇年 江藤淳展」という記念講演会(2019年)で、文芸批評家江藤淳や近代家族について語っているとき、上野さんは途中で唐突に話題を変え、次のように語り始める。
今、わたしは「ケア(介護)」の研究をやっております。ケアにおける「関係」は、自立した個人間の関係ではありません。ケアする主体とケアされる客体という、圧倒的な強者と依存的な弱者との関係です。近代リベラリズムがカバーすることのできない非対称的な人間関係は、人間社会の中には山のようにあります。それを男性社会は無視してきました。
こうした認識を起点に、日本にもフェミニズム批評が登場します。
(上野『近代家族の成立と終焉』)
突然、「ケア」(介護)の問題に話題を移し、近代リベラリズムではカバーできない非対称な人間関係が、社会には山のようにある、という。
おいおい、とつい口を挟みたくなる。古来、そもそも子と親の関係こそ、近代リベラリズム云々に関わりなく、圧倒的に非対称な関係を形成してきた。それは高齢者と介護者の関係以上に非対称的である。とりわけ子が幼いときは。
○圧倒的に「非対称的な人間関係」を男は無視してきた?
だからこそ、世の「親」たちは「子」を護り育て養うことに奔走してきたし、今もそうだ。
男女の関係性・役割分担の問題点はここでは措かせてもらうが、親は、圧倒的な「依存的弱者」である子を養い育てる経済的基盤を築くために、労働に励んできた(歴史的にはおもに男性が、あるいは女性も、あるいは共同で)。
だから、少なくとも「非対称的な人間関係」を「男性社会は無視してきました」というのは当たっていない。むろん、「(妻)子を養う」という“錦の御旗”のもと、なんでも許されるとする横暴な姿勢、家事負担の押しつけなどで男の問題が免責されるものでないのは当然のことだが。
少なくとも近代にあっては、高齢者以上に圧倒的な「依存者」である子を育てる経済的基盤を築くために、大資産家以外の庶民は必死で奔走してきた。しかも近代にあっては、稼ぎを得ることは楽なことではない。今日でも同じだ。近代に入り社会の生産力が飛躍的に向上し豊かな社会になっているはずなのに、さらに厳しさを増している。こうした中でも圧倒的に非対称な存在である子を護り育てるために、「親」ははたらいてきた(それは子育ての一部にすぎないけれど)。
「ケア」の中の「介護」に非対称の関係を大発見のように語るなら、まず子育て世界からだろう。それを氏は意図をもってかどうかはわからないが、回避している。
話を戻せば、「ケア」を子どもの「要求」の「充足」とだけみるのは、子育てを一方的な無機質的世界に押しこむものだ。
こうした見方は、欲求する主体としての個(近代的主観)を基本とする西欧的思考から生まれ、江藤が評したアメリカの「母子の疎隔ぶり」(『成熟と喪失』)ともつながっている。子どもは立派な人格の持主であるので、一刻も早く母親から分離・独立させるべき、という発想とも重なる。
上野氏はむしろ子育てという「ケア」を「母性」(という幻想)から解放し、サーヴィス労働のように社会が担えばよい、との考えに立っているのだろう。それは、これから触れる「子育て」を「牧場」とみなす考えにつながる。この視点に立てば、子育てが子の「要求の充足」だけですむとみなすほうが論を展開するにあたり、単純で都合がよい。

「子ども牧場」はコストがかかりすぎるから……?
○ケアの完全な「社会化」は到来しない!
前述したように、近代家族がケアの「私事化」を前提に成り立っているとすれば、その脱私事化は「脱近代家族」を意味するはず、と彼女はみている(『近代家族の成立と終焉』)。ケアを「公事化」すれば、そのとき「脱家族」、「近代家族の終焉」がやってくる、と。氏念願の「家族の解体」の到来だ。
ところが、そういう未来図を描きながらも、近代家族が解体しても「依存」の現実そのものはなくならない、とも認識する。
たとえ「依存の脱私事化」が進行したとしても、その完全な「社会化」(すなわち「再生産工場」や「子ども牧場」!)が成立するとは考えにくい。というのも、ヒトがヒトになる過程は市場化や公共化され尽くすには、あまりに厖大なコストがかかるからである。
(『近代家族の成立と終焉』)
こうして、子育ての完全な「社会化」を断念する。理由として、「ヒトがヒトになる過程」、つまり子育てにおいて厖大な「コスト」がかかってしまうことを挙げている。
いかにも上野さんらしい。子育てをコストの問題に収斂させている。負担するにはあまりに厖大なコストがかかるという理由で、子育ての「完全な社会化」を断念する。
逆にみれば、コストがかからなければ、あるいはコストを度外視すれば、「子ども牧場」が実現し、ケアは全面的に「社会化」される(脱私事化される)。そのほうが好ましい、という認識のもとにある。
○近代家族は終焉しない?!
ここにも、依存者である子どもの「要求を充たすこと」が「ケア」であるという一方通行的な関係把握が反映されている。子育て作業は「牧場」「工場」なぞらえられている。だから、コスト問題さえ解決すれば、本来は「子ども牧場」で行うべきということになる。
論を忠実に辿ると、子育ては「工場」「牧場」でなされるのが好ましいが、現実には「コスト」問題ゆえに子育ての完全な「社会化」(脱私事化)が成り立たないので、残念ながら家族で担うことになるし、「近代家族」はなくならないことになる。
とするなら、「近代家族の終焉」は迎えられない。「終焉」「解体」と表現すべきではないはずだ。
○「子ども牧場」を描く思考欠陥
さらに気になるのは、氏が子育てを、あえて挑発的にだろう、「牧場」という比喩で語っていることだ。私はここでも立ち止まってしまう。西欧近代的思考のルーツを想起せざるをえない。
古代ギリシャ(プラトン)では、次のように思考される。神は自ら監督者として人間を「牧養」する。そして神に近い人間は下等な動物を「牧養」する。また、政治家は牧者に、民は羊に喩えられる。
古代ギリシャに限らない。西欧文明のもう一つのルーツの「創世記」でも同様に、聖職者は牧師、司牧者と呼ばれ、民(羊)を統御し導く。
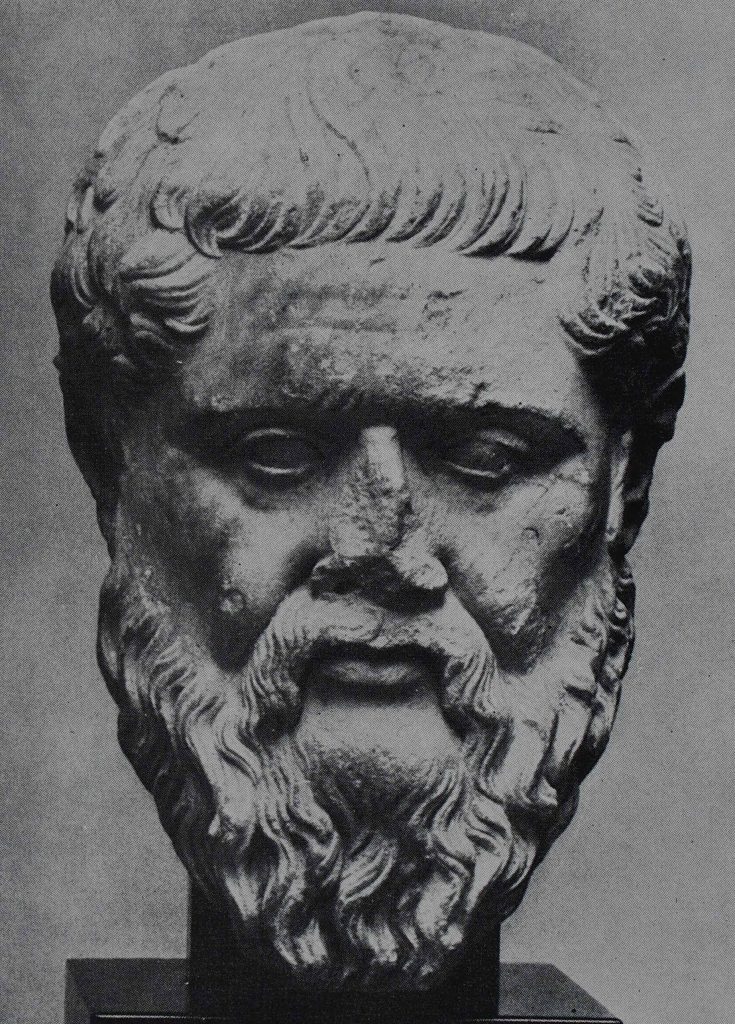
西欧2大思想では、神→人間→動物という上下の支配構造を基礎にしている(もちろん両者の「神」概念は異なるし、近代は「神」が後退し、その死を叫ぶものが増えたが)。
人間が人間を育てることが、羊を「牧場」で「牧養」することに喩えられている。「牧場」に子羊(依存者)を放牧し、草をいっぱい食べさせ、「要求を充足」させること、「牧養」である。子育て・人間支配はそのようにイメージされている。
子の「要求を充足」させればよいという一方通行の「子育て」観と、草を食べたい欲求をもつ羊(大衆)を放牧して「充足」させれば成長するという「牧養」が重ねられる。
上野氏が「子ども牧場」という表現をどこからもってきたのか知らない(おそらく海外文献だろう)が、こういう西欧的な思考のもとにあることは間違いない。「再生産工場」との表現も同じだが、これについてもあとで論じよう。

「家族」と「民主主義」
○「近代家族」に残る家父長制
なんとしても近代家族を批判したい氏は、家族における権力関係にも言及する。
……、実のところ家族に民主主義はない。家族は性と世代とを異にする異質度の高い小集団である。そのなかで権力と資源が、不均等に配分されている。年長の男性が年少の男性および女性を支配し、統制する家父長制という概念は、近代家族にもあてはまる。
(『近代家族の成立と終焉』)
「家族に民主主義はない」とは、男への糾弾だ。
封建的な「家」制度がなくなったはずの戦後家族(近代家族)に家父長制など存在しない、という論はまやかしだ、という。最小家族である核家族にも、「夫の専制支配という家『長』制は存在していた」と。
たしかに、夫婦間の「権力と資源の不均等配分」が女性への抑圧をもたらすケースは多い。21世紀に入った今日ですら、家父長制的支配は残存している(反対に男性が抑圧される場合もあるが)。男女間の「権力」の不均等配分はまさに問われる。
国際家族年(1994年)に国連は「家族から始まる小さな民主主義」をモットーとし「人権、特に子どもの権利、個人の自由、男女平等の促進」を謳った。児童虐待や女性への支配などの事例がなくならない以上、こうした啓発は求められる。
○すべてが権力支配に収斂されるのか
しかし、家族は「民主主義」の運営で貫かれるべきだろうか。
子育ての場合、前述したように、依存者である「子」の要求を充たすだけでなく、その修正や停止を求めるのも、子育ての一環だ。それは子にとって「抑圧」と感じられるかもしれない。
だが、それは不当な「権力の行使」とか「弾圧」と呼ばれるのだろうか。「権力と資源の不均等配分」とみなされるとすれば、子育てなどできない。毎食ファストフード店に出向きハンバーガーとポテトチップスを食べたいと泣き喚く子に対して、その都度、子と熟議を重ね、民主主義的合意を得るまで論議を続け、食事内容を決めなければならないのか。子どもが多い場合、多数決で子どもたちの要求を認めなければならないのか。
ここにも「要求の充足」こそ「ケア」だとする論の無理がみられる。
子が育つにつれ、一般に親と子の関係は、しだいに個と個の関係に移る。そこで「民主主義」的運営が加味されるようになる。この過程でほとんどの親子の間で軋轢や厳しい対立が生まれる。当事者間にじつに深刻な摩擦をもたらしながら、子は大人になり、巣立つ。独立する。それが自然過程だ。
話を戻せば、家族の全領域に「民主主義の貫徹」、権力の「均等配分」など求めることはできない。

「愛」と「母性」は支配側のイデオロギー装置か
○「愛」も「母性」も家父長制の産物?
彼女は、「愛」も「母性」も、男性支配のためのイデオロギー装置にほかならず、そのイデオロギーを女性自身も愚かにも信じている、とする。
「愛」とは夫の目的を自分の目的として女性が自分のエネルギーを動員するための、「母性」とは子供の成長を自分の幸福と見なして献身と自己犠牲を女性に慫慂(しょうよう)することを通じて女性が自分自身に対してはより控えめな要求しかしないようにするための、イデオロギー装置であった。
(上野千鶴子『資本制と家父長制』)
「愛」とは男が女を支配するための「イデオロギー装置」であり、「母性」とは女に自己犠牲を強いる家父長制の産物である、とする。「愛の共同体」なんて神話であって、「家族の中に現にある格差と不平等を、愛と自発性の名において覆い隠すのに役立っている」と(同前)。
○「愚かな大衆を啓蒙するマルクス主義」の病
だが、すべての「愛」、すべての「母性」(親性)は支配側が企むイデオロギー装置によって生みだされるのだろうか。
たしかに、「愛」「母性」の強調が、それぞれの社会体制のもとで、男の支配を強めるように機能することはずいぶんある。といって、すべての「愛」「母性」は、男、支配層のイデオロギー装置によってでっちあげあれた偽の意識である、と否定できるものだろうか。
古来、人々が「愛」の文学や音楽や映像に熱く惹かれる姿が、上野氏の眼には、権力や男が設けたイデオロギー装置に踊らさせている愚かな大衆として映っている。
そういう見方は、20世紀のマルクス主義全盛時代に、社会や生活、意識の諸問題のすべてを階級的イデオロギーに収斂させる思考型と同じだ。革命主義者やマルクス主義知識人からみれば、愚かな大衆は、支配層・ブルジョア側が仕掛けるイデオロギー装置の罠に気づかず、没階級的な奴隷意識・虚偽意識に囚われ、革命に起ちあがろうとしない、と。決起せよ、とアジテーションする。
こうした思考型は、今日の陰謀論ともあまり変わらないようにみえる。
彼女の「マルクス主義フェミニズム」の「愛の共同体」批判には、マルクス主義的思考の欠陥が反映されている。フェミニズムから批判を加えているとはいえ、そもそも21世紀に入っても「マルクス主義」が護持されていることにめまいを覚える。

「再生産」概念に固執する限界
○「再生産」とは
上野さん的「マルクス主義フェミニズム」のさらなる問題点として、「労働力の再生産」という概念が挙げられる。
一般的には聞き慣れないだろうが、マルクスが経済学批判で用いることばだ。
「労働力の再生産」とはどういうことか。市場に売り(貸し)に出される労働力は、職場で働き心身を消耗する(働いて1日が終われば疲れる)。休養・睡眠・栄養補給が必要となる。このように労働力を回復させ、再び活力を与え、職場で労働力を発揮できるようにすることを、マルクスは「労働力の再生産」と呼ぶ(『資本論』等)。
そして、自分と同じような新しい労働力(子)をつくるのもまた、労働力の「再生産」である。将来の労働力を育てるのも、再生産労働の重要な役割だ。
これらの「再生産」の活動は、基本的には、家庭領域で行われる。
マルクス主義は「人間生命の生産・再生産」を「労働」と呼ばない。マルクス主義はモノの生産のみを「労働」と呼ぶ。フェミニズム(上野氏)はこのようにマルクス主義を批判する。
○「再生産」を「支払い労働」から外したマルクス主義
氏が問題提起するのはここからだ。市場(資本制)と男の論理(家父長制)を批判する。
問題の核心は、労働の「収入を伴う仕事」と「収入を伴わない仕事」へのこの分割、そしてそのそれぞれの男/女への性別配当にこそある。家事が「収入を伴わない仕事」であるとは、それが不当に搾取された「不払い労働」であることを意味する。この「不払い労働」から利益を得ているのは、市場と、したがって市場の中の男性である。
(『家父長制と資本制』)
支払われる労働と、支払われない労働がある。前者は利潤を生むための労働であり、後者は利潤を生まない家庭での労働だ。
資本制は剰余価値を生むことを目的とする。ところが、「再生産労働」は価値を生まない。マルクスが経済学批判で用いる「再生産労働」(家事労働)は、「価値」を生む「生産労働」の反対側に対置している。公の経済領域から外れた裏方の話とされる。つまり職域での「生産労働」に対して、家事労働(再生産労働)は補助的なものにすぎない。価値が低い。対価が支払われない。
さらに、再生産労働もじつは利益を生みだしているのに、それを「市場」と「男性」が搾取している。そう告発する。
マルクス主義はこのことに無自覚だ。そこでフェミニズムは、マルクス主義が「人間生命の生産・再生産」を(賃金)「労働」から除外してしまい、「モノの生産」を優先する思想であることを批判する。
○「再生産」という定義への疑い
「労働力の再生産」は、はたして二次的で「生産」の下位に置かれるべき過程なのだろうか。
なぜ人間の生命を産み育て、その死をみとるという労働(再生産労働)が、その他のすべての労働の下位におかれるのか、という根源的な問題である。この問いが解かれるまでは、フェミニズムの課題は永遠に残るだろう。
(同前)
この問いかけは根源的な提起として正しい。「再生産」労働が蔑視されるべきではない。
しかし、こうした労働をそもそも「再生産」と呼び続けるのは妥当ではない。
たとえば、「食」は労働力(を提供する労働者)に単にガソリンを補給する過程ではない。食とは、いのちを育む過程であり、他者との関係を育み、文化を育む場でもある。食という領域は栄養補給にとどまらず、「こころ」「いのち」を育み、つながろうとする、心的価値交換の過程でもある。
家庭領域の「労働」を単なる「再生産」という概念に押しこむことはできない
ところが、西欧的知はそのように評価はしない。あるいは、軽視する。食物は食べてしまえば、何も残しはしない。日々消費され、消えていくだけだ。そんな食に従事する労働(活動)は、最下位に位置づけられるべきだ、と。
身体に関わる労働など、なんの痕跡も残しやしない、価値のない労働とみなされる。それが西欧哲学のルーツのひとつである古代ギリシャ(プラトン)以来の労働観である。
なにしろ、「身体は牢獄」だ。そうみなすプラトンからみれば、食づくりは主人(治者、賢人、高貴者)が手を染める仕事ではなく、奴隷か身分の低い者、あるいは女に任せておけばよい。
近現代もそうした発想は変わらない。ハンナ・アレントあたりは、そんな思考の典型だ。
「再生産」という概念自体、西欧的思考から生まれる侮蔑的な表現だ。
○子の誕生は「再生産」概念では括れない
だから上野氏が指摘するように、「人間の生命を産み育て、その死をみとるという労働」つまり子育てと介護が、「再生産」労働として、他の労働の下位に置かれるのは不当である。その通りだ。
しかし、上野氏自身もそうした批判を徹底できていない。「再生産」ということばにこだわり、「再生産」労働という概念を壊さないからだ。
そもそも、家庭とその周辺領域の労働を、マルクス経済学に倣って「再生産」労働と呼ぶこと自体がふさわしくない。

「再生産」とは同じものを再び生産すること。
マルクスの師匠筋にあたるヘーゲルは、「人間」ではなく「動物」について、次のように書いている、「生命のあるものは、このように自己を再生産するものとしてのみ、存在し、自己を保持する」。「生命のあるものは、自己を現在あるところのものたらしめるものによってのみ、存在する」と(『エンチュクロペディー』)。
難しい言い回しだが、要すれば、(同じ)いのちの繰り返しや連続性が「再生産」とされている。それは精神を有する人間の行為ではなく、動物の次元の話とされる。「再生産」とはそういう文脈で語られている。
マルクスはおそらくヘーゲルあたりからこの概念を引っ張ってきて、使っているのだろう。
子を産み育てるという過程もまた、「再生産」として括ってすませることはできない。なぜなら、親にとって子は自らによってつくったもの(連続)であるが、同時に、まったくの他者(非連続)でもあるからだ。たえず、親は子の他者性と出会う。思い通りにはならない。連続しているはずだが、非連続でもある。親と子との間は、深淵によって断絶されている。
つまり子の誕生と子育ては、たんなる「再生産」(同じものを再び生産する)という概念には、まったく納まらない。
○「生産」と「再生産」という区分けの誤り
労働者の日々の「再生産」だって同様だ。人間(マルクス経済学では「労働力」)は日々学び、日々成長する。あるいは成熟したり、衰える。昨日の私と今日の私は同じではない。ある商品を繰り返し生産する「再生産」とは異なる。
反対にマルクス主義が価値を見出す「生産労働」に目を転じるなら、そこでは同じ商品を再び生産することで利潤を得る。むしろ同一商品の生産(再生産)が大量であるほど利潤増をもたらすので好ましい。つまり同じ生産を繰り返すのだから、マルクス経済学上の「生産労働」だって「再生産労働」とも呼べる。
だから、ボードリヤールのようなフランスの拗ねた哲学者は、(モノを生産する)労働だって再生産労働にすぎないと皮肉った。
○等価交換できない「労働」
繰り返せば、家族域における労働は、市場で利潤創出をめざす「生産労働」と比較し、下位に置かれるべきものではない。むしろ、上位に位置するといってもよいほどだ。
子を生み育てるのも、単純労働のような響きに通じる「再生産労働」という枠にはとうてい収まらない。
家庭領域の「労働」が利潤を生まないのは、それ自体が商品とならないからだ。そこでの活動、たとえば親が子に関わる活動は、計測できる商品の売買(等価交換)として成立しないからだ。商品化しがたい(等価交換しがたい)活動が行われ、家族間で心的・身的価値が交換されているからだ。家族(対)の核心は、剰余価値とか利潤とか、商品売買とかの経済世界の介入を拒む関係世界だからだ。
なにも、家族、家庭を美化するわけではない。「すさまじい親子関係」(ボーヴォワール)であったり、すさまじい男女関係が渦巻くことも日常的にあるけれど、どうあれ、たがいに等価の価値を計算し、商品を交換し、利潤の創出を願う関係世界ではない。
たしかに家族の領域には、衣食住に関わるさまざまな商品、サーヴィスが入りこむ。たとえば20世紀半ばには洗濯機が、のちには冷凍食品が、今世紀にはAIロボットが登場し、家族はそれら商品を利用する。しかし、家族どうしが互いを商品として等価交換を行っているのではない。むしろ、商品交換しえない世界を生きることで、家族(対)は成り立つ。
上野氏は「再生産」ということばを手放さないが、その概念自体、対的世界、家族の営みに適用するのはふさわしくない。

子育ての「支払い労働」化を求める論
○「ケア」と「支払い労働」
近代前の子育てはたしかに、親だけでなく、親族、周囲の大家族や使用人らによって支えられていた。今日よりも「社会化」されていた。上野氏は、家族が最小単位(核)になった今日、ケアの負担が女性1人にのしかかってくる現実を告発した。
こうした中で、女性たちを中心とする運動の高まりが力となり、介護保険制度が施行された。少なからず問題を抱えるものの、高齢者・障害者への介護の社会化は大きな前進である。
上野氏はさらに子育ても「社会化」すべき、つまり「支払い労働」化すべきと主張する。
ケアが「支払い労働ではない」「支払い労働であってはならない」と考える人々は、急速な現実の変化に押されてもはや少数派でしかないが、……。
(『家父長制と資本制』)
氏が使う「ケア」概念には「介護」と「子育て」が含まれることはすでに述べた。氏は子育てにも「支払い労働」を適用したいのだ。「公事化」したいのだ。「子ども牧場」がその究極形態である。
だが、これまでみてきたように、高齢者「介護」と「子育て」は異なる。高齢者はすでに人格を形成した人たちだ。老いて「依存的存在」とはなっても、人格の主体である。だからその「ケア」を「要求の充足」ととらえてもおかしくはない。だが、「子育て」という「ケア」は高齢者へのそれと異なる。
「ケア」(子育て)の「支払い労働」化は可能だろうか、妥当だろうか。
彼女の立場からすれば、むしろ子育てを「支払い労働」化するほうが、「母性」「父性」イデオロギーの罠からの解放へ近づくので好ましいだろう。
○子育てにおける「労賃」の支払い
氏の論に従えば、女の「家事労働」を「不払い」として利益を搾取してきたのは「男」(夫)か「市場」(企業か社会)である。
搾取者が「男」(ときには「女」)である場合、搾取は家庭内のことであるので、対の相手から取り戻すほかない。平たくいえば、労力の負担配分を変えるか、負担割合に応じた家計から支払いをするなど、家庭内でやりくりするほかない。よくみられるケースだが、給与が振り込まれる口座を被搾取者である「女」(あるいは主夫である男」)が握り差配すればよい。これを労働の「不払い」の奪還としてよいものかどうかは疑問だが。
もうひとつは、「市場」(企業か社会)による搾取からの奪還。たとえば家族手当(の増額)も、不十分とはいえ、そのひとつだろう。
あるいは「子ども牧場」「再生産工場」をつくれば、親は子育てという役割を免除されることになるから、「不払い労働」自体、生まれない。
この場合、「牧場」労働者、「工場」労働者が子育てを賃労働として担うことになる。たしかに一部は昔から保育サーヴィス労働で子育てを側面で支えてきた。
どうあれ、社会的なしくみをつくった場合、家族以外の労働者に子育て「賃労働」の支払いをする。
しかし、子育ての基本は労賃として支払われる労働によってなされるべきなのだろうか。
○「支払い」への返済を要求する親の出現
対的世界の現場である家庭で、経済原理(等価交換や労賃支払い)を拡大し、貫徹(工場化)しようとすれば、子と親の間の心的・身的価値交換は後退し、減る。いや、消滅するのかもしれない。
上野氏は子育ての「工場」化、「牧場」化を希求するが、そもそも子と親の関係は、労働(力)の提供と賃金支払いという等価交換で築かれる世界ではない。子と親のあいだでは、親が労力や心情(情愛)を注ぎ、これに対して子もまた動きや心情を返してくる。ささまざまな活動やこころの価値の交換が行われ、そのなかで子の心身が育まれる。それは、経済社会での「賃労働」の提供とその対価支払いの関係世界とは異なる。
ときには誤解する親もいる。子にこれだけの支払い(投資)をしたのだから、大人になったら、利息を付けてリターンを支払え、と子に要求する発想だ。子が社会で働けるようになるまで数千万の費用を要したから、利息を付けて返済せよ、という論になる。
この親の場合、家族世界を等価交換の論理(経済原理)で貫こうとする。上野氏の子育ての「支払い労働」化論は、このような親の考えと親和的である。
○すべてを「労働」へと収斂させる誤り
「人間生命の生産・再生産」を「労働」と呼ばないというこのマルクス主義の定義こそが、「モノの生産」優位の思想からきていると、マルクス主義フェミニストは批判しているのである。
(『家父長制と資本制』)
こうして上野氏的なフェミニズムは、モノを生産しない「再生産」をも「労働」の枠に組み入れるよう主張する。「労働」と認め、労賃を支払えという主張になる。子育てを近代的「労働」範疇に無理矢理押しこめ、賃金を「支払え」と主張し、親子の心身の価値交換世界を、経済的等価交換の世界に組み入れようとする。
方向が逆だろう。氏自身、「労働」の見直しを訴えているのだからだ、子育て(「再生産」労働)を「労働」に組み入れること(「支払い労働」化)で落着させるのではなく、むしろ「労働」概念を一度解体してみるべきだ。

「感(はたら)き」から「労働」を見直す
○問われているのは「労働」の概念
上野さん自身、重要な指摘をしている。
……、女性が「労働」の場に参入していくことが、男性と同じ「労働」疎外のもとに置かれることであれば、何の意味もない。女性の「労働」参加は、「労働」の意味のつくり変えを、不可避的に要請する。
(『家父長制と資本制』)
男性の「再生産」(家事労働)への参加も同様だと言う。その通りだ。
問いは、支払われるか不払いかと立てられるのではなく、「労働」のとらえ方と関係性そのものへと向けられるべきはずなのだ。
生産労働と家事労働のうち一方を特権化するのは、いずれもまちがっている。問題なのは労働のこの分割それ自体、そして「労働」と「非労働」の分割を可能にする、「労働」概念そのものである。
(同前)
そう。問われるべきは「生産労働」と「再生産労働」、「生産労働」と「家事労働」という対項の立て方だ。まさに「労働」概念そのものが問われる。
しかし、氏は結局「家事労働」「ケア」を「支払い労働」に組みこむことに求め、それ以上は問うていない。
○近代に生まれた「労働」
「労働」という概念を一度解体して捉えなおすことが求められる。
「労働」ということばが日本列島に生まれてから、まだ1世紀少々しか経っていない。「働」は日本の国字であり中世からみえるが、「労働」という熟語が列島に登場するのは、20世紀に入ってからだ。labourの訳語として、「労働」ということばは産業資本主義の勃興期に生まれた。
近代の前、「生活」と「働くこと」の境目は曖昧だった。働くことが生活であり、生活することが働きであった。「はたらき」は、たとえば江戸期の医者安藤昌益のように、「感」の字を当てて「感(はたら)き」と書かれることもあった。いわば、「生きてある」こと自体、「感(はたら)き」であった。
このばあいの「感(はたら)き」とは、ひとが他者や自然にはたらきかけることであり、同時にはたらきかけられることである。たとえば大気を吸い吐くこと(呼吸)だって、自然との交換であり、はたらきだ。つまり、生きること自体が「感(はたら)き」としてある。
ところが、近代に入り、工場などの生産場への労働力の集約化が起こり、「労働」が生まれ、労働とそれ以外の領域に明確に分けられ、利潤を生む労働に労賃が支払われるようになった。逆に「労働」以外の場での「はたらき」(たとえば家事労働)は労賃不払いの領域へと追いやられた。
要すれば、「労働」は近代の産業資本主義とともに生まれたもので、「感(はたら)き」の一部にすぎない。そういう視点から「労働」を相対化する。
※拙著『「労働」止揚論 ~「労働」から「感(はたら)く」へ~』
○近代の産物である「労働」のみなおしへ
問題の本質は、だから不当に支払われない「家事労働」(子育て)に支払いを要求することにあるのではなく、「労働」概念そのものをもう一度見直すことだ。
上野さんは、家事労働が「労働」扱いされない、あるいは二流の労働扱いされ、労賃が「不払い」であることに抗議する。家事労働を一流の「労働」に格上げし、「労働」として認定し、搾取(不払い)をやめ、労賃を支払えと。だが、それは対、家族内に経済原理を拡大させることを意味する。
問題は「労働」概念そのものだ、と指摘するなら、家事労働の「労働」(賃労働)への格上げで問題は解消しない。事態はもっと根底的に問われるべきだ。
※ここで、「感(はたら)き」の視点から「労働」(そして「家族」)を見直すための予備的なテーゼを書き始めたが、さらに原稿が膨らんでしまうので、今回は割愛し、別の機会に明らかにしたい。

家族終焉論の頓挫を超えて
○恋愛、性愛、情愛
「恋愛」はloveの翻訳語として明治初期に生まれたことばである。この訳語「恋愛」も含めれば、「愛」は3つのかたちに分けることができる。恋愛、性愛、情愛。もちろん3者は明確に分離できるものではなく、重なりあい、各要素のどれかが強かったり弱かったり、激しく衝突しあったり、いずれかが喪われていることもある。
次第に浮かびあがってくるのは、上野さんの家族論や愛をめぐる論考では「情愛」の要素がかなり希薄であるということだ。「ケア」論や「愛の共同体」論批判、「愛」「母性」のイデオロギー装置論などを通じて示される方向は、情愛の世界を無視するか軽んじて、家族を近代的な個と個の関係に組み替え、「支払い労働」や等価交換に集約させていくことにあるようにみえる。
本居宣長は、「情」という漢字に「こころ」とルビを振った。宣長だけではない。しかも情は対関係世界だけに固有なものでもない。
生の営みから育まれる「情愛」が果たす力はけっして小さくない。それは日本列島における倫理の問題ともつながっている。
○示せない「新しい物語」
江藤淳『成熟と喪失』(文庫版)に寄せた解説を自著『近代家族の成立と終焉』に収録するにあたり、上野氏は「『母』の戦後史」と改題し、前文と後文を付け加えた。
前文に「日本人と『倫理』」という小論を、後文に「『近代家族』を超えて」という小論を付け、「倫理」をテーマとして前面に押し出した。
氏によれば、日本では1980年代から90年代にかけ、「父の喪失」と「母の崩壊」が「近代家族の終焉とともに、常態化しつつある」とした。戦後は家族が倫理の基礎とされてきたが、「『家族の物語』の耐用年数も尽きたようにみえる」。
そして、「わたしたちは新しい物語を編み出すことができるのだろうか」と問うて論を結んでいる。
しかし上野氏の家族論は、「恥ずかしい父」「苛立つ母」「不甲斐ない息子」「不機嫌な娘」という近代家族を「本当に困ったもの」と嗤うものの、自らは「倫理の基礎」や「新しい物語」の方向をまったく示しえていない。
限界は彼女が近代的思考の枠に依拠し、これを相対化できないところにある。「ケア」の捉え方、家族と民主主義、権力の不均衡配分といった、西欧近代主義的視点から近代家族を批判しているだけだからだ。対的関係をとらえそこなっている。
江藤淳や彼女にとって倫理は、天上から降ってくるか、あるいは優れた「知」が指し示すものとされるようだ。列島の人々の存在観に裏打ちされた情愛が倫理を発生させる現場をみようとしない。
○家族は「たえず開きつつも、必然的にまた閉じていく」
最後に、ぶっきらぼうに投げ出すようだが、同世代の優れた哲学者であり思想家だった小阪修平さん(1947~2007年)が遺した家族論の一節を引用して、3回にわたる「近代家族の終焉という捏造」論のキーボード入力をお終いにしたい。
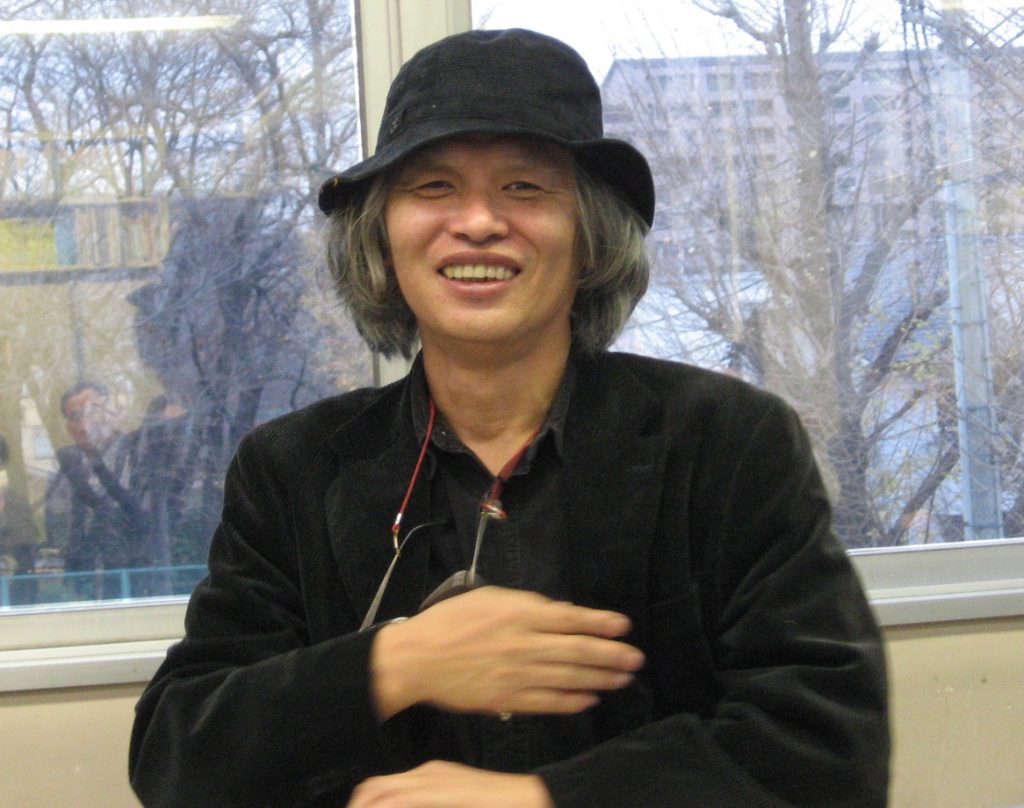
私も属する“戦後生まれ”が1970年代に友だち(同志)のような対関係を築き始めると、商戦狙いの産業界が「ニューファミリー」などと名づけて消費を煽ったが、その核家族的理念も崩壊し始めた1980年代半ばに書かれたものである。
すでにこのとき、小阪さんは「マイホームは消費生活への解体以上の意味をつくりえなかったのではないか」という印象を抱いている。
家族は、時代によって過剰に、あるいは過小に評価される。たしかに当時、「家族の意味の喪失」「家庭内での断絶」「父親の不在」といった、ちょうど上野氏が『抱擁家族』にみたような社会的事象を小阪氏も受けとめている。
ここから上野氏の場合は家族の解体を志向する。対の世界を、近代的理念のもとでの透明な個と個の関係に移行させようとした。誰にも縛られたくない、誰も縛りたくない、と。そして、すべての「労働」(「感(はたら)き」の「賃金支払い」化を求める。
しかし、小阪氏は近代的理念にすがるのではなく、家族のテーマを自ら抱え、そこで踏みとどまって思考する。
家族が「具体的な感情のるつぼとして生きられてしまう」のはなぜか。それは「わたしたちが身体によってこの世界に棲みついているということが、家族という関係のなかでいちばんあらわになるから」と(太字は引用者)。
こうした基本を押さえた上で、次のように記している。
家族は自立しようとする意識にとっては、しばしば悪しき自然だと映ずるが、ひとが家族であることの膠着、ひとが家族であることの意味は、この自然性にあるのだとわたしは思う。家族は必然的に意味をはらむものだが、それはしばしば、既存の社会のコードと重ねられてあらわれる。ここに家族の存在にとってはきわどい場所があり、家族と社会の接点はつねに揺動せざるをえない。そして家族とはたえず開きつつも、必然的にまた閉じていくようなそういう相剋をはらんだ存在であるしかない。
(小阪修平「家族の時代」)