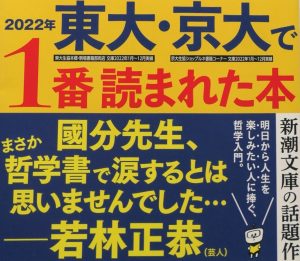『パーフェクトデイズ』 PERFECT DAYS
[雑記帳]
Days of HIRAYAMA ~公共トイレ清掃、生活の営み、日本列島的労働観~

東京・渋谷区の公共トイレ清掃員の生活が淡々と描かれる映画。
こころを静かに動かされた。ありがたいことだ。
その理由を探る。
◎繰り返しの日々
公共トイレの清掃を請け負う中年男は「平山」という。小津安二郎監督作品に登場する笠智衆さんはしばしば「平山」姓を名乗る。小津さんへのオマージュなのだろう。
「平山」の一日は、近くの路上を掃くホウキの微かな音で目をさますことから始まる。
布団をたたみ、台所で歯を磨く。室内の、盆栽とは言いがたい(が逆に味わいのある)若木に水を吹きかけ、仕事の道具類を身に着け、家を出る。
まどろむ朝の空を見上げたあと、自動販売機で缶コーヒーを買う。
軽自動車に乗り、渋谷に向かう車内では、カセットテープに入った好きな音楽を流し、到着すれば、さっそく公共トイレ清掃業務に就く。
昼食はコンビニで買ったサンドイッチを神社境内で食べ、高い木々から漏れてくる陽光の絵をポケットカメラに収める。
仕事を終えて家に戻れば、銭湯で湯船に浸かり、浅草駅地下街の呑み屋でグラスを傾ける。
夜は布団の上で古い文庫本を開き、まどろみ、眠りに就く。
◎生活音と音楽
こうした日常の映像とともに、生活音がクリアに響いてくる。
起きてすぐの「平山」さんの歯磨きの音。ずいぶんと勢いがある。はじめはびっくりしたが、日々の繰り返しに、こちらも馴染み始め、いのちの音として響いてくる。
ふつう、生活から生じる音は雑音として重視されない。しかし、日常のそんな音が、とてもいとおしく聞こえてくる。不思議なことだ。
自販機で買った缶コーヒーの落下音はずいぶんと賑やかで、早朝、近所迷惑になっていないか、気がかりだが。
音楽は、「平山」さんが通勤用の軽自動車内でかけるカセットテープ以外には流れない。それもシンプルでよい。ゆえに作曲家もこの映画にはいない。
◎「清潔」と簡素な美
「平山」さんは、人が嫌がる(はずの)公共トイレ清掃という労働を、毎日きっちりこなす。様々な道具を使い分け、手順よく磨くように掃除する姿に、職人の矜持のようなものを感じる。公共トイレという日々刻々汚れる場所を、利用者に快適に使ってもらえるように清潔に保つ。
彼が生活する簡素な部屋も、「清潔」が保たれていて、なぜか味わい深い。

ふと想い出すのは、500年以上前、安土桃山時代に来日した宣教師アレッサンドロ・ヴァリニャーノが、日本と日本人について漏らした言葉だ。
彼は、日本家屋について「板や藁で覆われた木造で、はなはだ清潔でゆとりがあり、技術は精巧である。屋内には何処もコルクにような畳が敷かれているので、極めて清潔であり、調和が保たれている」と(『日本巡察記』)。
こうも書かれている。列島人は庶民も貴族も「極めて貧困である」が、「貧困は恥辱だとは考えられていない」、「彼等は貧しくとも清潔」であると。
宣教師は、日本人を「貧しくとも清潔」と評した。本質を衝いた彼の指摘は、5世紀以上を経た今日も、列島人に継がれている。
ヴァリニャーノが感じた列島人の「清潔」への志向は、「平山」さんの簡素な畳部屋の整理整頓のみならず、彼の仕事ぶりともつながっている。そう思う。
これは日本列島人が、ほぼ無意識で抱く存在観によるものだ。
列島人は、(人間自身を含む)自然の生成に驚き、感謝し、自然と感(はたら)きかけあう。そして、いま「生きてある」ことを「ありがたい」と受けとめる。自然と親しみ、慈しみ、いまを「よし」と受けとめる。ゆえに、空間を清潔に保ち、簡潔な美を求める。
◎トイレ清掃と列島の「労働」観

それは「労働」にも反映される。
たしかに今日の労働は「賃労働」でしかない。ただ、その「労働」を通じて、心的価値を自己以外とつねに交換しあっている。「労働」の枠をはみ出し、「感(はたら)い」ている。
かつて、列島人は、「はたらく」を「感(はたら)く」と表記していたのだ(拙著『「労働」止揚論 ~「労働」から「感(はたら)く」へ~』)。
何も、列島人が他に抜きんでているなどというつもりは毛頭ない。ヴァリニャーノも列島人の負性をたくさん直視している。ただ、「生きてある」ことを「ありがたい」と受けとめ、ともに感(はたら)きあう、列島の存在観、労働観は、いま海外に訴えかけてよいのではないか。
いったい、「平山」さんがどのような経緯で公共トイレ清掃の仕事に従事することになったのかはわからない。
どうやら過去にある種の「断念」があっただろうことは、容易に想像がつくし、姪の登場でその一端が示される。
自ら欲してこの職に就いたのか。あるいは、強いられるようにして就いたのか。どちらかはわからないが、少なくともいまは、この労働の日々を「よし」と受けとめている。
余談になるが、「平山」さんは、古新聞紙を水で濡らしてちぎり、畳に撒き、それをホウキで掃いていた。若い人にはわかりにくいだろうが、濡れた新聞紙の塊に塵や埃を吸収して掃除しようというものだ。
じつは私自身、京都に仮住まいの時代、古いマンション部屋を、同じスタイルで掃除していた。21世紀に入ってからのことである。
◎西欧的労働観の偏り
ところで、「平山」さんが担うような「労働」は、西欧近代的な知からは、最も価値のないものとみなされる。一例として、20世紀のドイツ系哲学者ハンナ・アレントさんの論を採りあげてみよう。
彼女は、人間は「自然や地球の召使い」であってはならない、「支配者」でなければならない、という(『人間の条件』)。ゆえに、人間が自然的存在であることから生じる「必然性」(有用性)に縛られることをとことん嫌い、「労働」を徹底して蔑んだ。
彼女は、人間が周囲に働きかける動き(広い意味での活動)を、「活動」、「仕事」、「労働」の三つに分けた。
まず「活動」(action、Handeln)。これはモノを介在させない、いわば人間の自然性に関わらない活動で、言論や政治活動がこれにあたる。精神的な活動で、もっとも価値が高い。
次に、「仕事」(work、Herstellen)は、制作活動を考えるとわかりやすい。すぐに消費し尽くされるわけではないモノづくりで、制作物として残る。「役立ち」「有用性」あるモノをつくることが、これにあたる。「活動」より劣るが、「労働」よりはマシである。
「労働」(labor、Arbeiten)は、人間が(動物的な)生命・生活を維持するために必要なものに関わる活動だ。「労働」で作られるもの(たとえば食物)は耐久性がなく、労働の成果はすぐに消えてしまう。それゆえ、価値が一番低い。
アレントさんは、一番目の「活動」に、人間らしい最高の価値を与える。これに従事する人こそ、自然に支配されない、「地球全体の支配者、主人」としてふさわしい。
逆に、「労働」に従事する人間は、身体を維持するために必要なものをつくるだけであり、「自然と地球の召使いにすぎない」ことになる。いわば、奴隷だ。
すると、トイレ清掃は、人間の排泄処理に関わる業務であり、生産的ではなく、役立つモノも生みださない、最も下層の「労働」ということになる。要するに、エセンシャルな労働はみな、そこに組み入れられるだろう。
とんでもないことだ(こうした西欧的知の問題点については、拙著『「労働」止揚論』に詳しく書いた)。
◎西欧近代的知にいまだに縛られる列島の知識人

アレントさんの見解は、なにも彼女だけに特有な考え方ではない。プラトンやアリストテレスの古代ギリシャ哲学に発し、ユダヤ・キリスト教との融合にルーツをもつ西欧近代的労働観、存在観をみごとに承け継いだものであるからだ。
現代日本でも、こういう西欧近代的知を承け継ぐ思潮はいまだに絶えない。
たとえば柄谷行人さんが、交換様式Dと称している内実は、自然性・身体性(必要性・有用性)に左右されない「純粋贈与」や、「全き自由」(自己以外に一切左右されない自由な意志=カント)の希求であり、西欧近代的知の延長上に位置づけられる。
こうした知からみれば、「平山」さんのトイレ掃除労働は、「純粋贈与」から外れ、「自由」からも大きく外れた、動物的奴隷的労働にすぎない。なぜなら、それは賃金(貨幣)という見返りを求める「賃労働」であり、かつ人間の自然性(動物性)の最たる排泄に関わる「労働」であり、自然性にまったく縛られない「純粋な贈与」希求からはもっとも遠い行為にあたるからだ。とても「地球の主人公」たる「自由人」の行うことではない、ということになる。
「パーフェクトデイズ」のドイツ人の監督ヴェンダースさんは、こういう西欧近代的知の視線に縛られていないようだ。
銀座線浅草駅地下の呑み屋、富士山の描かれた銭湯、二階建ての木造アパート、……、他方には、東京スカイツリー、そして先端テクノロジーを駆使した渋谷トイレ……、それらはヴェンダーズさんの興味を惹いたろうが、これまでの西欧人的興味(オリエンタリズム)とは異なる。日本人が企画・脚本にも参画し、役所さんもプロデュースに参加しているし、西欧近代的知にとらわれない眼を、そもそも監督はもっているのだろう。
◎「平山」さんの「パーフェクトデイズ」の行方
一見単調に見える「平山」さんの生活には、さまざまな味わいがあり、変化がある。
いつもは穏やかだが、ときには怒ることもある。仕事に欠員が生じ、過重労働を押しつけられれば、管理職に抗議もする。

それでも、賃労働をしているときも、休息のときも、賃労働を終えたあとの時間も、ときどき笑みを浮かべる。空を見上げ、木漏れ日を見上げ、街の人、食堂やスナックの人に、笑みを浮かべる。
それは世界の「肯定」であり、「生きている(生きてある)こと」を「有り難い」と受けとめ、「ありがたい」と感謝する心情のゆえである。「暇」や「退屈」に苛まれる時間などありえない。
しかし、この「パーフェクトデイズ」も、危うさを抱えている。「平山」さんの体に不具合が生じるかもしれない。木造アパートの解体立ち退きを迫られるかもしれない。スナック、地下食堂、それにフィルム現像を頼む写真屋も、まもなく店じまいするかもしれない。いや、スナックは店じまいする。
「パーフェクト」が成立するのは危うい。つねに崩壊と紙一重だろう。でも、列島の存在観がOSとして駆動される限り、また立て直される。あるいは、立て直しが求められるのだろう。