村上春樹 『街とその不確かな壁』 [書評]

70代半ばを迎えると、心も体も一層強張りがちになる。かつて組織・共同体に属していた人は、とうの昔に離れた地位や力の幻影を捨てられず、振る舞いに現れることが多々ある。
“ただの人”として老年を淡々と生きることはなかなか容易ではない。
このあたり、村上春樹さんは1度も組織に属さず、単独の表現者として生き、“文壇”なるものとも距離をとってきたのだから、みごとな生き方を貫いていると言えるだろう。
私自身、体力、知力の衰えを感じる中で、彼の構想力、表現力には、同世代人として感心する。
だが、新刊『街とその不確かな壁』を読み終えて、大きな感動に包まれることはなかった。同じ全共闘世代の社会学者橋爪大三郎さんが、「この作品を同時代で読めるとは何と幸いだろう」と書評を結んでいる(毎日新聞)が、そんな心境には至らなかった。
なぜなのだろう。読後に“ものたりなさ”を感じた要因は、おもに2点に絞られる。「愛のかたち」と、「街」を生成してしまう切実さの度合である。

(1)「愛のかたち」 ~「純愛の特権性」~
『街とその不確かな壁』の主要な人物をみると、「ぼく」(私)、子易さんは、いずれも、絶対的な愛の喪失を体験する。また、「きみ」(君)、コーヒーショップの女性店主、イエロー・サブマリの少年は、心身の欠損、不全を抱えている。
絶対愛の喪失や、心身の欠損が、物語の柱を構成するのは、本作に限らず、村上さんの主要作にしばしばみられる。ひとはみな、大なり小なり、欠損や病いを抱えこんでいるゆえ、村上さんが描く世界に傾倒しやすい。彼の構想力、描写力がそれを促す。
今回も、「混じりけのない純粋な愛」(子易さんの言)と、その喪失が物語の核をなしている。
“ものたりなさ”を私が感じる第一の理由は、そんな「愛のかたち」への異和にある。もう少し突っこんで言えば、「純愛の特権性」へのもたれかかりである。

愛は三つに分けることができる、と思う。恋愛、性愛、情愛である。むろんそれら三者は深くからみあい、浸透しあい、截然とは分けがたい。ときには対立することもある。いずれにせよ、志向性として三つに分けられる。
村上さんの主な作品では、恋愛と性愛はたっぷり描かれ、つねに物語の起点、転換点、そして回復すべき目標とされる。
ところが、三つ目のかたちである情愛が滲み出てくるような世界の表現には、私の記憶する限り、接したことがない。
恋愛と性愛は近似している。個と個が向きあい、一体化をめざし、溶けあう。そういう志向性をもつ。だが、情愛はそうではない。
違いを喩えてみよう。
テーブルに座るとき、二人はそれを挟んで向きあう。互いに相手を見つめ、深く知りあいたいと願い、溶解を目指す。
対して、情愛は二人が向きあうのではない。テーブルを前にして横に並んで座り、二人は同じ景色を眺める。(共同であれ、ばらばらであれ)課題に対して取り組む過程(生活)を通じて、対的世界の深まり(情)を得る。あるいは解体に瀕する。
情愛とは、「いつくしむ」という表現に近いのだろう。「なじむ」、「にじむ」等の言葉もふさわしい。時間による「風化」を逆に味方につけて折りあいを図る世界でもある。
作家村上さんは歳を経ても、そんな情愛の世界へは焦点を絞りこまない。
★ ★ ★
「混じりけのない純粋な愛」について、子易さんは語っている。
いったん混じりけのない純粋な愛を味わったものは、言うなれば、心の一部が熱く照射されてしまうのです。ある意味焼き切れてしまうのです。とりわけその愛が何らかの理由によって、途中できっぱり断ち切られてしまったような場合には。そのような愛は当人にとって無上の至福であると同時に、ある意味厄介な呪いでもあります。
(『街とその不確かな壁』)
そう、「純粋な愛」は両義的だ。
それは風化を拒否する。絶対、密閉、圧倒といった特権性で貫かれている。ゆえに描きやすいし、読まれやすい。
しかし、絶対世界の喪失に直面し、嘆き・悲しみが外部に向かって全面的に発露されると、まわりの人は退いてしまう。村上ワールドで、特権性を発露させる発端となったのは『ノルウェイの森』であり、ゆえに絶大な人気を博したのだろうが、逆に私は退き気味になってしまった。
こうした「愛のかたち」は今回の作にも及んでいる。読者はしばしば既視感を覚えるし、作品世界は停滞しやすい。
たとえば今回の小説では、次のようなフレーズが出てくる。
「わたしはあなたのものです」――わたしはあなたの所有物である、と。16歳の少女である「きみ」がこんな言葉を17歳の「ぼく」への手紙で記している。「もしあなたがそれを望むなら、わたしのすべてをあなたにあげたいと思う」と。愛への渇望と、心身の不全によって相手を満足させることができない申し訳なさとが、そう言わしめている、ということなのだろう。
しかし、ティーンエイジャーの言としてありうるのだろうか。いや、現実にそう発言する少女はいるのかもしれない。しかし私はここに、著者の、対世界への偏りの表出を見てしまう。そして、いささか食傷気味にならざるをえない。
むろん、じわりと育まれるはずの情愛の世界も、薔薇色だけで描けるわけではない。地獄と紙一重である。往々にして、相手(主に女性)に抑圧だけをもたらす関係に結果することもある。こうした散文的世界が、「純粋な愛」と背中合わせに貼りついている現実に描写の領域を広げることも、文学的成熟につながるはずだ。
作者は、「純愛の特権性」にもたれかかりすぎていないだろうか。

(2) 壁に囲まれた「街」の切実さについて
“ものたりなさ”を感じる第二は、物語の要となる、壁に囲まれた「街」という存在に、切実さを感じにくいことだ。
壁に囲まれた「街」は、10代の「きみ」と「ぼく」が生みだしてしまった世界として設定されているが、「街」の性格がぼんやりしたままで、二人が「街」を生みだしてしまう背景が見えてこない。読者からすれば、「街」の存在を切実には受けとめられない。
それとは対照的なのが、今作と同じルーツ(中編小説「街と、その不確かな壁」)をもつ、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』における「街」だ。同作に登場する壁に囲まれた「街」は、読者にとってとても切実な世界として受けとめられた。
『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』は1985年に発表された。壁に囲まれた「街」は、主人公(の意識の核)が図らずも生みだしてしまったものである。ひとことでいえば、「世界の終り」の街だった。そこは、拡大する「自我やエゴ」のない閉塞的なエリアであるけれども、関係の煩わしさや労働の苦しみから開放される街でもある。
そういう両義性をもつ「街」が読者を惹きつけたのは、当時の時代背景と密接に関係している。
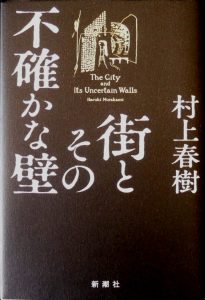
『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』の「街」は、明らかに時代が生みだしたものだった。
「1968年」を中心とする、若者たちの反乱のムーヴメントが、1960年代後半から、70年代初頭にかけて吹き荒れた。そこでは観念(思想やイデオロギー)が熱狂し、呼応するように身体の直接性が重視された。しかし、嵐のような波が引いてしまうと、村上さんも含めて、渦中にあった若者たちは市民社会のなかにバラバラに散っていく。1970年代とは、生活を織りなすなかで、ひとりひとりが反乱の季節の厳しい総括を迫られ、また残務の整理に追われる時代だった(実際にどれだけの人が「総括」に値する作業をなしえたかどうかは別だが、それを掬いあげることが表現者の役割だろう)。
『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』は、そんな歴史的背景を明確にもつ、村上さんなりの総括作業の産物であり、傑作だった。
大義を掲げて社会変革を図ろうとする「完全なヴィジョン」の断念の末に、「限定されたヴィジョン」のもと、争いのない静かな生活を単独者として引き受けるスタイルを選んだ。いや、そう強いられた。
同作の「ハードボイルド・ワンダーランド」のラスト――晴海埠頭に停めた白いカリーナの中での「私」の述懐は、1980年代の表現のなかでも、際だって倫理的なフレーズだったと断言できよう。
1985年に意識の核が生みだしてしまった「街」と、今作の、壁に囲まれた「街」は、細部では違いがあっても、自我や感情が失われた静かな街としてルーツは同じである。
けれども、今回の『街とその不確かな壁』で、無垢なティーンエイジャーがつくりだした「街」には、図らずも生みだしてしまう必然性が感じられない。「きみ」という「影」は、3歳のときに「本体」から引き離されてしまったが、それが「街」を生みだす根拠とはつながりにくい。ようするに、「街」が生みだされる切実さを感じにくい。
だから、壁に囲まれた「街」にとどまるにしても、出て行くにしても、その選択に重みはあまり感じられない。

じつは、「街」は問題を抱えている。単角獣(旧作では「一角獣」)の存在である。これは、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』でも同じである。
「街」のシステムは、短角獣の犠牲の上に成りたっている。それは「街」の矛盾、問題点として今作でも指摘されている。けれども、何かの犠牲の上に成りたつ社会構造は、壁のあちら側にだけ特殊なことではない。こちら側の世界にだって厳然と存在している。
しかし『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』では、自我・エゴが消されたけれど逆説的に成りたつ半ユートピアとして「街」が設定されていたので、一角獣の存在は問題点としてはっきり浮上した。けれども、今作の「街」は、ユートピア性の欠片も感じられず、むしろ目に見えない絶対権力に支配された社会だけのように存在しているがゆえに、単角獣の犠牲という問題も、倫理の問題として浮上しにくい。
読者は、静謐ではあるけれど異物を排除して成りたつだけの「街」の生成に、切実さを感じることができないし、壁の内側に残るか否かといった二者択一の判断に重さを感じない。決断に倫理性を見いだしにくいので、恣意的な選択として映る。
もちろん倫理的問いとして軽く感じられるのが、一概に悪いことではない。ティーンエイジャーにとっては絶対的なことではある。けれども、「ぼく」はすでに中年の「私」に成長している。
村上さんとしては、こちら側とあちら側を隔てる壁は、努めれば動きうる可変的なものであり、努めれば行き来できるし、そもそも不確かなものなのだ、とメッセージを送りたかったのだろう。
自己がつくりだす壁、また社会がつくりだす壁を相対化する――そうした姿勢をもちつづけることや、そもそも個の本体と影の関係だって、入れ替わりうる可変的なものである、と。そう訴えたかったのだろう。
その呼びかけには共感できても、壁で隔てられる肝心の「街」が新作では切実さを欠いていることは否めない。
★ ★ ★
氏の作品について私は、初期三部作から『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』まで強く支持してきたが、『ノルウェイの森』でかなり退いてしまい、以降はいくぶん醒めた目をもって接してきた。それでも、短編には共感するものが多いし、新作が出れば必ず目を通してきた。
きっと彼の次作も、発表されればすぐに手にするだろう。同時代を走ってきたランナーの姿に無関心ではいられない。それはずうっと「1968年」の総括作業の意味を内包していると思うからだ。
願いうるならば、これまでの「絶対の純愛・性愛」(愛の特権性)とは異なる「愛のかたち」を描いてほしい。困難ではあるが、そのほうが今日の情況とより深く向きあえると思う。そこに成熟の深まりを見出せるのではないか。

(付け足し) 「じゃあ、お前はどうなんだ!」
「じゃあ、お前はどうなんだ!」――これは「1968年」という時代が噴出させた問いかけのスタイルだ。
あたかも傍観者的に感想や批評を述べる相手に対して、「じゃあ、お前自身はこの問題をどうとらえ、どう克服しようとしているのだっ」と。当時は、人差し指を相手の目の前に突き出し、上下に強く揺らしながら、問い糺した。いわば、「指弾」である。
これは乱暴に過ぎるスタイルであったけれど、「そう言うあなた自身は、どうなのよ?」という問いかけ自体は、けっして否定されるべきではない。
当時、美しく立派な「良心」を口先で披瀝しながら、自らの生き方や足元の実態を棚上げして問わず、現実の社会構成関係においては、政治家はもとより、不正を隠蔽し、抑圧者として弾圧に加担する学者・知識人たちに対して、若者たちは現実の生き方を問うた。そういう問いかけは、全共闘運動におけるスタイルの特徴でもあった。「当事者」性である。
なにも学園だけではない、職場でも、家庭や男女関係でも、そう問い、問われた。
ちなみに、かつて吉本隆明さんはこうした問題を、“良心・観念の相対性”に対する「関係の絶対性」として問うた。
話が飛んでしまったが、『街とその不確かな壁』への批評に対して、「じゃあ、お前はどうなんだ!」と投げかけられる問いには、こう答えよう。
ジャンルは異なるけれども、こちらは自分なりに、「1968年」に浮上した「近代の問題」をどうとらえ、乗り超えるか――もう時間はあまり残されていなけれど、考え続けている、と。
拙著『村上春樹と小阪修平の1968年』
拙著『村上春樹の歌』
編著『探訪 村上春樹の世界』


