柄谷行人 『力と交換様式』 [書評]
【雑記帳】
労作だが、近代的知の限界が露わになったと受けとめざるをえない。
「交換様式D」の内実、交換における「力」の正体、「戦争と恐慌」による「到来」――これら、本書の核をなす3点について批評してみる。
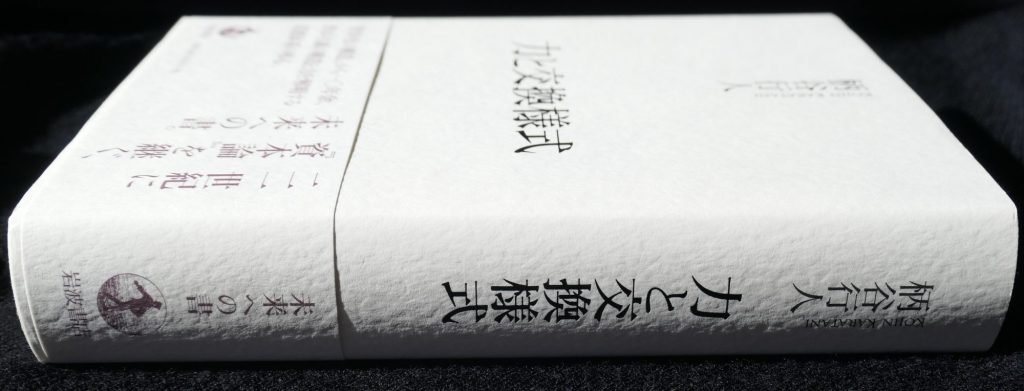
大著であり、労作である。社会(構成体)の歴史を、マルクス主義・唯物史観が従来用いる「生産様式」からではなく、「交換様式」から描く。西欧の主な思想家たちの言説を配置して、巧みに論を展開している。
柄谷さんは昨年、〝哲学のノーベル賞〟を目指す「バーグルエン哲学・文化賞」に選ばれているが、そんな氏の近年の論考を補強し、総まとめとする著作と位置づけられるのだろう。
とともに本書は、著者が依拠してきた西欧近代的知の限界を改めて示している。こう表現して傲慢に響くなら、「私たち近代人の限界」と言い換えてもよい。「限界」を噛みしめることも大切と考え、書評してみる。
主に三つの問題点を論じる。第一に、「交換様式D」の内実について。第二に、交換によって生じる「力」の正体について。第三に、「戦争と恐慌」による好機の「到来」について。いずれも、本書の核をなす点である。

第一 「交換様式D」の内実について
◯交換様式から世界史をみる
まず、第一(「交換様式D」の内実)から。
柄谷さんは、世界史を基礎づけるのは、従来マルクス主義、唯物史観が用いてきた「経済的下部構造」における生産様式ではなく、交換様式であり、それこそ重要ととらえ、時代に沿って以下の四つを挙げる。

A 互酬(贈与と返礼)
B 服従と保護(略取と再分配)
C 商品交換(貨幣と商品)
D Aの高次元での回復
人と人(あるいは共同体と共同体)の間での「交換」では必ず、ある「力」が働いている、という。この「力」とは、「物に付着する霊」、「フェティシュ」(物神)などと呼ばれる「観念的な力」である。書名における「力」とはそれを指している。
じつは、A、B、Cの各社会で人々を自発的に従うようにさせているのは、こうした「力」である、と著者は指摘する。
◯ 核心となる「交換様式D」、あるいは「コミュニズム」について
柄谷さんは世界史を、交換様式AからBを経て、今日はC(商品交換)が中心の段階へ至ったとし、いまだ実現していないDを、目指すべき交換様式として措定する。
交換様式Dとは、「互酬(贈与と返礼)」である交換様式Aの「高次元での回復」とされる。この追求こそ、本書が主に訴えたいことである。
Aの「高次元での回復」とは、著者自ら明言しているように、コミュニズム(の運動)である。
コミュニズム(共産主義)とは、ずいぶんと手垢にまみれながらも曖昧な言葉で、著者が本書ではっきり定義しているわけではないが、先入見を排し、本書全体からその内実を拾いあげてみる。
国家の揚棄(止揚)であり、資本の揚棄であり、階級の揚棄である。人々の平等性、独立性の実現であり、自由の確保である。また「私的所有」の廃棄(「個人的所有」の実現)でもある。それらは、国家・資本の揚棄なくして手にしえない。
◯ 「交換様式A」、「贈与」の評価

では、なぜ互酬性Aの「回復」であり、かつそれが「高次元」でなければならないのか。
交換様式Aとは「贈与と返礼」である。かつてマルセル・モースが『贈与論』で明らかにしたアルカイックな社会での交換のあり方を指す。
モースが古代社会に見出したのは、二者(共同体)の間で、あたかも一方がただ与えるだけにみえる「贈与」には、実際は返礼(お返し)が必ず伴うという構造だった。贈与とは、じつは返礼を強制するものである(贈与の互酬性)、と。
すると柄谷さんが、アルカイックな社会に見出せる交換様式A(贈与と返礼)の「高次元での回復」がいったい何を意味するのかが、自ずとみえてくる。
そう、強制を伴わない贈与である。それが、互酬性より「高次」とされる。
彼が他の著書で使う言葉を引っ張ってくるほうがわかりやすい。「純粋贈与」である。返礼とかお返しを強制しない、純粋な贈与である(『哲学の起源』)。そこでは、「各人は自由であるとともに平等であった」(同前)。
Aの高次的回復としてのDを追求する論の根拠を、柄谷さんは、かつてあったであろう歴史的段階に求めている。人類が定住する以前の「太古の遊動的段階」である。そこに生きる原遊動民は、「個体性・独立性」を保持していた。言い換えれば、「自由」であった、ということになる。
ところが、定住するようになり、氏族社会を迎えると、「個体性・独立性」を失ってしまい、交換様式Aが出現した。返礼の強制を伴う贈与交換(互酬性)である。
ただ、氏族社会では、遊動的段階にあった「原遊動性(U)」は辛うじてまだ保持されてきた。しかし、のちに国家が出現すると、交換様式Aは交換様式B、つまり、「服従と保護(略取と再分配)」に押さえこまれてしまった、ということになる。
話を戻せば、人類が定住する以前、遊動的段階には、「原遊動性」(自由)、「純粋贈与」を見出すことができるが、こうした純粋贈与への回帰こそ、柄谷さんにいわせれば、「交換様式Aの〝高次元での回復〟」ということになる。
なぜ、Aの互酬性より「高次」なのか。見返りを求めない(強制しない)贈与、つまり純粋贈与だからだ。それは絶対の自由の確保でもある。
◯ユートピア主義
このような思考は、私からみれば、西欧近代的知の構造に属する。
交換様式Dへの希求は、人類史でしばしば湧きあがってきたとして、柄谷さんはさまざまな例を挙げている。
たとえば、アウグスティヌスの論考に沿って書いている。
人類はエデンの園にいたとき、いわば原遊動的な状態にあった。しかし、それは定住化とともに失われ、A・B・Cが支配する社会が形成された。ゆえに、エデンの園に戻ることが目指される。それがDであるといってもよい。
(『力と交換様式』)

(『世界の名著 アウグスティヌス』口絵から)
原初への回帰の思考は、アウグスティヌスにとどまらない。千年王国運動にも見出せる。千年王国運動を、「原遊動性の回帰、あるいは交換様式Aの、〝高次元での回帰〟」とみなす。
さらに、トマス・モアの『ユートピア』に触れて、次のように書いている。「地の国」を動かしている力は、貨幣の力、あるいは自己増殖する貨幣としての資本の力である。それに対して、ユートピアでは、「貨幣に対する欲望が貨幣の使用とともに徹底的に追放されている」。つまり、「神の国」では、「資本主義が揚棄されている」と。
原初を措定した上での、D(ユートピア実現)の希求は、まさにキリスト教における歴史(はじめと終わりのある世界)と重なる。論は、ユートピア論的思考の構造下にある。ただ、ユートピアは、あの世ではなく、この世において生じる、と柄谷さんはいう。
始原が括りだされ、それへの回帰が求められる。「原遊動性の回帰」とは、かつてあったとされるユートピアへの回帰だ。それは、キリスト教のエデンの園、ルソーが措定した自然状態、エンゲルスらの唯物史観における原始共産制などと二重写しにみえる。かつてあったであろう理想郷(原初)への「回帰」は、まさに西欧近代的な歴史観の基礎をなすものである。
※翻ってみると、こうした論は、著者自身が批判する「初期マルクスの疎外論」を構造的には踏襲しているようにみえる。つまり、「あるべき」「本来の」あり方から疎外されてしまった状態から、元の本来の状態への回復(疎外からの回復)の志向である。
だが、そもそも、若きマルクスと、のちのマルクスの間に「認識論的切断」を見出したアルチュセールによる、初期マルクスの疎外論批判自体、私からみれば、ヘーゲル、マルクスにおける「疎外」の誤読に基づくものであり、柄谷さんもそのアルチュセールの後に続いているようにみえる。
拙著『「労働」止揚論』における「『認識論的切断』で捨てられたこと ~アルチュセール~」参照。
◯「交換様式D」、「純粋贈与」にみる近代的知の限界
交換様式Dにおける「自由」とは、いかにも西欧近代的な知の産物にみえる。
個人が自己以外のいかなる制約も受けない「自由」が夢想されている。底に流れているのは、精神より価値の低い自然や物質の規定を振り払う、純粋な「自由」の希求である。これは、古代ギリシャ哲学(ヘレニズム、たとえばプラトン)とユダヤ・キリスト教(ヘブライズム)とが融合して組み立てられた西欧的世界の近代的世界観に基づくものである。そこで求められるのは、自然や動物性の制約を受けない精神、理性の確立である。しかし、それ自体、逆立ちであり、自然に規定されない存在などありえない。

※こうしたことについては、拙著『労働「止揚」論』や『「ありがとう」の構造』に詳しく書いた。
「贈与」の捉え方も、同様である。
返礼を強いる贈与ではなく、返礼を求めない(強制されない)純粋な贈与を氏は希求する。しかし、こうした「純粋贈与」(交換様式D)は幻想といわざるをえない。
なぜなら、柄谷さんが「自由」の主体とする個人とは、そもそも自己以外のもの(自然、他者、社会)から贈与されたものにすぎないからだ。表現を変えれば、生誕から死に至るまで、自己以外の自然(大地)、他者、社会に絶対的な「規定」を受けている。他からの規定を受けない、純粋な「主体」など存在しえない。純粋な「自由」がありえないように。仮に当人が「純粋贈与」を他者に行ったと思いこんでも、それは「返礼」でしかありえない。返礼を求めるか、求めないか云々の以前に、主体自体が贈与されている。
すでに、生まれ、「いま・ここに存在する」(生きてある)ということにおいて、主体の贈与の純粋性という概念は成り立たない。
もし、モースがとらえたような贈与(互酬性)の揚棄(高次元での回復)にこだわるとすれば、贈与された存在でしかない個(主体)は、たえずその「返礼」を続けるほかない。おそらく謙虚なクリスチャンなら、そのように宗教意識を掘り下げているにちがいない。
しかし、柄谷さんは存在論的基底まで降りてはいない。「返礼」を求めるか(互酬性)、求めないか(純粋贈与)、あるいは後者こそ「高次」といった論自体、近代的主体の地平に拘泥しすぎていないだろうか。
以上みてきたように、交換様式Dとは、近代的な主体が自己の純化を図る先に幻想されるものにみえる。

第二 交換によって生じる「力」の正体について
◯「霊的な力」「物神」について
次に、問題の第二。本書のタイトルにも置かれた「力」という概念について。
柄谷さんによれば、交換において、「霊的な力」が生じる。「霊的」とは「観念的」とも言い換えられる。それは強制的な力である。著者は、これを「物神」(フェティシュ)と呼んでいる(もちろん、マルクスに由来する)。
交換様式A(互酬性)では、物に「霊が付着」している。その霊が、「贈与を受け取れ」「贈与にお返しせよ」と強制している。
交換様式Bで発生し、Cにおいて大きな役割を果たすネーションも、一種の「霊」ととらえる。
交換様式Cでは、貨幣に「霊」が付着している(フェティシュ)。そして、資本にも「霊」が付着している。「信用」も交換であり、そこにも強制的な力(霊の力)が働く。
このように、著者はどんな交換においても、介在する「力」を見出し、それを「霊」、「物神」、「観念的な力」と名づけている。それらは「固有の生命」をもち、人間を強いる「力」として存在する、と。
だが、こうした捉え方に、落とし穴が潜んではいないだろうか。
◯「アニミズム」と定義する思考
この問題は、本書でも触れられるアニミズムの概念ともつながっている。
柄谷さんは、イギリスの人類学者エドワード・バーネット・タイラーに依拠してアニミズムの概念を用いる。遊動的な段階では、人々は素朴なアニミズムをもっていた、と。
だが、「アニミズム」という概念規定自体が、西欧近代的知の産物である。

タイラーは、一九世紀後半に著した『原始文化』で、宗教の起源をアニミズムに求めた。アニマとは、ラテン語で、霊魂、こころのこと。アニミズムは、すべての存在物に霊魂が宿っているとする霊魂主義である。
タイラーによれば、すべては霊的存在であると信仰するアニミズムが宗教の基礎になっている。その上に進化・発展したのが「多神教」(複数の神々)。そしてもっとも上位にあるのが「一神教」。クリスチャンである彼が、一神教(キリスト教)を信仰の最高形態としたのは当然で、キリスト教こそもっとも進んだ宗教のかたちとされる。
一神教にあっては、万物に霊魂が宿っているとみる宗教を邪教として低位に置き、霊をどんどん上昇させ、天上に君臨する神(霊魂)だけを崇拝し、地上の事物は一切崇拝してはならない(偶像崇拝禁止)とした。だが、こうした序列化自体、疑問だ。これは万物に見出される「霊的な力」を次第に絞りこみ、すべての力を唯一者(絶対者)のもとに集約し、力を正当化することにつながる(遠藤周作『深い河』は、そのように流れてしまう信仰のありように疑いを呈するものでもあった)。
もっと重要なことは、そもそも「霊」を括りだすこと、さらに霊がどこに付着しているか、アニミズムか否か、などと論じること自体が、近代というひとつの枠組内の思考である。柄谷さんが「霊的な力」「霊魂」を実体化して世界史を論じるのもまた、同じ構造のもとにある。
しかし、これは根本的な見誤りだと思う。人間は自然と大昔からつねに心的価値を交換してきたし、今もしている。人間が人間と、あるいは人間が自然とたえず行う心的価値の交換から、「霊」を括りだして、「霊が付着する」とか「霊が強制する」と実体的にとらえるのは、物神化を徒らに強めるだけだ。このような物神化の過程にあえて加担する必要はない。
◯「霊的な力」はどこからやってくるのか?
たしかに私たちは、資本の自己増殖運動の僕(しもべ)の役割を演じさせられている。これは転倒である。しかし、それが「霊的な力」によって強いられているとみなしても、貨幣・資本の物神化を強化するだけだ。
では、この「力」とは、いったいどこからやってくるとみるべきか。
原点を探ると、人が(さらには共同的観念が)抱かざるをえない「負い」に辿り着く。
人間は自然(的存在)である。根底で、自然の規定を受けている。言い換えれば、自然に「負っている」。負っているから、自然に「感謝」し、あるいは逆に自然を「恐れ」る。自然とは人間にとって両義的である。
このようにして、感謝であれ、恐れであれ、人間は自然との間でつねに心的価値を交換してきたし、今もしている。
そうした心的価値交換の中で、自然への「負い」を「霊」とか「神」などと括りだすように衝き動かされる。自らが自然であるゆえ、人は飢餓や死への不安とつねに向きあわざるをえない。そうした不安こそ、物語を形成させ、「霊」を括りださせ、実体化させる。観念過程だけではない。経済過程では、貪欲な、飽くなき富の増大を促す。
日本列島に例をとれば、こうした心的価値交換を通じて、古代から人は自然に「負い」を抱いてきた。隠れて見えない「力」を古代人は「カミ」と名づけた。カミとは、隠れていて、人間が把握できない場所や力を指しているだけだった。
それがのちに漢字の「神」が当てられ、人格化を通じて神格化(物神化)され、近代の一時期には神格の絶対化に転倒することすらあった。
ただ、全体に列島では西欧近代とは異なり、人間と自然との間に断線が引かれていない(それは近代的知からみれば、〝遅れ〟とみなされるのだが)。それゆえ、「自由」や「純粋贈与」への絶対的傾斜を比較的に免れてきた。
◯ケインズとマルクスの「曉の理論」予想はなぜ外れたのか?
西欧にあっても、構造的には自然への「負い」の心情が基底に流れている。そこから、両義的な力としての「神」が括りだされ、エデンの園とそこからの追放(原罪)が措定された。共同体間の摩擦や戦いが苛烈を極めたから、神の力が強化されたのも、たしかに避けがたいことだったろう(もちろん「神」の概念自体、列島と西欧では異質だが)。
このように自然に「負って」いる(自然に規定されている)という根底での受けとめが、宗教を生み、社会的・経済的活動を規定している。程度の差はあれ、蓄蔵や資本の拡大へと人間を駆りたてるのも、人間が自然的存在でしかないという根底での受けとめ(強迫)に帰因する。それが個人の活動のみならず、共同的な活動にも影響を及ぼしている。
柄谷さんが「霊的な力」「物神」などと呼ぶ「力」は、人間の自然への「負い」から衝き動かされ括りだした観念を実体化し、そう名づけているのにすぎない。
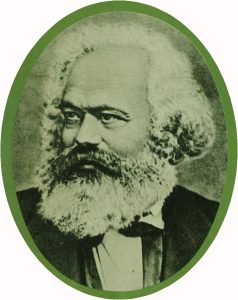
視点を変えてみよう。百年少々前、経済学者ケインズは、人類の「経済問題」はあと百年以内に解決すると予測した(「孫たちの経済的可能性」)。急激な技術革新によって「生存のための闘争」が終わり、「貪欲と高利貸し」の時代が終わる、と。
また、百五十年ほど前、マルクスもまた、生産力が発展し、生存に必要なものが生産できるようになったとき、自然からの束縛が終わり、人間は「自由」を謳歌できるだろうと予言した(『資本論』)。
二人は生産力が発達した曉には、「貪欲と高利貸し」が支配する世界が終わり、自由の王国が出現する、と希望を抱いて遠望した。近代人はみな、この「……が実現した曉には」という「曉の理論」を信じたし、それはもっともだったと思える。
その後、彼らの予想通り、生産力は飛躍的に発展した。しかし、偉大な二人の経済学的慧眼にもかかわらず、「経済問題」は相変わらず解決していない。
なぜ「経済問題」の解決に至らないのか。
柄谷さんの論では、そこに「霊的な力」「物神」の力を見出すだけで、それ以上の追究には向かわない。
その問いへの答えは、人間が自然に「負っている」、言い換えれば人間が根底的に自然に規定されているという存在論的構造にまで掘り下げてみるしかない。人間は自然的存在として決定的な刻印を受けているゆえ、飢餓や死への不安を抱えざるをえない。たえず生活への不安が湧きあがる。どんなに経済的に豊かになろう(蓄蔵しよう)が、絶対の安心が保証されることはない。
ゆえに、ケインズやマルクスだけでなく、私たちが信じてきた、「経済が成長した曉には……」という「曉の理論」は幻とならざるをえない。
「曉」は、ずっとやってこない。蓄財家をみればよい。蓄蔵すればするほど、吝嗇や投資に走る。生存を脅かす恐怖を振り払い、逆にこれを制圧し、安心と優越を得たいからだ。他との競争がそれを加速させる。「承認欲求」などさまざまな観念的バリエーションが上層にあるにしても、根底に流れているのは、自然的存在である(でしかない)という規定からの脱出志向だ。とりわけ、西欧近代的思考では、自然の束縛からの脱出(精神・理性の確立)が強く求められてきた。
柄谷さんが名指した「力」とは、人間の存在論的ありように降りて、見直さねばならない。

第三 「戦争と恐慌」による「到来」について
◯「到来」待望と「いま・ここ」の「関係の組み替え」について
最後に、第三の問題。交換様式Dの「到来」について。
著者は、D(ユートピア)は、「あちら側からやって来る」のであり、それを人間から意志して実現することはできない、とする。むしろ逆に、BやCの揚棄を目指すこと自体が、BやCを回復させてしまう、と。
Dは人間の願望や意志によってもたらされるのではく、それらを超えた何かとして到来する。
『力と交換様式』
さらに柄谷さんは、本書の最後を、次のフレーズで飾っている。
そこで私は、最後に、一言いっておきたい。今後に、戦争と恐慌、つまり、BとCが必然的にもたらす危機が幾度も生じるだろう。しかし、それゆえにこそ、〝Aの高次元での回復〟としてのDが必ず到来する、と。
同前
D(ユートピア)の到来は、人間の願望や意志では招き寄せることができない。「戦争や恐慌」こそ好機であり、それを待望することになる。著者としては、希望を指し示したいのだろう。だが、「戦争と恐慌」待望論は従来のマルクス主義と変わらない。
ちなみに佐藤優氏が、「向こうからやって来る」という発想を「柄谷神学」として歓迎し、「『希望の原理』に評者は強い共感を覚える」と評価している(『文藝春秋』2023年2月号)のは、二人が思考的枠組を共有しているからだろう。
著者のこうした考えに触れるとき、私はかつてプルードンがマルクスに送った手紙の一節を思い起こす。マルクスは当時のヨーロッパにおける社会主義運動に関するネットワークづくりで、フランスのメンバーを、プルードンに依頼した。それへのプルードンの返事を要約してみると、次のようになる。
「あなたは、いかなる改革も、『実力行使』、『革命』なしには不可能だと今も考えているようですが、わたしはそういう見解を完全に放棄しました。それらはせいぜい「動乱」でしかなく、目的の成功に必要なものではありません。つまり、『革命的行動』を社会改革の手段とみなしてはならないのです」(プルードン「マルクスへの手紙」の要約、1846年)
プルードンは、マルクス主義や柄谷さんが予想する、「戦争や恐慌」の到来時の「革命的行動」への幻想を、すでに捨てていた。少なくともこの点では、プルードンの考えのほうが正しい。なぜなら、「革命的行動」が、その「善意」(たとえば交換様式Dの志向)とは裏腹に、とんでもない観念的転倒をもたらすことは、歴史が繰り返し何度も証明しているからだ。
「高次元」の「純粋贈与」や完全な「自由」の追求とは、媒介(規定)を欠いているがゆえに、恐怖政治をもたらす。「地獄への道は〝善意〟で敷きつめられている」――皮肉にも、マルクス自身がこのように記していたではないか(『資本論』)。

※ささやかな個人史を振り返れば、たしかに「闘い」は「向こう側からやって来」た、と感じられる。
二度ほどあった。二度目を余震とみることもできるし、一度目を予震とみることもできる。
どちらにしても、たしかに起ちあがった(せざるをえなかった)。ただし、そこで「解放区」を純粋な空間(交換様式D)として括りだしてしまえば、そこに観念の転倒が起こる。このことをつねに深く考察していたのが、哲学者小阪修平さんだった(『三島由紀夫VS東大全共闘 1969-2000』藤原書店刊、拙著『村上春樹と小阪修平の1968年』新泉社刊を参照)。
また、到来して起ちあがることと、日々の営み(日常、自然過程)が直結しているわけでもない。柄谷さんがこのことを押さえているようにはどうしてもみえない。
職業革命家や一部学者知識人ではない、ふつうの生活者なら、たとえそれが不可避だとしても、「戦争や恐慌」の待望論(決起論)には背を向ける。

たしかに私たちは、資本の自己増殖運動の駒のように存在させられている。それはまさに転倒である。だが、これに反発して、「戦争と恐慌」の危機から生じる「Dの到来」を待ち望むのは、さらなる転倒重ねといわざるをえない。なぜなら、Dとされる「純粋贈与」も「絶対の自由」も近代的知が括りだした幻想にすぎず、その追求こそ逆に専制政治を招来しかねないからだ。
「霊的な力」を実体化し、その「高次元」の到来を待つのではなく、「霊的な力」を人間が括りだしてしまう観念的転倒の相対化につねに努め、現に形成されている関係の「組み替え」(変革・改良)に取り組むことこそ、市井の少なくない人びとが今日も願い模索していることであり、職業革命家(政治家)や一部学者知識人よりは転倒(フェティシュ)を免れている。
近代的知を相対化しなければならない。
たとえ、貨幣物神がどんなにしつこく深く介入してこようが、汗をかきながら「感(はたら)く」とき、夕暮に一杯のワインで疲れを癒やすとき、あるいは愛を交換しあうとき、そして、関係を少しでもよくしたいと願うとき、言い換えれば、経済的価値交換より深いところで、心的価値を交換しあっているとき、人は「いま・ここ」を肯定し生きている。
いかなる傾向の政治権力も、こうした自然過程での味わいを抑圧したり破壊する権利をもたない。出発はそこからではないだろうか。


