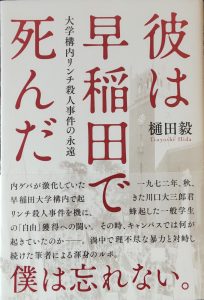ウクライナ侵攻 ロシアの「大義」と「陰謀」の系譜
~ネチャーエフ/スターリン/プーチン~
「目的は手段を浄化しうるか」
◯自然過程と破壊する力
人は、生まれ、育ち、はたらき、(子をつくり育て、)老いて、死ぬ。
1日のサイクルに目を転じれば、起きて朝食を摂り、はたらいて(活動して)汗を流し、夕餉に疲れを癒し、寝る。その日々の繰り返しである。
悩みや苦しみを抱えながらも、こうした自然過程を味わいながら、人は一生を終える。
誰もがこの自然過程を免れることはできないが、この日々の営みこそ、一人ひとりにとってかけがえのない歓びであり、価値である。

しかし、この自然過程を突然、根こそぎ破壊する力が生起することがある。
ひとつは、地震や津波、嵐、火山爆発などの災害。だが、これは自然の力によって起きるもので、自然過程の内なることである。
もうひとつは、戦争。これは人間が人為的に起こすものだ。いわば、反自然的できごとである。
◯くらしを破壊する戦争の「大義」
むかしは、小さな村落どうしでも争いがしばしば見られた。たとえば水争いで、これは「必要性」に迫られ切実で、「大義」が大手を振ることはなかった。そうした争いは、今日、技術と知恵を生かして、ほぼ回避できるようになった。人々の「学び」だ。
近代の戦争は、「大義」を掲げる。ほとんどの戦争で、立派な正義が掲げられる。
20世紀は「戦争の世紀」だった。第1次、第2次の世界大戦があり、また後半には東側と西側との「冷戦」が続いた。しかし、最後にはソビエト連邦が崩壊。21世紀という新しい世紀は、大戦はもとより、あからさまな侵略・侵攻も人類の叡智で防ぎうるもの、と多くの人々は思った。それが「戦争の世紀」から学んだ人類の知恵のはずだった。
だから、大国ロシア国によるウクライナ国へのあからさまな侵攻が、今世紀に起こるのは歴史の巻き戻しと映る。
ウクライナでのいのちや生の営み、街への暴力的破壊に言葉を失う。
国家とは、他国家との関係において成立している以上、国家間での争いや摩擦は避けがたい。片方にだけ100%の非を求めるのは筋違いだろう。長く複雑な歴史的経緯も背景としてみなければならない。それにしても、この侵攻と破壊はとうてい許されるものではない。
※親露・反米的な論(たとえば、イマヌエル・トッドのテクストやオリバー・ストーンの映像等)をしっかり受けとめても、その想いはいささかも変わらない。

銃撃が。100年後、ロシア軍はウクライナの街頭で同じ
ように街頭デモに銃撃を(『写真集 トロツキー』より)
今回も、どの戦争とも同じように、ロシア側は「大義」を掲げた。ウクライナ領域内におけるロシア「民族の保護」であり、ウクライナの「非ナチ化」であり、歴史的に俯瞰すれば、「ロシアとウクライナの民族的一体性」である。その名のもとで、嫌がるウクライナを弟分とみなし、兄貴分が無理矢理、配下に置こうとしている。
そんな大義によって、赤ん坊から老人まで、土地の人々のくらし(自然過程)が瞬時に破壊される。
◯ロシアの体制的特徴
ウクライナ侵攻からみえてくるのは、ロシアという国・大地の特殊性である。
ここ200年ほどに限ってみても、ロシアの政治体制を特徴づけることが3点挙げられる。
① ツァーリズム(ツァーリ(皇帝)専制支配体制)
② 「何でも許される」という陰謀主義
③ ロシア的な「大義」
そして、これら3者がからみあっている。
◯変わらぬツァーリズム
ロマノフ王朝では専制政治が行われた。たとえば200年ほど前、皇帝ニコライ1世は、政治警察を皇帝官房に直属させて強化し、革命につながる動きを厳しく弾圧。専制君主として君臨した。
それから1世紀ほど経た1917年、ロシア革命が起こると、ニコライ2世が退位。今からちょうど百年前の1922年には、ソビエト連邦が成立した。
それは、ツァーリ体制の崩壊を意味した、はずだった。なぜなら、ロシア革命とは、持たざる者であるプロレタリア(無産階級)と貧農の解放を目指す革命であり、彼らを「代表」するボリシェヴィキが権力を握ったのだから。
ところが革命後に、奇妙なことが起こる。領導した中心人物レーニンが亡くなると、遺体は廟に祀られ、「レーニン主義」が生まれる。演出したのは、スターリンだ。
今度はレーニンを祀って利用するスターリン自身が絶対的権力者(ツァーリ)の地位に就く。個人崇拝(スターリン主義)の出現である。

(『写真集 トロツキー』から)

(同)

“フェイク彫像”をつくらせた。時代は変われど、
フェイクはいつも生みだされる
公安警察チェーカーが、権力に盾突く者には容赦ない弾圧を加え、絶対の恐怖政治を敷いた。党幹部、党員、知識人はじめ、1000万人近い人々が「反革命」のレッテルを貼られ処刑、粛清された。
党の独裁のもとでは、権力者が主張さえすれば白は黒とみなされ、黒は白と認定される。党幹部の中には、スターリンによってデッチあげられた容疑をあえて「自白」して処刑を受け容れたものもいる。「革命の大義」を守るためだった。
「プロレタリア独裁」という名の下でボリシェヴィキが権力を握り、スターリンが敷いた専制は、ロマノフ朝以上のツァーリ的恐怖政治をもたらした。
しかし、ソビエト連邦も1991年に崩壊。今度こそツァーリ体制は崩壊するはずだった。
ところが、混乱を経て、今世紀に入ってからは、プーチンが再び伝統的体制を敷き、その座に君臨している。
こうしてみてくると、ロマノフ王朝時代、そしてロシア革命後の「マルクス・レーニン主義」を掲げるスターリン体制(ロシア社会主義)、さらにはプーチンと、どうやらツァーリ的体制は変わらずに続いている。今日、形式的な選挙は行われているものの、政治体制はこの200年に限っても、あまり変わっていない。
◯「なんでも許される」 ネチャーエフ的土壌
維持されたツァーリ体制は、これを支える「陰謀と粛清」という負の遺産も引き継いだ。
2番目の特徴、陰謀主義である。陰謀とは秘密裏に企む謀りごと。虚偽、デッチあげ、脅し、テロなどを駆使し、プロパガンダを活用。権力の奪取・維持のためには「何でも許される」とするのが陰謀主義である。
ロマノフ王朝時代、クーデターや反権力運動、決起がしばしば起こった。
19世紀前半には、貴族出身の青年将校らが決起した。デカブリストの乱は、専制政治と農奴制の打破を目指した。
19世紀後半には、ナロードニキの運動が起こる。インテリゲンチア(知識人)が「人民(ナロード)のなかへ」を掲げる運動だったが、結局、農民は起ちあがらなかった。
反革命と革命の激しい攻防がロシアではみられた。
その中で、異様な輝きを放つ人物がいた。セルゲイ・ネチャーエフ(1847~1882年)である。
彼は断乎として主張する。唯一の喜び、唯一の報酬、唯一の満足は「革命の成功」である。革命とは非情なもの。「その目的を妨げるものは、いつでも自分の手で殺す用意がなければならぬ」と(『革命家の問答書』)。
革命とは「陰謀」である。革命という目的のためには、手段を選ばない。虚偽や脅迫、殺人……あらゆる手段が許される。陰謀こそ権力にたいする最も有効な行動である。
革命という「目的のためにはすべてが許される」。このような陰謀主義の毒は、専制と反権力の争いが長く続く中で、ロシアの大地にじわりと蔓延り、ネチャーエフ個人の思想というより、ロシアの政治的特徴を色づけているようにみえる。
不幸なことに、「目的のためには手段を選ばない」とする陰謀主義は、革命後のロシアでも生き続ける。
ネチャーエフのテーゼは、すでにレーニンにもみられた。ボリシェヴィキは、たとえば「われわれはソビエト(評議会)の味方であって一党独裁の味方ではない」と起ちあがったクロンシュタットの水兵たちの反乱を弾圧。こうした動きは、スターリンにおいてより露わになった。
目的、つまり革命の達成・維持という「大義」を実現するため(のボリシェヴィキ支配貫徹のため)なら、その手段はどんな形をとっても許される。攪乱工作、テロ、粛清、毒殺、戦争……すべてが許される。
プーチンは、ソ連時代のカー・ゲ-・ベー(国家保安委員会)の出身だ。
そもそもは、レーニンの時代、反革命・テロ・サボタージュを取り締まるべくチェーカーが設けられ、1922年にはゲー・ペー・ウーに改組。これが変転し、のちにカー・ゲー・ベーとなった。秘密警察であり、国内の治安活動のほか、対外諜報活動も行う。陰謀技術を駆使する組織だ。
彼はカー・ゲー・ベーのノウハウ、人脈を駆使して、ツァーリの座に就いた。
わたしたちがしばしば目にする、プーチンの象徴的な映像がある。きらびやかな宮殿の扉が開けられると、臣下が両側に列をなし拍手を送る中、体を左右に揺さぶりながら花道を得意げに歩く彼の姿だ。ツァーリはナルシストでもある。スターリンも、肩から胸にかけて数え切れないほどの勲章で飾りたてた。その裏で、彼らは陰謀と粛清に励んだ。
ネチャーエフ的な陰謀主義は、2世紀を経て一貫して変わることなく、ロシアに棲息している。
どうして、「目的は手段を浄化する」というテーゼが現代にも生き続けているのだろう。「陰謀」は大地にも支えられているはずだ。
◯声高な「大義」は「陰謀」を引き寄せる
陰謀主義は必ず、堂々たる大義を奉じる。陰謀と大義は、コインの裏表である。
ロシアでは、革命前から、西欧派と反西欧派(スラブ主義)の2潮流が存在し、つねにせめぎあってきた。近代の日本にもみられた対立である。
西欧文明への反発は、心情としてわからないではない。なにも西欧的価値観が絶対であるはずはない。西欧側の文化を、物質主義的・技術主義的、安易な進歩主義だ、と批判することもできるし、それはロシアの庶民に根強く息づく心情かもしれない。
ロシア正教がある。歴史を踏まえた大国ロシアの誇りもあろう。ナチスとの壮絶な戦争を制した体験も極めて大きい。
「偉大なるロシア」への回帰運動。ヨーロッパでもアジアでもないユーラシア主義。さらにこれをバージョンアップした新ユーラシア主義。こうした「大義」は、心情的には共感を呼びやすいのだろう。わからなくもない。
しかし、高々と掲げられる大義(回復運動)は、版図の拡張(侵略)とつながっている。さらに、現実的な経済利害と結びついている。あるいは支配層の生々しい欲望や名誉欲につながっている。
政治世界に陰謀はつきものだが、声高な大義ほど陰謀への依存を強める。
◯反欧米の受皿をツァーリズムにしか見出せない不幸
ツァーリ体制、陰謀主義、大義の3つが、互いにからみあいながら、ロシアの政治的な特殊性がかたちづくられているようにみえる。
ウクライナ侵攻後、独立系メディアによるロシア世論調査でも、プーチン支持率が80%を超えた。これを受け、ロシア文学者の亀山郁夫氏は、ロシア民衆の闇の部分を指摘している、「この数字に示された『愛国心』は、逆にうそに固められた国に生きる屈辱と恐怖の大きさの証でもあるのです」(毎日新聞)と。ツァーリ体制と陰謀主義の状況を生き続けてきた人々の「屈辱と恐怖の大きさ」が、支持率の高さを物語っている、と。あるいは「ロシア人の受動的メンタリティ-」を指摘している。
ここはもう少し分析を深める必要がある。
ロシア人の多くは、欧米的な文化・風潮に大なり小なりの異和を抱えているのだろう。理性的人格としての主体の確立を前提とする近代欧米的な世界観・スタイルとは距離をとっているのだろう。
しかしこのとき、ロシアの人々が思想の拠り所とするものは何だろうか。ロシア革命とその崩壊を経て、どこに戻るのか、あるいは新しくどこに着地するのか、さだかではない。ロシア革命とその後の社会主義体制について、全否定でも全肯定でもなく、きちんと総括しきれていないのではないか。
結局、戻るところは、200年以上前から続くツァーリズム的な大義である。いいかえれば彼らは、欧米的近代批判の受皿を、ツァーリズム的大義のほかに見出せていない。あるいは、ロシア正教に求めるほかない。
◯「目的は手段を浄化しない」
20世紀の後半までは、「目的は手段を浄化する」というテーゼに対し、世界は即座に断固たる否定を与えられなかった(たとえばテロの容認)。「プロレタリア解放」「民族の解放・救済」……さまざまな大義が叫ばれ、まだリアリティをもっていたからだ。
ひとごとではない。振り返れば、私たちの国も戦前は「大東亜共栄圏」という大義を掲げ、戦後には科学的マルクス主義を大義とする政治党派同士が血を流してきた。
「目的は手段を浄化しない」――21世紀は、このことを、国境を越えて人々が共有し、「大義」を少しずつでも相対化させていくほかない。
現実は厳しい。大義を高々と掲げる国に囲まれている。「人類の最終的解放」をめざすマルクス・レーニン主義を「科学的真理」として奉じる前衛(党派)が支配する専制政治国家や、社会主義を掲げながら家系を絶対化する専制政治国家がいまも周囲に存在し続ける。
あるいは、民主主義的なはずの「先進国家」内であっても、「陰謀」で世界をとらえる史観や陰謀説にとらわれるグループが勢いをもっている。
「ツァーリ・陰謀・大義」的な国家や運動の傾向は、ロシアだけのこととは言いきれない。
今回のウクライナへの侵攻について政治的な解決が急がれるが、その努力とは別に、私たちにできることは、時間を要するけれど、情報にせよ、組織にせよ、「開いていく」方向に進めることだ。少しずつでも庶民同士がつながり、閉じられた陰謀的専制体制に風穴を開け、互いに「大義」を相対化する・できるようにしていく。SNS等のデジタルテクノロジーも助けとしながら。
自然過程こそもっとも守られるべき価値である。そこから離脱し肥大化する観念としての「大義」は、つねに自然過程の側から相対化しなければならない。