松本輝夫 『言語学者、鈴木孝夫が我らに遺せしこと』
~書評 と 鈴木孝夫さんの想い出~

「世界を人間の目だけで見るのはもう止めよう」
一昨年亡くなった鈴木孝夫さんは、ユニークな英語教育論、あるいは日本語の唯一無二性評価など、言語学分野での大きな足跡から、「言語学者」と紹介される。
しかし、氏が論及した分野は、言語という一専門領域にとどまらず、文化、自然・地球(環境問題)まで広く及んだ。スケールの大きな思想者でもあった。
この本は、そんな氏の業績と生涯を総合的にいきいきと描いている。書名は少しいかめしく感じられるが、主な著書や講演の主旨がわかりやすくまとめられたアンソロジーでもある。
これまで鈴木さんの著書・発言にある程度接してきた人にとっては、復習の幸運に恵まれる。また、十分読みこめていなかった点について、そうだったのか、と気づかさせてくれる。新しい発見にも出逢える。
もちろん、これから接する若い人には、格好な鈴木孝夫ガイドブックの役割も果たしそうだ。
氏がテーマとしてきた「ことば」「文化」「自然(地球)」を「トライアングル」として捉え論じた鈴木孝夫論は、他にないだろう。
恩師井筒俊彦との決別(弟子からの絶縁宣言)はじめ、興味深いエピソードも随所に散りばめられている。
◎“トライアングル鈴木孝夫論”がなぜ可能だったのか
本書で貫かれているのは、「世界を人間の目だけで見るのはもう止めよう」という鈴木さんの言葉だ。いいかえれば、西欧発の人間至上主義、それが招く経済成長主義への叛旗である。早くから地球環境の危機を受けとめていた氏の言葉は重い。地球をこよなく愛するがゆえの訴えでもある。
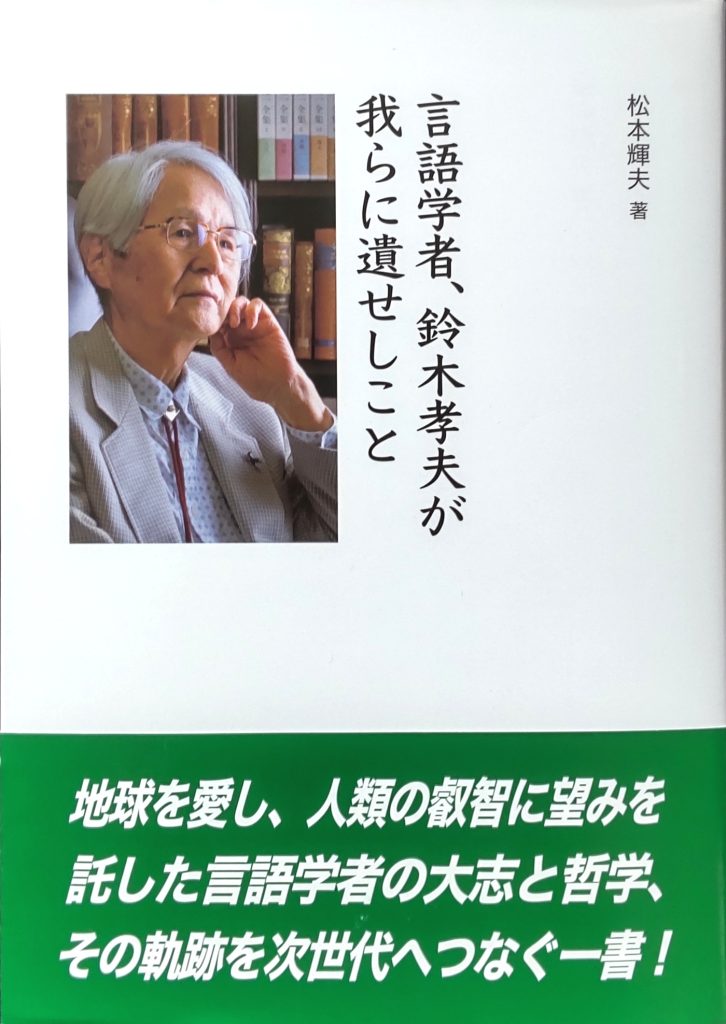
では、こうした総合的な“トライアングル鈴木孝夫論”は、どのようにして成立が可能だったのだろう。
著者の松本輝夫さんは、学界の人ではない。谷川雁に惹かれて、谷川が経営陣の一角を担っていた言語教育事業体であるテック(のちのラボ教育センター)に入り、長年働いてきた。
その組織に、鈴木さんは草創期と今世紀に入ってからの2度ほど、深い関わりをもった。とくに、後者の時期、70代後半になっていた鈴木氏は、全国各地でラボの講演を担い、それを著者らが支えたようだ。
そして著者松本さんは退職後ほどなく、「鈴木孝夫研究会」(通称「タカの会」)を起ちあげて主宰。同会で、氏の講演と会員の交流を演出してきた。
じつは私は、著者が若い頃、希有なオルガナイザーとして活躍する姿にときどき接してきた。その資質というか力は、「タカの会」でも遺憾なく発揮される。密度の濃い会の活動を支え、晩年の鈴木さんの伴奏者の役割も果たしてきた。
こうした経緯があるからこそ、本書では、鈴木さんの個別専門領域を超えた思想者としての活躍を総体として活写できたのだろう。
◎「西洋の尺度」の絶対視をやめる
私が初めて鈴木孝夫さんに会うことができたのは、雑誌の取材で、だった。氏の軽井沢の住まいに出向き、お話をうかがった(これについては後述)。恥ずかしながら、それまで氏の著述をよく知らなかった。取材のためにざっと目を通したくらいである。

氏の論と本格的に向きあい始めたのは、著者松本さんらが開いていた小さな研究会で氏の講演を聴いたのがきっかけだ。
直後に発足した「タカの会」でも、何度か講演に耳傾ける機会を得た。
ちょうどその頃、欧米が牽引してきた「近代」をどう乗り越えるか、というテーマと苦闘してきた小生にとって、ギリシャ語、ラテン語、英語をはじめ諸言語に精通し、豊富な海外生活も踏まえたうえで、日本語の卓越性を強調する氏の話には、わが意を得たりの感をもった。
鈴木さんは、戦後、私たちが当然のこととして受け容れてきた「西洋の尺度」を絶対視することはやめよう、という。「自他の区別の超克」をはかる傾向が強い日本文化とは対照的に、「自己と他者の対立を基礎とする」西欧文化を相対化してみようと訴えた。

こうした鈴木さんの論と響きあう考えは、哲学の分野にも見出せる。
たとえば、ハイデガー研究で知られる木田元さんは、晩年大胆にもこう語っていた、「日本には哲学がないからだめだ、といったふうなことを言う人がいますね。しかし、わたしは、日本に西欧流のいわゆる『哲学』がなかったことは、とてもいいことだと思います」(『反哲学入門』)。
古代ギリシャに生まれ、キリスト教文化と融合し構築された西欧の「哲学」は、「人間」を至上とするが、それを世界の基準とするのは傲慢だ、と木田さんは言う。
「西欧文化圏が立てた超自然的原理」(イデア、神、理性・精神)を基に上から自然を見ることが、西欧では「哲学」と呼ばれ、普遍とされたが、これは普遍でもなんでもなく、特殊なローカルな見方にすぎない、と。日本人は「自分が自然のなかにすっぽり包まれて生きていると信じ切って」いるのだから。
木田さんのこうした捉え方は、鈴木さんの「世界を人間の目だけで見るのはもう止めよう」と呼応する。

また、生命形態学者の三木成夫さんは、動植物のからだの仕組みと発展を形態学の立場から辿り、「精神としての人間」を至上とする西欧の「人類至上主義」は「宇宙との交流を妨げる一つの元凶ともなりうる」(『胎児の世界』)と厳しく警鐘を鳴らしていた。
ちなみに、鈴木、木田、三木の3氏は、二十歳前後、あるいは10代後半に敗戦を迎えている。彼らが同じような認識をもつに至ったことに、時代が関わっていたのかどうか、分析の誘惑に駆られるが、追求する時間の余裕をなかなかもてない。
◎「右と左」という近代主義の止揚
本書によれば、保守の論客とみなされてきた鈴木さんは、自らの立場について、「私は右翼でもないし左翼でもない。強いて言えば<両翼>だ」と語っていたようだ。
その通りだと思う。

日本列島における今日の思想的不幸の一因は、「保守」を自称する人たちの多くが、じつは「近代主義」の土俵に立っていることに無自覚であることに求められる、と私は思う。もちろん、反対側の陣営にも概ね同様にいえるが。
そういう意味で、氏は擬制の「保守」とは異なる。
たしかに「近代」そのものは全否定できない(つまり「反近代」ではない)けれど、西欧的文明から生まれた「近代主義」を相対化しなければ、これからに希望は見出しえない。
「近代主義」という同じ土俵上でせめぎあう右と左、保守と革新、保守とリベラルという貧しい二項対立の止揚こそ、めざされるべきである(これについては、『「ありがとう」の構造』でも書いた)。こうした捉え方も、鈴木さんの考えから促された。
◎日本文化は「近代主義」を超える好位置に
今日の状況をさらに困難なものにしているのは、かつての「西洋」と「東洋」という対項では情勢を語れなくなったことだろう。たとえば中国の覇権主義化だ(もともと、インド、中国、日本などを括って「東洋」とするには無理があったが、当時の欧米列強の侵出に対抗するためにやむをえない面もあった)。
「西洋」と「東洋」の二項対立は、太平洋戦争期で躓きの石になった。三木清や西田幾多郎らの京都学派もそうした見方から自由ではなく、それがむしろ“東亜の盟主”を謳う日本(軍国主義)のアジア拡大(侵略)の正当化に口実を与えることに結果した(このあたりは鈴木さんと見方がやや異なるかもしれないが)。

しかしもはや、(西洋に対する)「東洋」、あるいは(ヨーロッパに対する)「アジア」とひと括りすることはできない。中国の覇権主義化とは「近代主義」の亡霊であるからだ。ゆえに鈴木さんは、こうした情勢も踏まえ、西洋と東洋という対項とは別に、「大陸」「ユーラシア」と日本という枠組を設けるようになったのだろう。
20世紀に息絶えたと思われていた「マルクス主義」的なものが、今日逆に蔓延り、肥大化している。近代主義の最たるものである。
「マルクス」とはひとまず分けるが、「マルクス主義」は、西欧的近代が生みだしたイデオロギー(近代主義)である。絶対の正義・真理を体得する前衛(為政者)が庶民を導く。無謬の党に抵抗する者は「反革命」であり、弾圧する。このイデオロギーが、西欧以外の地でローカライズされ、ロシアではロシア・マルクス主義(マルクス・レーニン主義、スターリン主義)、中国では毛沢東主義を生んだ。いずれも固有の風土と密通し、絶対主義が強化された。
それらの「近代主義」イデオロギーは20世紀で終焉したはずと思っていたら、今日のロシアでスターリンの亡霊が甦り、中国では習近平主義が生みだされている。目眩を起こさせるような事態が、いま眼前に広がっている。
日本列島の人びとは、どうしようもない「負性」を抱えている(なにより私自身がそうだ)。しかし、列島の言葉とその存在観(西欧的にいえば「哲学」)は、「近代主義」の病いとは距離をとりやすいところに位置している。鈴木さんはそんなポジションになんとか希望の光を見出していた。
私も同感である。本書を読み終えて、改めてそう思う。

[想い出] 千ヶ滝「小屋」の鈴木孝夫さん
ちょうど20年前のこと。雑誌の取材で、鈴木さんの軽井沢の住まい(山荘)にお邪魔させていただいた。氏は御年77歳だった。

(現東芝)製のものが健在
テーマは、お金にまつわる「シニアの生き方」のようなもので、氏にふさわしいテーマではなかった。なぜなら、氏のモットーはいたってシンプル、「ものは買わないで拾う、捨てないで直す」だったから。
取材時よりもさらにまえに、『人にはどれだけの物が必要か』が出版され、氏のミニマム生活は広く知られていたが、定年後すでに年金生活を迎えていたこのときも、生活スタイルはまったく変わっていなかった。むしろより徹底していたのかもしれない。
「食べ物と肌着類以外は買わない。服はもらいものがほとんど」と言う。
居間や台所に置かれた生活必需品、備品を見せていただき、驚いた。

腕時計は初任給で買ったシチズンの手巻き式というから、半世紀以上まえのもの。
ソファや電気スタンド類は、近所のホテルの廃品や、人からもらったものばかり。
トースターは結婚時(当時50年以上まえ)の花嫁道具が現役。
扇風機は、東京芝浦電気(現在の「東芝」ロゴ以前なので1950年より前)と表示された時代物。
残飯は一切出さない……。
3R、つまりリデュース、リユース、リサイクルを徹底する生活ぶり。

10坪足らずのこの建物で、年間の1/3を家族4人で過ごした。野鳥のさえずりに耳を傾けながら
「地球の荒廃を目の当たりにして、右肩上がりの経済成長を望むのは間違い」ときっぱり。
とはいうものの、苦行僧の禁欲主義的なイメージはいささかも見られず、奥様と二人で日々の暮らしを楽しむ。
年金生活に入り、「ものを買わない生活」で生じた余りは、留学生の日本語学習のための教育基金や、イヌワシやオオタカの巣を守る自然保護団体に寄付をしている。「受益者たるよりも授益者たれ」と。

『ことばと文化』など名著は、ここから生まれた
「勲章を受けるつもりはない」と権威にへつらわない。自分の気の趣くままに生きてきた。借りのない人生、人に迷惑をかけない人生でありたい、と。
案内をしてくれたり、お話しているとき、身のこなし、指づかいに強張りが見られず、しなやかで、存在自体がオシャレだった(ブランド物など一切身に着けていなかったけれど)。
人は誰もが老いる。生活面で周囲の支えが必要となるときが来ることは避けられないけれど、氏は最晩年期もみごとに生ききった。
最後の数年間はご家族や施設の職員らの補助、介護に支えられたのだろう(教員時代は大学でも無駄な照明を次々に切ったようだが、高齢者施設内でも節電に努め、無駄な灯りがあればただちにスイッチを切り、職員の方々を慌てさせたという話を聞き、苦笑させられた)けれど、間際まで「タカの会」等に向けて言葉を発信し、周囲の人に別れの挨拶状を送るなど、見事な晩年と最期を迎えたようにみえる。そのことも、本書で知った。
末期(まつご)の姿からも、学ぶべきところが多い。
享年満94歳。
教えに感謝しつつ、改めて、合掌。


