國分功一郎 『暇と退屈の倫理学』 書評(上)
[雑記帳]
若者によく読まれる哲学書だそうで、なるほど好感がもてる。ただし、西欧近代的知の枠組に依拠していることに疑問を感じる。あえて、その点について触れてみたい。
遅ればせながら、『暇と退屈の倫理学』である。
単行本発売当時(2011年、増補版2015年)から、哲学書コーナーに並ぶので気にしていて、文庫本(2022年)を買ったものの、脇にしばらく積んでいた。つい最近ページを開いた次第。
私から見れば子ども世代に当たる若手哲学者が、「暇」と「退屈」をキーワードに倫理を考えている。
本書がテーマとする分野は、2008年から2011年まで私が旧サイトで連載していた「スローワーク論」とほぼ重なっている(連載は改稿して、『「労働」止揚論』としてまとめ、2018年刊)。なので、興味深く読んだ。
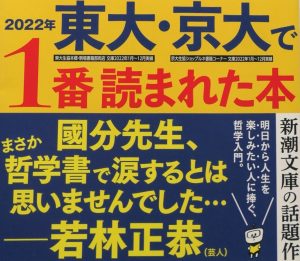
好ましいのは、イデオロギッシュではないこと。読みやすさをこころがけているからこそ、「哲学」という近年不人気な分野でありながら、それなりに売れているのだろう。帯に「2022年 東大・京大で1番読まれた本」とある。
今日の若者には「暇と退屈」が切実な課題なのだろうか、とも驚く。
著者はこう表明している、「<暇と退屈の倫理学>は革命を目指してはいない。だが、社会総体の変革を目指している」と。現状を全否定するのでもなく、現状肯定に甘んじるのでもない姿勢にも好感をもつ。
評価してよいのは、「疎外」という概念自体を、正面から取りあげたこと。ただ、そのとらえ方には同意しがたいところもあり、長くなるのでそれは次回に回す。
〇本書の趣旨をまとめてみると……
まず、本書の要旨は以下のようになる。

かつて人類が遊動(狩猟採集)生活をしていたときは、「物があふれる豊かな社会」であり、「退屈」することはなかった。しかし定住生活に入り、退屈を強いられ、それを紛らわせることが、人類の恒常的な課題となった。
今日の労働者は暇を得ることになったが、暇を何に使えばよいかわからない。労働者は「暇」を搾取されている。
暇の中で、どう退屈と向きあうべきかが問われる。
キーワードは「贅沢」。「必要を超えた支出があってはじめて人は豊かさを感じられる」のだ。「人が豊かに生きるためには、贅沢がなければならない」。浪費できる社会こそが「豊かな社会」である。贅沢であるには浪費できなければならない。
「消費」と「浪費」は違う。
今日の消費社会で人々は、物に付与された観念や意味(記号)を消費している。だから、消費には限界がない。消費し続ける。
他方、浪費を感じるのは、「必要の限界を超えて支出が行われるとき」である。浪費とは「必要のないもの、使い切れないもの」を「受け取り、吸収すること」だから、必ず限界に至る。浪費は物の受け取りだから、とどめのかからない「消費」と異なり、必ず満足してどこかでストップする。
「浪費」できる社会こそ「物があふれる豊かな社会」である。問われるのは、「贅沢」を取り戻すこと。
今日の消費社会で生じる「退屈」(現代の疎外)は、「観念」を対象としている消費から起こる。消費ではなく、浪費、つまり「物」を受け取り、その「物」を楽しむべきである。たとえば日常的な楽しみ……衣食住や芸術、娯楽を楽しむこと(これを著者は「浪費」と定義している)。生活の中に芸術が入っていく「民衆の芸術」が求められる。そうすれば、退屈は消える。
「誰もが暇のある生活を享受する『王国』、つまり暇の『王国』こそが、『自由の王国』」である。その王国を実現するための第一歩は、「贅沢」から始まる。
強引に要約すると、以上のようになる(「暇と退屈」自体の哲学的考察にもページが割かれているが、私は「暇と退屈」にほとんど馴染みがないので、端折った)。
まとめる作業をしていて、論のつながり、展開に疑問を感じるところが少なくなかったのは、私の頭脳の弱さだけではないように感じる。
ここから、疑問に感じたこと、著者に問いかけたい点を、あえて明らかにしてみる。
論点は、「消費と浪費」、「自由の王国と必然の王国」という二項構造に絞られる。
〇「浪費」と「消費」の対置
國分さんは、「贅沢」に生きるために、「消費」を批判し、「浪費」を勧める。だが、「消費」批判のための、「浪費」概念導入には疑問を感じる。
著者によれば、浪費とは、「必要を超えて物を受け取ること、吸収すること」である。「浪費はどこかで限界に達する」。
他方、消費には限界がない。なぜなら、「消費の対象が物ではないからである」。じつは人が消費するとき、物を受け取ったり吸収しているのではない。物に付与された観念や意味(記号)を消費している。だから、消費には限界がない。
狩猟採集民がそうであるように、消費ではなく、「浪費できる社会こそが『豊かな社会』である」。
〇ボードリヤールの「浪費」論の導入
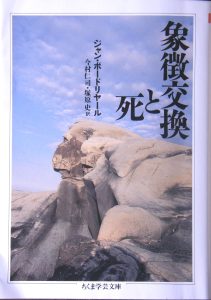
この論は、著者も名前を挙げるボードリヤールの消費社会論をベースにしている。
私から見れば、ボードリヤールは、フランスでも屈指と言えるほど冷笑的で、西欧的知の負性を一身にまとった人物である。
ちなみに、彼の主著の一つ『象徴交換と死』は、2001年、ニューヨークのツインタワーなどに旅客機ごと突っこみ、民間旅客を巻き添えに激突死を敢行した9.11事件の首謀者・実行者に強い影響を与えたのではないか、と私は睨んでいる(拙著『「労働」止揚論』)。言い換えれば、彼らは『象徴交換と死』の字面をそのまま実行したと思わざるをえない。
そんなボードリヤールの「浪費」論に、私は首肯しがたい。
ボードリヤールによれば、近代の社会では消費は「有用性」(必要性)に縛られていたが、現代の消費社会では、モノではなく、記号としての消費に縛られている。そこでは、人々は「役に立つもの」「有用性」としての商品を消費しているのではない。モノの商標、ブランド、記号を消費しているにすぎない。
すると、消費が「きりがない」。現代は余暇ですら、記号・ブランドの消費に振り回されている。
古代社会には「真の豊かさ」があった、とボードリヤールは断じる(『象徴交換と死』)。今日の消費社会とはまったく異なり、将来を心配するような気遣いなんて考えない「浪費性」に満ちていた。「有用性」などに縛られない「浪費」の世界を、「未開社会人」は存分に生きていた。そこにこそ「真の豊かさ」がある。
だから、ボードリヤール、そしてこれを承けた國分さんは、消費ではなく浪費を対置して、これを勧めることになる。國分さんは、アレンジを加えて、浪費には切りがあるから、限界を知ることになる、と。
〇「消費」への対抗に「浪費」を持ってくることへの疑問
記号(ブランド)を消費しているだけとして、今日の消費社会のありようを批判することに、私も異存はない。
しかし、それへの対抗に、「浪費」を持ちこむことには首を傾げざるをえない。

そもそも「有用性」(何かの役に立つもの)に対して、「浪費」的な世界、蕩尽、消尽を対置させたのは、マルセル・モースを経て、ジョルジュ・バタイユである。「出し惜しみ」しない贈与、あるいは「富の破壊」こそ、有用性(的消費)の対極に位置するものとして、バタイユは称揚した。そこには、有用性世界を蹴散らしたいという西欧的知のひたむきさがあった。バタイユには可愛らしさがまだ感じられた。
だが、ボードリヤールになると、これを妙に皮肉化させる。
國分さんが、記号を消費することの空しさに警鐘を鳴らすのはわかるけれど、フランスの中でももっともシニカルな知識人の「浪費」をもってくる必要はない。
〇列島人には馴染みにくい「浪費」概念
列島人からみれば、浪費とは無駄遣いである。「必要を超えた支出」である無駄遣いを、「浪費」として持ちあげるまでもない。「もったいない」ことだから。
「清貧の思想」へ戻れなどというつもりは毛頭ない。ただ、とりわけ現代はなおさら、無駄遣い(浪費)は倫理的によろしくないし、列島人の感性にもふさわしくない。
記号の先端を消費して、他者からの承認や優越を得ようとする欲望の空しさを、ただ静かに暴けばよいことだ。無理やりフランス知識人の「浪費」「消尽」「濫費」といった概念を持ちこむのはどうだろうか。
「浪費」概念を呼びこむ西欧的思考を支配しているのは、有用性(必要性、自然性、必然性、動物性)に唾を吐き、有用性を超えた領域に至高性、自由を求める知的傾向である。古代ギリシャのプラトン以来まったく変わらない。
さらに、未開社会や古代社会に「真の豊かさ」を見出して、これをユートピアとして括りだし、今を斬るボードリヤールも、近代的思考の典型である。
〇生活と芸術・娯楽

本書結末近くで、國分さんは、「贅沢」とは日常的な楽しみの中にあることを示唆する。
「<物を受け取ること>とは、その物を楽しむことである。たとえば、衣食住を楽しむこと、芸術や芸能や娯楽を楽しむことである」と。そして、「物を楽しめば、贅沢を得られる」と。この結語には同意したい。当然のことであるから。
だが、これと、ボードリヤール的浪費はちっとも結びつかないし、結びつける必要もない。
また、「生活の中に芸術が入っていく」という言葉にこめた想いはわかるが、表現が妥当ではない。「生活の中で芸術が生みだされる」とするほうが好ましい。
ボードリヤールを捏ねて引き合いにするまでもなく、日本列島人はそうしたスタイルを承け継いできた。もちろん西欧にも、國分さんも名を挙げたように、モリスのような人もいるけれど。
こういう「有用性を大切にする」列島的スタイルは、「有用性をバカにする」ボードリヤール的知識人とは異質であり、正反対に位置する。ボードリヤールの浪費論など導入すると、かえって混乱を招き寄せる。
※ 日本ではかつて見田宗介さんが、バタイユ的なconsumationとボードリヤール的なconsommationを対比して論じていて、バタイユの「消尽」のほうに目を向けていた。見田さんの視線はまともだと思う(『現代社会の理論』-情報化・消費化社会の現在と未来-)。ただ、彼も、「生産の自己目的化の狂気」の問題とどう向きあうかの姿勢がいささか弱かったようには感じる。むろん、それは私自身の課題でもあるけれど。
〇「労働日の短縮」
國分さんがハンナ・アレントの労働論を批判するのはまったく正しい。
拙著『「労働」止揚論 ~働くから感(はたら)くへ~』でも、すでにアレントの労働論の矛盾について批判した。また、映画批評『パーフェクトデイズ』でも、簡単に触れた。
さて國分さんは、誰もが暇のある生活を享受する「王国」、暇の「王国」こそが「自由の王国」である、だれもがこの恩恵にあずかれる社会が作られねばならない、と結論づける。
そこで、求められるのは、マルクス『資本論』に明記されている「労働日の短縮」である。労働者にとって、「暇」は労働日の短縮によってもたらされる。
〇「自由の王国」「必然の王国」 という構図
この一般的見解自体に異を挟むものではない。
私が問いたいのは、「必然の王国と自由の王国」という構図に立脚するマルクスの、さらにこれをすんなり承け継ぐ立論である。
検討に入る前に、アレント、そして國分さんがとりあげた、マルクス『資本論』における「必然の王国と自由の王国」(長谷部文雄さんの翻訳では「必然の領域」と「自由の領域」)の要旨を、私なりにまとめると以下のようになる。
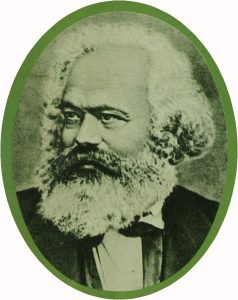
マルクスはこう語る――「未開人」が自然と戦わなければならないのと同じように、文明人も物質的生産を行わなければならない(生きるための衣食住の確保)。このように、食べる(自然的存在として生きる)ことを確保するための活動領域を「必然の領域」と呼ぶ。食べ生きるためには、「未開人」と同じように、現代人も労働しなければならない。
しかし、将来、この「必然の領域」の欲望が充たされるとき、その彼岸で「真の自由の領域」が始まる。そのために、労働日の短縮は根本的条件である――。
以上が、『資本論』第三部で述べている「自由の領域(王国)」「必然の領域(王国)」論のごくかいつまんだ趣旨である。
マルクスはこう書いているが、少し微妙なところがある。「自由の領域」は、物質的欲望を充たす「労働がなくなるところで、はじめて始まる」と書いているし、別のところでは、「必然の領域の彼岸において」、また「必然の領域を基礎としてのみ開花しうる」とも書いている。
おおきく括れば、「必然の領域」の欲望が(労働による生産物によって)満たされてはじめて、(これを基礎としてのみ)「自由の領域」が始まる、ということになる。
〇〝暁の二段階論〟 ~「必然」の次に「自由」へという思考~
ここには、マルクスの西欧的知の特徴(限界)が示されているし、またこの思考の枠組を承け継ぐ『暇と退屈の倫理学』の限界も示されている。
國分さんだけではない、西洋哲学にこだわる竹田青嗣さんあたりも、マルクスの「自由の王国」論に触れて、同様に、いやそれ以上に絶賛している、「ここでマルクスは完全に事態の本質をつかんでいる」と。「必然性の国」から解放されるときこそ、人間にとっての「真の自由の王国」が開花する、と。そのためにさらなる「生産性の向上」が必要だと(竹田青嗣『人間の未来』)。
私は、「必然・必要」が満たされた暁に、「真の自由」「完全な自由」が実現するという思考形態を、〝暁の二段階論〟と呼ぶ。「……が達成された暁に、完全な……がはじめて実現する」という二段階論。
〇〝曉の二段階論〟は無効ではないか
だが、この〝暁の二段階論〟は正しいのだろうか。
人間は自然(的存在)である。「未開人」だろうが現代人だろうが、マルクスのいうように、生活の維持・再生産に食物や衣服が必要である。自然的必然に縛られている。この世界をマルクスは「必然の領域(王国)」と表現した。そして、この需要を満たすために、「窮迫や外的合目的性によって規定される労働」を担わねばならない。
しかし、生産力が発展してこれが充たされるようになった暁に、「自由の領域(王国)」が開花する、始まる、とする。それが〝暁の二段階論〟である。
「必然(必要)」の領域が充たされた「先」、あるいは「上」に、真の「自由の領域(王国)」を見出そうとするのは、マルクスのみならず西欧的思考の特徴(限界)にほかならない。
もし、その「先」や「上」にそれを設定するなら、永久に「自由の領域(王国)」は実現しない。なぜなら、人間は自然(的存在)でしかありえず、つねに「必然の領域」の外には出られないからだ(飢餓を怖れ、ふだんは意識上に上らせないものの、不安を抱えている)。
だから、必然と自由という二項概念をあえて用いるとすれば、「自由の領域」は「必然の領域」とともにしか成りたたない。「必然の王国」の「先」に、ではない。
そもそも「自由の領域(王国)」と「必然の領域(王国)」を対項として立てること自体に疑問を感じる。
あえてこの二項を用いて表現するならば、日本列島では、「自由の領域」は「必然の領域」とともにしか見出しえないと受けとめ、生き、楽しみ、そこに美を求めてきた。
さらに、もっと言えば、「自由」という概念自体が問われる。
〇マルクスの時代には切実だったが

(大木健『シモーヌ・ヴェイユの生涯』1964年刊より)
ただし、150年以上前にマルクスが『資本論』でこうした論を立てたことを責めることはとてもできない。時代的にやむをえなかったと思う。
たとえば、『資本論』が書かれてからすでに半世紀以上も経ったパリの労働者の実状をみれば、納得できる。
今から100年ほど前、フランスの女性哲学者シモーヌ・ヴェイユは、鉄工所やルノー工場で働いた。そこでは労働者は「食べるために働く」「働くために食べる」という必要性、必然性の世界に完全に閉じこめられていた。いいかえれば、「暇」はまったく与えられていなかった。「必然の領域」を生きるだけだった。
だから、毎日工場まで通うために渡る橋からセーヌ河に飛びこみたいという誘惑に抗うことに、労働者たちには苦労した。「暇」を感じる時間をもてず、ただ生物として生きるための食と睡眠の時間を押しつけられるだけだった。
そのようにしか生きられなかった労働者の実状を踏まえれば、マルクスの熱い希求を責めるのはためらわれる。
〇ケインズが想定した「暇」と「生産性の向上」
ところで、ヴェイユが工場労働で絶望に陥っていた同じ頃、イギリスの経済学者ケインズは、人類の経済問題は100年以内に解決するか、少なくとも解決が視野に入ると考えた(「孫たちの経済的可能性」1930年、山形浩生訳)。
ケインズは、人間のニーズを、衣食住に関わる「絶対的ニーズ」と、人間関係上の「相対的ニーズ」(心理的なニーズ)に分け、絶対的ニーズは「人類の永遠の問題」ではなく、100年以内に解決するか、それが視野に入るだろうと予測した。そして、絶対的ニーズが解決されれば、「暇」が生まれるので、「退屈」せずに今を楽しむコツも必要とされるだろうと心配までした。
いわば、マルクスが「必然の領域」が解決し、「自由の領域」に入るとの将来展望と同じように、ケインズもまた、物質的ニーズが解決され、「生存のための闘争」が解決すれば、人類は明るい「太陽の下」に導かれるだろうと遠望した。
このように二人が揃って未来を希望をもって語ることができたのも、その時代に、著しい生産力の向上(経済的発展)がみこまれたからだ。そこで想定される生産様式は、マルクスが協同組合的生産、ケインズが資本制的な生産と、異なっていたけれど、どちらも「生産力」が発展し、「必要の領域」(絶対的ニーズの世界)から、「自由の領域」(相対的ニーズの世界)に入ることを遠望した。
そして、マルクスもケインズも、「労働日の短縮、労働時間の短縮」を条件とした。
〇〝暁の二段階論〟を問い直す
マルクスの『資本論』から150年以上、ケインズの「孫たちの経済的可能性」から100年が経過した。
私たちは「必然の領域」から「自由の領域」に移行しつつあるのだろうか。世界や国内の格差や収奪に目を瞑れば、「先進国」内では、ある程度そうだと、ためらいがちに言うことができよう。
けれども、生産力が伸張したはずの「先進国」内ですら、今も「経済問題」が必ず第一課題として挙げ続けられている。経済成長の課題を背負わされている。
マルクスの「必然的な領域」の欲求が満たされたはずであっても、ケインズの「絶対的ニーズ」(「生存のための闘争」)が解決されたはずであっても、「経済問題」が最重要課題であり、人々は経済成長に日々追いたてられている。
おそらく、これからも経済的課題に人々は追いたてられ続けるのだろう。なぜなら、人間が自然的存在であることを免れないからだ。
マルクスのいう「必然の領域(王国)」から人間は逃れられない。ケインズのいう「絶対的ニーズ」から人間は逃れられない。
とするなら、「必然の領域(王国」での欲求が満たされた暁に、「自由の領域(王国)」が実現するといった、暁の二段階論自体を見直すべきではないだろうか。
必然と自由という二項対立思考を問い直す。
生産性の向上を否定するのではない。ただ、それが「自由の王国」を招き寄せるという思考枠組に拘泥していてよいのだろうか。生産性向上が「自由の王国」実現の特効薬としてこれからも、期待できるだろうか。構造的に、原理的には、それは難しい。
だが、先に触れたように、列島では(いや、きっと他の地域にもあるだろうが)、二項は対立的ではない。たとえば、食という必然・必要の領域の中で美を生みだし、美を味わい、楽しんできた。
〇「労働」から「感(はたら)く」へ
『暇と退屈の倫理学』の直接のテーマから少し離れてしまった。
ただ、「労働日、労働時間の短縮」だけが課題なのではない、と言っておきたい。
労働時間は、ヴェイユの時代からみれば、相当に短縮された。それでも、家に帰れば寝るだけ、という労働生活実態がなくなったわけではない。
これからは、非正規雇用者もそこに明確に含まれることが切実な課題だと思うが、そう簡単には実現しないと思う。資本制の構造はそれを容易には許さないだろう。

「労働」から「感(はたら)く」へ』
國分さんが、マルクスと同じように「労働日(時間)の短縮」による「暇」の拡大を主張することに反対なのではない。「必然の領域」の先に「自由の領域」を見出そうとする思考構造を相対化してみることも大切ではないか、と言いたいのだ。
言い換えれば、労働時間の短縮とは別の視点、アプローチも大切だと思う。それは、「労働」のありようの変革である。労働も含めた「生きること」(全活動)の関係の変革である。
列島で今日の「労働」の形態(賃労働、雇用契約制度)が生まれたのは、たかだか150年少々前のことであり、今日の労働スタイルが絶対ではない。
「労働」を「感(はたら)く」へ組み換えていく。
いや、今日の賃労働でも、「感(はたら)く」関係が実現されている面もある。なぜなら、人はつねに他者とこころ暖まる心的価値の交換を、日頃から行っているからだ。「賃労働」の場であってもだ。
ただ、その労働が、資本の自己増殖の手段に成り下がり続けることには反対したり、抵抗すべきだろう。
時短だけではなく、こうした関係の組み換えも、課題とされるのではないだろうか。
そうなれば、時短を追求すること自体が、ついには意味をなさなくなることもありうる。なぜなら「労働」が「感(はたら)く」に変化する(止揚される)からだ。
『暇と退屈の倫理学』が、「社会総体の変革を目指している」のであれば、関係の変革にも視線を伸ばしてほしいものだ。
〇「仕事」は「退屈から逃れたい」ためなのだろうか
長くなってしまったが、最後に二つほど付け足しで。
第一。今日、人がなぜ働いているか、という直接的に理由について。
國分さんは、「人は日常の仕事の奴隷になっている」と指摘する。
「では、なぜ人は日常の仕事の奴隷になっているのか? それは『なんとなく退屈だ』という声から逃れたいがためだ」と(『暇と退屈の倫理学』)。
ときに耳にする言説である。現実を冷笑するボードリヤール的シニシズムの影響かもしれないが、はたしてそうだろうか。
私たちが「仕事の奴隷」になっている、とは、たしかに一面いえる。「賃労働」自体がそうだ、と。
また、「なんとなく退屈」から逃れたいからだ、との見方に当てはまる人も一部にいるだろうし、こころの一部にそのような性向を見出せるかもしれない。
ただ、そう断じられるだろか。
多くの人々は、自分、さらに家族が生活を営む費用は、自分の働きで得るべきだ、と考えている。そして、少しでも生活を充実させたい、と。それが仕事する「倫理」であり、まっとうな人の立ち姿である。
詐取や窃盗、強奪で貨幣を得るわけにはいかないから、そう思い働いている。もちろん仕事自体に、生きがいをひしひしと感じる人も少なからずいるだろう。
だから、「『なんとなく退屈だ』という声から逃れたいため」とはとても言いがたい。
歳を重ね、想いを強くするのだが、コロナ禍や、自然大災害に遭う事態を見るにつけ、人が生きるために必須(エセンシャル)な労働(たとえば医療、介護・介助、生活インフラ維持、ここに『パーフェクトデイズ』の「平山」さんの仕事も加えたい)に従事している人たちに対して、私は今まで以上に敬意を抱くようになった。「ありがたい」ことだ、と。
もちろん賃金(対価)の獲得を目的とするのは当然だ。しかし、労働(感(はたら)き)の中で、彼らはかけがえのない贈与をおこなっている。
彼らの姿を見ていると、「『なんとなく退屈だ』という声から逃れたいがため」に働いている、との見解には同じられない。
國分さんもまだ若く、思わず筆が滑ったのだ、と受けとめておきたい。
〇「露骨な定住中心主義」という批判
第二。
本書では、ドイツの哲学者ハイデガーが「露骨な定住中心主義」者として厳しく批判されている。國分さんとしては、「定住」より「遊動」に重きを置きたいのかもしれない。近年の論壇でも、「遊動」に価値を置く傾向が強いようだ。

ハイデガーは、後年、ある詩人の言葉を引用している、人間は「草木である」と(「放下」)。「根をもつて土中から生ひ立たねばならない草木である」と。國分さんもそのテキストは知っているはずだ。
ところで、動物は移動するが、植物は定住する。大地に根ざす。
西欧では、人間を動物に喩える論が主流で、古代ギリシャ、聖書からすでに見られる。そうした中で、人間を草(植物)と喩える西欧人は、おそらくそう多くはあるまい。
ハイデガーは存在の生成を「動物的」ではなく「植物的」にとらえていた。だから、彼を「露骨な定住中心主義」者として論難してすませると、重要なはずの存在論(存在観)を狭めてしまうのではないか、と懸念する。
ちなみに列島では『古事記』『日本書紀』で、人間、いや神までも、「草」に喩えられている。このことは、今日の近代主義的な「保守」の人たちからは、私の知る限り、まったく無視されているけれど。
だが、列島で人間(いや神までも)が「草」に喩えられていることは、とても重要なことなのではないか。
むしろ、そこに列島文化の今日的な可能性を見出せるのではないか、と思うのだ。
★ ★ ★ ★ ★
以上、ずいぶん書き散らかしてきた。
老爺心的お節介と映るかもしれないが、西欧近代的思考枠組の相対化、そして「社会総体の変革」への一助となることを願うだけだ。
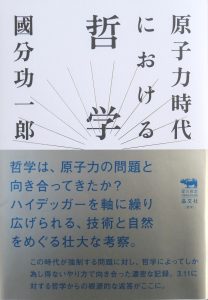
なお、本稿を書き終えてから、小生の旧ブログ(スロー風録、2020年)で、同じ著者の『原子力時代における哲学』について書評したことを想い出した。『暇と退屈の倫理学』よりあとに出た著書である。この書評では「著者がこれから追究していくだろう、この道の進展には大いに期待したい」と結んでいる。
このことも付記しておく。
※「疎外」については、次項で論じたい。
「疎外」ということ 『暇と退屈の倫理学』書評 (下)


