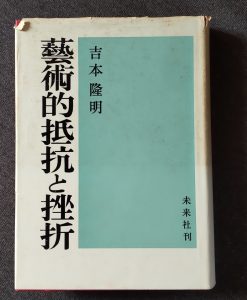斎藤幸平と先崎彰容
今も人気の『人新世の「資本論」』(斎藤幸平)に対して、異議を呈する論が「文藝春秋」2022年2月号に掲載されている。
先崎彰容「「人新世」の『資本論』」に異議あり」である。

先崎さんは、テレビやネットでたまに拝見すると、語り口も雰囲気も江藤淳を彷彿とさせる。きっとずいぶんな影響を受けたのであろう。論も、江藤淳に近い立場にあるようだ。どちらかといえば、私は好感をもって話に耳を傾けている。
その先崎さんが、斎藤幸平さんの『人新世の「資本論」』の問題点に触れている。
◯先崎さんによる批判と課題
昨今の気候変動問題の諸悪の根源を「資本主義」に求める斎藤さんの書を前に、先崎さんはその「語り口」を批判し、過去の「マルクス主義」が「大量粛清」「管理社会」という恐ろしい事態を招いた歴史の教訓に学んでいないではないか、と指摘する。
私自身、『人新世の「資本論」』における「マルクス主義」への傾斜ぶりの危うさについて、ブログに書いたので、ここでは割愛するが、先崎さんと同じ疑念をもっている。

ただ、先崎さんの批評は、いささか上滑りしているようにもみられる。
人間とは「非合理的な生き物」であるのだから、今日のエビデンス主義(科学主義)や、「絶対の正義」に背を向けることがある。それが人間の「自意識」である、とドストエフスキーなどを引用し、文学的な立場から批判を加えている。言葉や精神のしなやかさが、『人新世の「資本論」』では失われているではないか、と。
こうした主張は「文学」的立場から指摘はでき、また気持ちもよくわかるのだが、一面的であることを免れない。
また、引用されている吉本隆明の「関係の絶対性」の理解はどうだろうか。
書きだすと長くなるので、これについては、別に「関係の絶対性」について書いた。
◯ご両人に期待すること
かつて20世紀に、「政治と文学」の論争があった。「政治」は信奉する「絶対の正義」に基づく有効性に拘泥し、文学を従属させようとした。「文学」は「人間の宿業」や人間の内奥の苦悩と向き合うポーズに拘泥して、社会との文学的・思想的対峙(政治をテーマとすればよいということではまったくないが)から身を逸らせた。
このように、閉じられた「政治と文学」の対立構造に、俊英の斎藤、先崎の両氏が陥ることはあるまい、とは思う。
先崎さんについては、本居宣長論等についても期待している。だからこそ、「取り組むべき問題は、環境破壊でも資本主義の危機でもなかったのである」と一蹴するのではなく、このテーマへの自分なりの掘り下げの一端でも本稿で示してもらいたかった。
他方、斎藤さんには、晩年を含むマルクスの研究を継続することを否定するつもりはまったくないけれど、「マルクス主義」が過去にどんな結末を招来したのか、たえず問い続けてもらいたい。
人間の性(さが)、観念のありようは、そう易々とは変わらない。まさにマルクスが『資本論』に書きつけたフレーズ「地獄への道は善意(正義)で敷き詰められている」の警句を、重々噛みしめた上で、論を進めていただきたい。
一例を挙げれば、スラヴォイ・ジジェク氏あたりの論をためらいなく引用していることには危惧を覚えざるをえない。
若い世代の優れた両論客だ。かつての政治と文学の論争のような地平にとどまることのない、研究と活動の豊かな進展に期待したい。