老講師

【忘れがたき人(1)】
○気になる女の子
小、中、高と、当然のこととして、公立の学校に通った。
塾や予備校とは無縁だったが、高校2年の終わり頃から、予備校の冬期、夏期の講習を受けるようになった。
案の定、志望した国立大学に落ち、通うことになった予備校は、国電(現JR)大塚駅近くにあった。武蔵予備校という。
浪人生活は苦役だった。とにかく試験に合格するだけのために1年間を費やするなんて、今振り返ってもぞっとする(それでも、学費は親が出してくれたのだから、恵まれてはいたが)。
ベビーブーマー世代ゆえ、どこへ行っても満員という事態は、予備校でも変わらない。ぎゅう詰めの授業が、うんざり感に輪をかけた。
青春時代の暗い妄想や衝動を抱えていたが、それでも「大学進学」という人生のコースを蹴飛ばすような大胆さはもちあわせていなかった。それなりにちゃんと予備校に通った。
あの時代の1年間で覚えていることはほとんどない。つまらない断片的なシーンがいくつか浮かぶくらいだ。
予備校からの帰り、池袋駅で乗換の架橋歩道を歩いていたら、デパートの電光掲示板ニュースに、「亀井勝一郎、死亡」のニュースが流れていた。『愛の無常について』とか『大和古寺風物詩』など、一時ずいぶん熱中したこともあったが、その熱もやや冷めていたころのことだ。
でも予備校には、気になる人が一人いた。
華やかな感じのする女の子だった。明るい色のカーディガンを羽織り、髪はくるっと丸めている。いつもボーイフレンドに囲まれている姿を、遠くから眺めるだけだった。私の好みとは異なるけれど、予備校に通う楽しみではあった。いや、楽しみはそれくらいだったかもしれない。
その子とは、翌年の新年度、同じ大学の同じ学部構内でばったり出会った。同窓の同期生になったわけだ。
予備校時代と同じように、つねにたくさんのボーイフレンドに囲まれていた。
ところが彼女は、わたしがどうしても反発を覚えざるをえない政治党派系のシンパになっていた。
わたしはセクト(党派)に属したことは一度もないが、相対的にみての好き嫌い(良し悪し)は多少あった。彼女は、明るさを売りにする(ゆえに、とても信用できない)セクトの周辺で行動していた。
あの時代、「明るい青春」などというものは、とても受容しがたかった(そうした事情について、ある程度は、『村上春樹と小阪修平の1968年』の中で触れた)。
ところが、しばらくして、彼女の姿をみなくなる。党派間の争いの渦に巻きこまれたのかもしれない。
当時、そのようにして、学内からすうっと姿を消す学生は、けっして少なくなかった。
○「フェルディナン、手を貸しておくれ」
「忘れがたき人」として採りあげたいのは、その女の子ではない。同じだった予備校の男性講師だ。しかも、当時御年80歳にはなろうか、いや達していたかもしれない高齢の先生。
痩せて小柄、短めに刈り上げた髪で、ちょび髭を蓄え、頬には大きな滲みがあった。名前は想いだせない。

予備校で、英語や古文、漢文などの講習を受けてみると、なるほど、問題を解くとはそういうものか……、と納得することが多々あった。受験勉強のコツがベテラン講師によってわかりやすく披露されるのだ。
この先生は英語(英作文だったか)を教えていた。
たいへんな高齢ゆえ、「おいおい、だいじょうぶかいなー」というのが、初めての率直な感想だった。
教壇に上がるにも、机に手をついてひと苦労しているようなお姿だった。
しかし、講義を聴いていると、それなりにツボを押さえた授業であることがわかった。お陰で、「受験英語」の力は増した。
ときおり交える、ほんのりしたユーモアは、10代で気が急いていたわたしですら、にやっとさせるものだった。かわいいお爺ちゃんという雰囲気を漂わせていた。
細くて小柄。強い風が吹いてきたら、飛ばされてしまいそうな、そんな先生の姿を想い出すと、ゴダールの映画『気狂いピエロ』の一シーンと重なってしまう。
フェルディナン(ジャン・ポール・ベルモンド)が、熱を入れた女マリアンヌ(アンナ・カリーナ)を探して南仏をさまよっているとき、港でどこかの国から亡命してきた「王女」と自称するおばあちゃんに出会い、その雇われ人になっている場面だ。
その老「王女」はヨットハーバーで、「舟が揺れるとわたしの体が飛ぶから、おさえておくれ。わたしはとても軽いの、フェルディナン。手を貸して」と、しわがれ声で叫んでいた。
失礼ながら、その老「王女」と高齢講師のイメージが、なぜかつながってしまう。先生も、強い海風が吹いたら、一気に飛ばされしまいそうな体つきだった。
○高齢社会のシニアの先駆
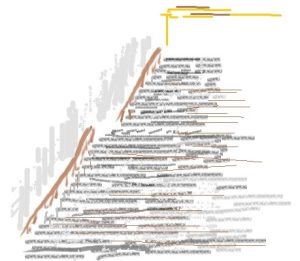
先生のお姿は校外でも見かけた。予備校に近い大塚駅。当時はエレベータもエスカレータもなかった。先生は必ず手すりにつかまりながらゆっくり階段を上り下りしていた。そんな姿を駅で何度か見かけたことがある。
予備校にだって階段がある。週何日かは予備校に通っていたのだから、その都度、駅や学校の階段の上り下りを、手すりにつかまってしていたことになる。
なぜそんな高齢にまでなって、と当時のわたしは思ったが、同時に役に立つ授業をしてくれているのだから、感心もし、親しみも感じていた。
先生の姿には、「稼ぎ」のために働いているという雰囲気はうかがえなかった。半ば趣味であり、半ば健康法であり、自らの知・ノウハウを若者に提供して役立つことで、生きがいも見出していたのだろう。
あれから、半世紀以上……。ずいぶん齢を重ね、わたしもあの先生に近い年齢になりつつある。振り返れば、「なかなかできない生き方だな」と思うようになってきた。
自戒も込めていえば、不機嫌そうな表情で、首を前に突き出して歩く高齢者を、街のあちこちで見かける。そうした中で、あの先生のように、心しなやかに、少しでも社会とつながって生きられれば、それに越したことはない。
老先生の働く姿は、そのあと間もなく訪れた高齢社会における生き方の、みごとな先駆でもあった。
その後の消息は知らないが、きっと大往生を遂げたにちがいない。



