マルクス・ガブリエル 『倫理資本主義の時代』 [書評]
[雑記帳]
資本主義と倫理のリカップリングは可能か。
「訓練を積んだ哲学者」が倫理的問題を解決できるのか。
ガブリエルさんは西欧近代主義的思考に陥っていないか。
・「資本主義」という定義をめぐって
・「倫理資本主義」は可能か
・「自然からの人類の解放」という近代主義
・「生産」「労働」を欠落させた消費論
・「ヨーロッパ中心主義批判」への反批判にうかがえる傲慢
・「倫理」こそ問われている

著者マルクス・ガブリエルさんの主張をざっくり要約すれば、次のようになる。
資本主義や近代的なものに批判を加える左派は、「現実的な代替策」をまともに示していない。近代は「人間の解放」を目指してきた。今後さらに「道徳的な進歩」を進め、資本主義・企業の中に「倫理」を導入し、資本主義と倫理を結合させるべきだ。道徳的価値と経済的価値をリカップリングさせること、それが「倫理資本主義」だ。「資本主義」と「倫理」を結びつけ、「エコ・ソーシャール・リベラリズム」を実現しなければならない。SDGsを実現させるためにも、資本主義で経済を成長させなければならない。
ガブリエルさんが主張するまでもなく、株式会社など企業活動に「倫理」を求めるのは、近代社会において当然のことであり、つねに志向されるべきだ。
しかし同時に、資本主義(私流にいいなおせば、資本の自己増殖運動)を批判する運動や声もまた、たえず湧きあがらざるをえない。それが、社会主義・共産主義という“イズム”として現象するかどうかは別として。資本の自己増殖運動のもとでは、人間がその手段に成り下がらざるをえないシーンがしばしば露骨に現れるからだ。
◯ガブリエルと斎藤幸平
近代は、この二つの潮流のせめぎあいとしてあった。そして20世紀末のソ連の崩壊で、後者はほとんど勢いを失った。今日残存する強権的「社会主義国家」は時代遅れの無惨にすぎない(だからこそ、なおさら怖いが)。

<個人的補注>
ちなみに、20世紀半ばから後半に青春時代を生きた私の軌跡を“注”として補えば、1960年代、若者たちはアメリカのヴェトナム戦争介入に反戦の声を挙げる一方、すでにソ連など現存する社会主義国家にも「こりゃダメだ」と幻滅していた。つまり右と左に絶望していた。それでも、ソ連とは違うかたちの社会主義的な運動や社会がありうるのではないか、と一縷の望みをもって模索していた。
1960年代後半、若者たちの反戦運動や全共闘運動には、そうした願いも込められていたが、1970年代初頭に終わりを迎えた。大きくはそう括れる。
しかし、1970年代、同世代人が反体制的な方向から「転回」してしまった時代のこと。私が働き始めた中堅出版社で倉庫のアルバイターが解雇され、「解雇撤回・社員化」を掲げて、正社員がともに起ちあがった。争議は泥沼化。延べ1000日の職場泊まりこみを含め、労働争議に見られるあらゆる戦術を駆使。闘いは10年近くに及んだ。
そこでは、雇用差別撤廃だけではなく、業種を問わない同一年齢同一賃金なども模索。執行部の輪番制(固定化を避ける)も実践した。
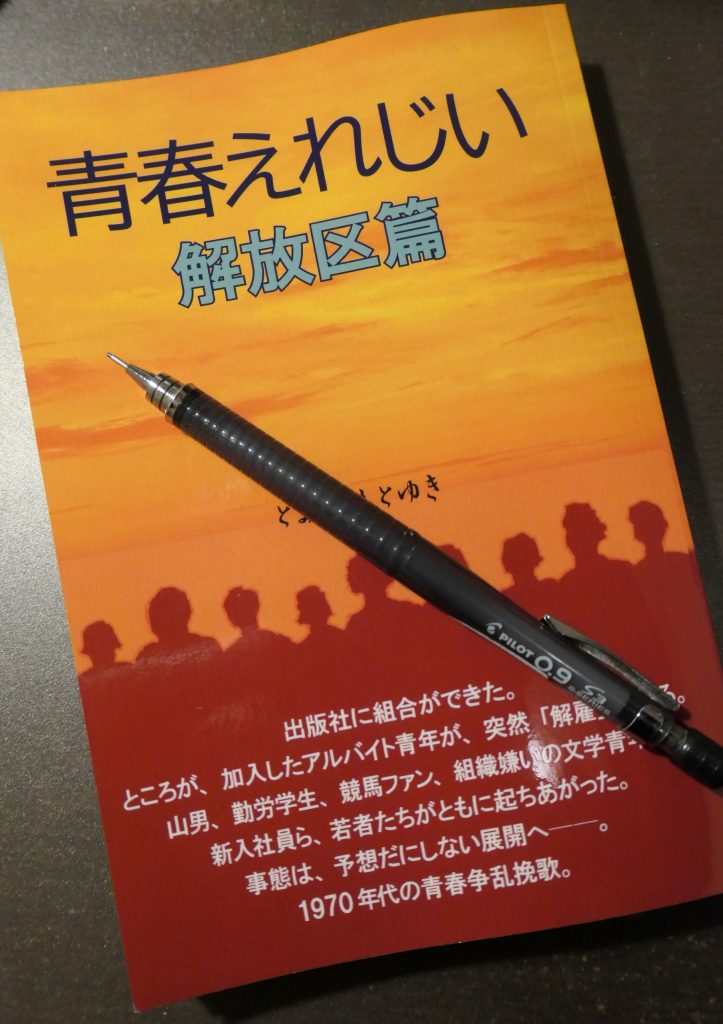
政治的課題はともあれ、現に生きる職場の問題から身を逸らすわけにはいかない――そう決意して進んだ。偶然に出会ったゆえに思想信条がばらばらな、多様な仲間たちが、議論しながら闘い、ときに寝食をともにした。
闘いは二つの要因から終わりを迎えた。ひとつは、“風通し”のよくないバリケート内の地下空間に閉じこもる中で関係が煮詰まり、内部から団結が崩壊しかけたこと。もうひとつは、そんな内部の疲弊や煮詰まりを嘲笑うかのように、外側に広がる、1980年代市民社会のまぶしさ。
半世紀前に地域(都内)・産別(出版関連産業)で労働運動の一端をラディカルに担った者からみると、監修者でありながら本書を批判する斎藤幸平さん的な、つまり左派的な論理と心情は当然理解できる。逆に、資本主義の中に「道徳の進化」を求めるガブリエルさんの論にも(楽観的にすぎるなあ、と感じながらも)理解を示せる。
双方の立場ともわかる。そしてこれからも、二つの潮流がせめぎあい続けるのだろう。ただし、どちらであれ、全体主義(観念の絶対化)に陥ることだけはあってはならない。
◯正反対にみえる2人は同じ土俵に立っている
そう表明した上で、ここでは、本書の問題点(近代的な限界)を俎上に載せたい。
著者は「倫理資本主義」という自論を、「ヨーロッパ中心主義」というローカルではなく、「普遍的価値観」に基づく哲学だと表明している。しかし、私から見ると、本書は西欧的近代を支える「ヨーロッパ中心主義」の限界を示しているようにみえる。
といって、本書「監修者」でありながら、著者とは正反対の立場をとる斎藤幸平さんに、双手をあげて賛意を示すものではない。なぜなら、斎藤さん自身「マルクス“主義”者」を名乗ることにおいて、同じ範疇から出ていないからだ。マルクスの晩年をどんなに評価しようが(そういう再評価はすでに1960年代からなされていた)、過去の、そして現在も続く「マルクス主義」の、観念を転倒させた、残虐な犯罪性を踏まえれば、そもそも「マルクス主義」者を名乗ること自体、憚られるはずなのだから(もちろんマルクス自身の著作を否定するものではまったくない)。
結局、ガブリエルさんも、斎藤さんも、同じ土俵に立っていて、欧米的近代をズームアウトできていない。そこに根底的な問題が潜んでいる。

「資本主義」という定義をめぐって
◯「資本主義はシステムではない」
本書では、「資本主義はシステムではない」ことが何度も強調される。「単一の経済システムとしての資本主義」は存在しない。資本主義は「経済の一側面でしかない」。むしろ、「社会が全体として資本主義的になり得ないからこそ、資本主義は繁栄できる」と。
資本主義は、「社会総体の特徴を語る言葉ではない」と著者は重ねる。たしかにそう言える。
たとえば、社会ではたえず商品の売買(等価交換)が行われている。このとき、たんに商品と貨幣が等価交換されているだけではない。そこに、販売側(とその前の生産者側)と購入側(消費者側)との間で、「等価」云々で測れない心の価値交換も行われている。単なる等価交換の場においてすら、両者の間にさまざまな思いが交錯する。こうした「心的価値」交換があるからこそ、世知辛いこの社会がなんとか維持されている、といってもよいくらいだ。
また、等価交換を破る贈与交換(たとえばボランティア)も広く行われ、それによって社会が支えられてもいる。
もし、経済的価値交換の場に、あるいは背後に、心的価値交換や贈与交換がなかったら、社会は味気ないものになるだろうし、そもそも円滑に回らない。
そういう意味では、ガブリエルさんの 「社会が全体として資本主義的になり得ないからこそ、資本主義は繁栄できる」とのフレーズは、たしかに一面を衝いている。
◯「資本主義」という呼称への疑問
だとすると、そもそも「資本主義」という呼称は妥当なのだろうか。
人は「資本」を「主義」として生きているわけではない。たしかに大金持ちになりたいと願う人はいる。大金ではなくとも、もう少しお金がほしい、とは多くの人が願う。
とはいうものの、「資本主義」、つまり「資本」を「主義」としているという表現はふさわしくない。経済の分野においてすら、現に資本主義の原理に即さない、あるいは反するような判断や行為、交換(たとえば贈与)を、人はいくらでもしている。
人が「資本」を「主義」としているのではない。
「主義」とは、人が信じて疑わない目標を最優先で目指すこと。自由主義は、「自由」を至上のものとして、何よりもこれを優先的に追求する。社会主義・共産主義は共生的・共産的社会を至上として追求する。
資本主義とは、「資本の自己増殖」を主義とすることだ。けれども、大方の人は「資本の自己増殖運動」を「主義」として生きているのではない。結果として、資本の自己増殖を強いられる中で生きているのであって、資本を至上として生きているとは言いがたい。
◯「剰余価値生産主義」
ガブリエルさんは本書で「剰余価値生産」という表現を使っているが、資本主義を、「剰余価値増殖主義」とでも呼び換えるほうが問題点が絞られる。
とすれば、「倫理」と「資本主義」の融合というガブリエルさんの表現は妥当性を欠く。「資本主義」という単一システム(実体)などない、と資本主義を定義しているのだから、直裁に「剰余価値生産主義」と「道徳」の結合と呼ぶほうがふさわしい。
現に彼はこう書いている、資本主義のもとで「必要なのは、剰余価値生産を道徳的進歩とリカップリングさせるという改革だ」。「経済的剰余価値生産と道徳的善には『真の利益』という概念のなかで相関性がある」。
そして、剰余価値を生み出さなければ、SDGsも何一つ実現できない。だから、倫理資本主義を推進せよ!という結論に至る。
彼の論を補えば、本書での「資本主義」とは、企業(組織)の生産活動を指しているようだ。企業に「最高哲学責任者(Chief Philosophy Officer=CPO)を据えることを、彼は提案しているくらいだ。とすれば、主に企業(活動)と道徳の結合でもある。

「倫理資本主義」は可能なのか
◯日本列島の経営哲学と比べると
“哲学界のロックスター”と持ちあげられるドイツの若手哲学者から、資本主義と道徳の結合といった論を提示されると、一方で、なにを今さら、という感は拭えない。
日本列島では、たとえば「売り手によし、買い手によし、世間によし」とする“三方よし”という近江商人の経営哲学が知られている。それを経営理念とする商社もある。
あるいは、パナソニックグループの創業者松下幸之助さんは、利益とは「社会に貢献した報酬として社会から与えられるもの」と教えている。
私のような左派崩れが口にするのは憚られるが、あえて経営哲学を論じるなら、こうした列島の経営哲学で十分に思えてくる。いや、学者ガブリエルさんの「倫理資本主義」論より、血の滲むような実践で刻んだ深みが感じられる。
◯倫理資本主義とは可能なのか
では、はたして、「資本主義」(剰余価値生産主義)と「倫理」の結合は可能だろうか。
「マルクス主義」的立場からみれば、資本主義は資本の自己増殖を「主義」とするのだから、人間をないがしろにするものであり、「倫理」と結合などできないことになる。
若い頃の私はそういう立場だった。企業が朝礼で毎朝立派な「社訓」を唱えようが、「倫理」や「道徳」を打ち出そうが、現実には労働者を搾取し、その犠牲の上に、利潤が生まれるのだから、と。
今日でもそういう面は否定できない。しかし、こうした否定だけで覆うこともできない。なぜなら、今日の市民社会では、古典的な階級性が崩れ、だれもが相互依存的にからみあっているからだ。19世紀、20世紀前半なら有効だった、明確な階級的区分けはもはや成りたたない。左派知識人たちが、プロレタリアートやマルチチュード、プレカリアートなど、貧困の極みを抵抗の拠点として名称を変更して設定しようが、事態は同じだ。
そもそも企業も、資本の自己増殖のみを「主義」として活動しているわけではない。現にさまざまな(倫理的)改革・改善に取り組む企業も少なくない。そうでなければ、批判を浴びる。近年では、投資も「倫理」を基準とするケースすら生まれている。企業活動が社会に貢献している面を否定はできない。
企業経営では、搾取的資本家の思惑も反映されるし、社会に貢献したいとの願いも反映されるし、さらにはPRの狙いもあるかもしれない。一組織の中でも、いろいろな思惑、願いが混在しているだろう。
◯「幼い子どもが浅いプールで溺れていたら」

では、株式会社などの企業で、道徳・倫理は頓挫せずに貫けるのだろうか。
ガブリエルさんがよく持ち出す例え話がある。
幼い子どもが浅いプールで溺れている。あなたはどうするか? 子どもを救うべきであるというのが「明白な道徳的事実」である、と彼は言う。その通りだろう。東京大学安田講堂で8月に行われた講演でも、彼はこの例をしばしば採りあげていた。
彼はその「道徳的事実」の拡大を願う。「道徳的に正しい行動から利益を得ることは可能であり、そうすべきである」。「資本主義のプラットホームは人間性を向上させるため、道徳的進歩を遂げるために活用できる」。
とすれば、他者を思いやり、助けあい、「共存共栄」を図ることが、道徳と企業活動の結合であるはずだ。道徳的立場からみれば、人と人は友愛で結ばれ、組織・企業の間でも、「共存共栄」が求められるはずだ。互いに相手を助けあい、尊重しあい、互いに繁栄する。つきあいのある企業やそこに働く人が溺れていたら、助けあう。
ガブリエルさんの「倫理資本主義」の立場からみれば、「共存共栄」が追求されるべきだろう。
◯「資本主義」と「共存共栄」 ~ビル・ゲイツの場合~
しかし。
「共存共栄」の理念は、資本の論理からすると難しい。資本の自己増殖運動(資本主義)は、つねに自己を拡大させなければならないのだから、共存共栄ではなく、組織の内外で、他に勝つ、他を倒す、あるいは他を併合する(、結果として他者の血を流す)ことが求められる。現に株主の中にはそれを強烈に求める人も目立つ。
小さなエピソードを想い起こす。
1980年代、パーソナルコンピュータが普及し始めたころ、無名だったマイクロソフトはIBMに食いこみ、OSで大きなシェアを占めるようになった。日本のハードメーカーのパソコンのほとんどにも、マイクロソフトのOS(MS-DOS)が搭載されるようになった。
出版業界から弾き出され、パソコン関連業界の片隅にいた私はこの動きを見ていて、そうか、これで青年ビル・ゲイツさんはMS-DOS上で動く日本のアプリケーションソフトメーカーと、共存を図るのだろうと、いかにものんびりした日本列島人的発想で眺めていた。
ところがどっこい。ビル・ゲイツさんはOSにとどまらず、アプリケーションソフトの世界にも手を広げ、在来種(日本企業)ソフトを一気に駆逐し、外来種(MS)で日本のアプリソフト世界を制覇した(Word、Excel、PowerPoint……)。日本企業が当たり前と思いこんでいた共存共栄などといった牧歌的理念は、彼の頭の中にはなかった。その陰でたくさんの血が流れた。

パソコン業界黎明期の一光景だが、なるほど「共存共栄」の概念なんて、グローバルを目指す企業には眼中にないのだ、とあとになって思いしらされた。
棲み分けをして共存共栄を図る道徳を貫くことにとどまれば、負けてしまう。現に競争社会はそのような力学で動いている。
ビル・ゲイツさんは、資本の自己増殖運動(剰余価値増殖運動)に忠実だったのだ。
資本の自己増殖という果てしない運動について、著者ガブリエルさんは身をもって体験していないのだろう。企業には、「最高哲学責任者(Chief Philosophy Officer)=CPO」を置くべきだ、しかも「少なくとも博士課程レベルの十分な教育を受けた学者」でなければならない、などという主張を聞くと、「知」への過剰な傾斜に、こちらとしては退かざるをえない。「知」を上昇・蓄積させただけの人の「道徳」が、企業活動を倫理へ導けるなどと思っているのだろうか。そんな等式が成立しないことは、博士課程レベルの内外の学者・知識人たちの現実の姿をみればわかるはずではないか。
◯「溺れる子を助けたい」という「道徳的事実」と「剰余価値生産」
といって、私は、「道徳的事実」を貫けない企業活動も、そこで働く人も、否定するつもりは毛頭ない。いや否定なんてできやしない。私自身も、企業でそういう宿命の一端を担い働くことで、自分と家族の生活の糧を得てきた。この市民社会の中では、相互依存的にしか生きられない。
「お前も気の毒な男さな。食べなければ、餓死するんだし、食べれば罪を犯すんだからな。不幸なめぐりあわせさな。」(武田泰淳『ひかりごけ』)
個人次元の道徳(人を助けたいという道徳的心情、善意)が、社会(共同次元)にそのまま移行して拡大できるとするのは、安易にすぎる。
道徳を「主義」として掲げる人々は、おおむねここで躓く。
「溺れる子どもを助けるべく飛び込む」という素朴な道徳心情が、食うか食われるかの共同的次元で貫徹できるわけがない。なぜなら、資本の自己増殖運動(資本主義)は、共存共栄に向かうのでははく、排除や蹴落としや勝利を目指さざるをえないからだ。
さらに、虐げられた人、貧しい人を助けたいという、初発の美しい「善意」は、共同的観念の次元に移行すると、「正義」「大義」のためには手段を選ばないという観念の転倒へ陥りやすい。美しい「道徳的事実」からの出発は、20世紀に国内外の左翼政治党派が起こした苛烈な弾圧、あるいは内ゲバ(対立党派への武力行使)殺人に帰結した。
地獄への道は「善意」で敷き詰められている。
経済の「剰余価値生産」と、道徳の「善」との間に、「真の利益」という概念において相関性がある――著者のこうした考えは成りたちにくい。
企業活動に倫理を求めるのは当然のことだし、必要なことと思うし、著者の主張に冷水を浴びせるつもりもない。しかし、彼がいう、「資本主義の基本概念は、人類のために剰余価値を生みだす自由市場の力を認めるというものだ」という認識はずいぶんに甘い。

「人類の自然からの解放」という近代主義
◯近代の評価と相対化
むしろ問うべきは、「資本主義」と「倫理」の結合を志向する、そもそもの土台(近代の原理)についてだ。著者は「近代」という時代の思考原理を相対化できていない。逆に、「近代的原理」のさらなる推進として、「倫理資本主義」を位置づけている。そこに本書の限界が示されている。
先に断わるなら、私は近代を否定したいのではないし、否定などできない。恩恵も十分認識している。
戦前・戦中、京都学派(哲学者)や、「文學界」派(文学者)、日本浪漫派らが掲げた「近代の超克」という概念が空回りして、むしろ戦場に赴くことに悩む若者たちの背中を押した歴史も理解している。
その上で、欧米が牽引してきた近代の根本に根差す病理は明らかにすべきだと思う。それが、近現代を総括し、前へ進むために必要不可欠だと考える。
西欧的近代は、「自由・平等・博愛」を高々と掲げた。それは「近代的主体」の確立とセットになっている。
同時に、近代的思考は、「科学」と「実験」の領域を開拓し、「自然に拷問を加える」(小林秀雄)ようにして、科学技術分野の発展を進めた。
たしかに、近代的主体の確立と「自由・平等・博愛」は、近代の産物として評価され、科学技術の進展も、西欧的近代の産物としてある。
経済分野でも、利子(利潤)の禁止・抑制という壁を突き破り、資本の自己増殖運動を全面開放させた。
しかし近代的思考は、「主体」の確立、「科学技術」の進展を可能にする「場」という「前提」(自然)について目を向けなかったし、今も向けていない。
残念ながら、ガブリエルさんの論も、そこに視線が及んでいない。いいかえれば、ズームアウトして近代を相対化する長い視線を持ちえていない。近代が抱える病巣を認識できていない。
◯「自然からの人類の解放」という驕り
彼が西欧的近代の思考の枠内にとどまり、かつそのことに無自覚である点について、いくつか触れておこう。
彼は近代を 「人間の解放」の時代として、基本的に礼賛する。
近代主義(モダニティ)を、「封建制のくびき」と「ありのままの自然から課された制約」からの人間の解放という歴史運動ととらえる。「集権的権力やありのままの自然の破壊的サイクルからの人間の解放」とも書いている。
近代は、自然の制約から人間を解放した、というのが彼の認識だ。
逆に、封建制期は自然の制約に縛られていたとする見方は、いかにも西欧近代的だ。
ガブリエルさんの論は、自然と人間を対立概念でしかみない。古代から培われた西欧的思考の典型的な近代論の系列に位置する。
しかし、現代人だって彼の表現を使えば、「ありのままの自然から課された制約」のもとに、今も置かれている。地震に、津波に、ハリケーンに、洪水に、「異常」気象に。
いや、それ以前に、そもそも太陽、大地、大気、水に、動植物に、総じて言えば地球という場(自然)で、人間のいのちと営みは生かされている。日本列島の人々はこれを「恵み」と受けとめるが、西欧近代的思考では、「制約」ととらえられる。
たとえば列島では、封建制期にあって「自然」に制約されながらも、自然と寄り添い生活してきた。治水技術が施され、1年のサイクルに即した農耕生産(労働)が、「道徳的」に行われていた。そこでは「ありのままの自然」に全面的に縛られていた、と受けとめるのではなく、自然を恐れ、畏敬しながらも、対話し親しみながら自然に手を加え、ともに生きてきた。また、「道徳」が存在しなかったわけでもない。これは列島に限らない。
だが、著者は、そうした事実に目を瞑り、暗黒の封建制期から、近代に入り人間は自然からの解放を実現した、との認識になる。
このように、自然を人間の対立概念と位置づけ、かつ自然の制約の克服に「人間の自然からの解放」、つまり「自由」「進化」を見いだす。そうした思考に、近代的人間の傲慢を感じざるをえない。
◯奴隷の解放 ~「人間からの解放」と「自然からの解放」~
たしかに近代は、「人間の人間からの解放」をもたらした。
古代ギリシア・ローマ時代からヨーロッパに厳然と存在した奴隷制は、人間が人間を所有し支配するものだった。奴隷制の廃止は、人間からの人間の解放である。
「集権的権力」の政治・社会体制からの「解放」も、近代として評価すべきことだ。
だが、それらは、「人間の人間からの解放」であっても、「人間の自然からの解放」ではない。ガブリエルさんが近代を「人間の自然からの解放」の時代とみているところに、西欧的思考の限界がはっきりとみてとれる。しかも、彼はそこにこそ「普遍性」を見出す。
人間は自然から解放されることはない。なぜなら人間は自然の一部であり、自然に依存しているからだ。
◯マルクス、ケインズと同じ「暁の二段階論」 ~必然と自由~
少し長いフレーズだが、『倫理資本主義の時代』から引用する(101頁)。
「ひとたび人間の基本的ニーズが充たされたら、社会とその経済活動を構築する次のステップは、企業に社会的自由の増大を促すことであるべきだ。少なくとも生存に最低限必要なものを届けるという役割を果たしたら、すぐに経済が担うべき機能はこれだ。こうした理由から経済学を倫理的にアップデートし、経済的手段を通じた社会的自由への貢献として、道徳的進歩と矛盾のないものにするする必要がある」
どこかで似たようなフレーズを読んだことがある。そう、マルクスが『資本論』で、ケインズが「孫たちの経済的可能性」(1930年、山形浩生訳)で描い図式だ。経済の発展が「必然的・自然的ニーズ」を満たした“暁”に、「真の自由の王国」が到来するという論と同じパターンである。私はこれを“暁の二段階論”と呼んでいる。
「人間の基本的ニーズ」「生存のニーズ」、つまり自然的規定が充たされた“暁”に、経済問題は解決し、「自由」「倫理」が確立され、「自由の王国」が到来する。これは、古代ギリシアとユダヤ・キリスト教の融合にルーツをもつ西欧近代的進歩主義歴史観にほかならない。
ところが、マルクスとケインズが予言した“暁”を過ぎたはずなのに、人は「経済問題」に縛られ、いまも最優先課題に据えている。
マルクス、ケインズ両氏は、時代的背景もあるから、やむをえない面もあるが、現代を生きるガブリエルさんも、同じ思考にとらわれている。
◯「自由」は自然に負っている
しかし、人間は自然(的存在)であるがゆえに、「生存のニーズ」「基本的ニーズ」から自由になることはできない。にもかかわらず、自然からの制約を脱した“暁”に「自由の王国」を措定し、そのために絶えず「経済成長」を、ともがく――それが西欧近代的思考だ。
ちなみに、日本列島では、そういう発想は生まれにくい。人間は自然的規定を束縛と受けとめるのではなく、自然とうまくつきあう、あるいは自然とのつきあいを楽しむ方向でやりくりしてきた。
たとえば、食べることは、西欧哲学的には自然的規定に属する。アリストテレスは味覚を、諸感覚の中でも最低位に位置づけた。古代ギリシャ哲学以来、徹底して蔑視されてきた。しかしその「食」の中に、列島人は楽しみを見いだすだけでなく、文化を育んできた。
だから自然的規定を脱した“暁”に、「自由の王国」など夢みない。直線的進歩の先にユートピアを夢みているわけではない。「生存のニーズ」「基本的ニーズ」をたえず充たす過程の中で、生を楽しみ、美を創出してきた。そして日々の営みの繰り返しの中で、喜びと美を味わってきた。
マルクス、ケインズ、そして今日のドイツ若手哲学者に至るまでの「自由の王国」追求運動こそ、まさに近代的思考の病理として剔出すべきだろう。「自由の王国」実現のための、経済成長・剰余価値生産を飽くなく追求するという思考構造こそ、問われるべきである。
“暁”をめざす。その実現のためには「経済成長」が不可欠である。剰余価値の増殖運動に人々は巻きこまれ続ける。
ガブリエルさんは、「新自由主義」を批判するとき、新自由主義者が「社会的自由」を見落としていると批判する。他者が存在しなければ、自由も実現しない、と。この批判はもっともで、同意できる。
しかし、そもそも人間は自らの存在を自然に負っている。つまり「自由」の成立を自然に負っている。「全き自由」などありえない。そういう視線を欠落させている。いいかえれば、「ある」ということを「負い」と「感謝」で受けとめる存在論(存在観)に降りていない。

「生産」「労働」を欠落させた消費論
◯「消費」だけを問う人生論
ガブリエルさんは、ボードリヤールらの西欧知識人たちと同じように、「消費」に足を掬われている。
「人間は決して単に消費対象となるモノに関心があるだけではなく、常に自らの消費を通じて、自らと他者の生活を改善することにも関心がある」
彼は「ほどほどの生活」や「消費のペースダウン」を求める。こういう生活道徳論は、古来、内外のどこにでもあった。
著者は「消費」の見直しによる「自らと他者の生活を改善」に言及するものの、人間が1日の主要時間を割く「生産・労働」についてはまったく触れない。「剰余価値」がどこかから湧いてくるのか、その内実は語らない。
「消費」とは、商品の消費だが、商品は生産・労働によってつくられる。消費は、生産物の消費である。消費があたかも単独で存在するかのように論じることは、西欧近代的知識人の思考を踏襲している。ボードリヤールや彼に追随する学者・知識人あたりの通例だ。
現に著者はボードリヤールを引用する。
「ボードリヤールは早くも一九七〇年の時点で、最大の問題は資本主義そのものではなく消費であると指摘している。そして消費は私たちの欲望と結びついている、と」
このようにボードリヤール氏の考えを引用してガブリエルさんが主張したいのは、悪いのは資本主義ではなく、「消費」のあり方だ、と。自分たちの「欲望」のあり方が問われる、と。
一般論として、「消費」「欲望」のあり方を問うことは大切なことだ。つねに問われるべきだろう。
しかし、人間は消費においてだけ自己実現を図るのではない。生産・労働の過程において、そして生産物を通じて、(他者との間で)自己実現を図ろうと願っている。
「働きがいのある仕事をしたい」――多くの人が、そのような想いを抱きつつ、働いている。
働く人は、生産物の提供によって、他者が消費を楽しむ、味わう、助けられることを願っている。
ところが、労働の場で、そういう願いが叶うとは限らない。むしろ仕事が自分にとってよそよそしいものになったり、労働が自分を苦痛で苛むシーンがしばしばある。その原因をすべてとはいわないが、多くは剰余価値増殖主義に帰因する。
しかしガブリエルさんは、人が1日でもっともアクティブに動く、主要な時間を費やしている労働・生産の過程や課題については触れない。
◯「労働・生産の終焉」
彼が見倣う、20世紀フランスの知識人ボードリヤール氏は主張する。「必要」や「効用」を求める(産業資本主義の)時代は終わった。生産は使用価値を生むものではなく、生産をマークするだけのものになってしまった。今や人々は記号論的世界を生きているにすぎない、と。
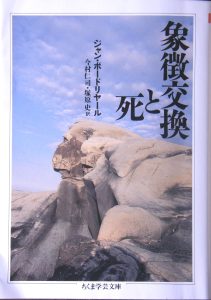
ボードリヤール氏は「生産の終焉」(労働の終焉)を高らかに宣言した(『象徴交換と死』)。だが、これはとんでもない転倒である。
彼は、自らが生活上で労働者の生産(物)によって生きてこられたこと(衣食住、執筆・出版等の生活)、彼の晩年生活を支えた、医療・看護・介護、およびその基盤をかたちづくる広汎な産業労働者の力を、思想的に組みこむことはまったくできなかった。
マルクス主義とともに「労働の終焉」を宣言したものの、終焉したはずの労働のお陰で日々の生活を営むことができた彼自身は、まさに幽霊の生涯を送った、ということになる。
◯「欲望」「消費」を語るなら「生産」にも目を向けるべき
ガブリエルさんに戻ろう。彼は「私たちの欲望とも向き合う必要がある」という。「知恵は『ほどほどの生活』を受け入れること」、「消費プロセスの一部をペースダウン」させること。「消費」と結びつく「欲望」の再構築、あるいは「ほどほどの生活」が提唱されている。
しかし、消費を規定している「生産」「労働」には目を向けない。
もう200年以上前の産業資本主義勃興期、ドイツの哲学者ヘーゲル氏はすでにこう指摘していた。
……欲求は、直接欲求している人々によって作り出されるよりもむしろ、その欲求が生じることによって儲けようとする人々によって作り出される。
(ヘーゲル『法の哲学』)
「欲望」「消費」は、「生産」によって作り出される。「生産」が「欲望」「消費」のかたちを規定している(もちろん逆に、欲望が生産をも規定しているが)。ガブリエルさんがいう「剰余価値生産」こそ、欲望・消費のかたちを規定している。その構造を、ボードリヤール氏やガブリエルさんは問わない。
◯「労働」「生産」とうまく距離をとれない
生産・労働を軽視・無視する背景には、西欧が古来一貫して「労働」を蔑視してきたこと(奴隷に押しつけてきたこと)、あるいは近代になると正反対に、富の蓄積をもたらす勤勉労働に励めと、極端に持ちあげてきたこと(プロテスタンティズム)がある。いいかえると、西欧は「労働」「生産」とうまく距離をとれずにきた。
生産(労働)と消費は互いに深く規定しあっている(このことをしっかり洞察したのはカール・マルクスだが)。「消費」が単独であるのではない。そのことが、ボードリヤール先生や彼を持ち上げる人には見えていない。
たとえば、「住まう」という消費を考えてみよう。それは生産に深く規定されている。住宅を「生産」販売・提供する不動産建設業者は、限りある土地と建物からいかに「剰余価値」をより多く生み出すか、に腐心する。そのための方法・工夫に、庶民の「住まう」という「消費」のかたちも、よかれあしかれ大きく規定される。
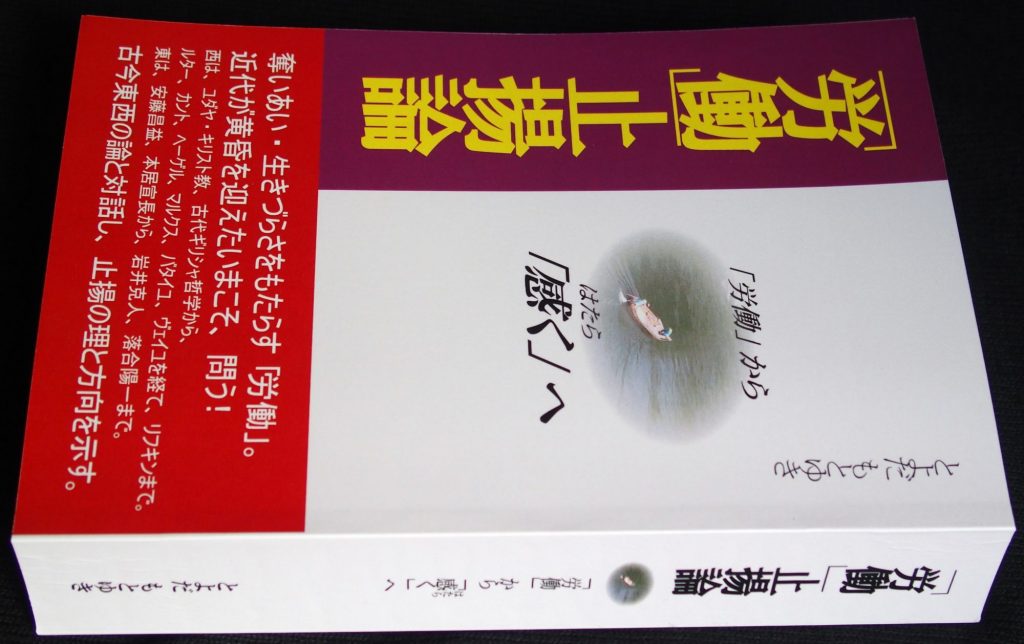
もっと本質的に思考を掘りさげるなら、じつは「住まう」という消費は生産でもあり、住宅をつくるという生産過程は消費でもある。これはどんな生産・消費にもいえることだ。
そもそも人間の活動を本質的にとらえるなら、「生産」と「消費」を明確に切り分けることはできない。生産は消費であり、消費は生産である。そこまで視線を伸ばさないまま、生産から切り離して「消費」だけを、その枠内で語るだけの人生論は貧しいし、ボードリヤール氏のように傲慢だ。
※拙著『「労働」止揚論 ~「労働」から「感(はたら)」くへ~』

「ヨーロッパ中心主義批判」への反批判にみる傲慢
◯「ヨーロッパ中心主義批判」への反批判
最後に、「ヨーロッパ中心主義」をめぐって。
ガブリエルさんは、資本主義や「ヨーロッパ中心主義」への批判に対して、以下のような反批判を展開している。長くなるが、引用してみよう。
「……、資本主義、ヨーロッパ中心主義、あるいは啓蒙主義を批判する為には、共有可能な価値観が客観的に存在するという考えに依拠する必要がある。すべての価値観は地域的な文化(ロシア的、日本的、中国的、あるいはヨーロッパ的価値観など)の現れに過ぎないと考えるのであれば、ヨーロッパ中心主義を批判することはできない。異なる文化的価値観のみが存在し、包括的、普遍的価値観など存在しないのであれば、ヨーロッパ中心主義に何の問題があるのか。それは単に地域の文化の擁護に過ぎない。このように資本主義、グローバリゼーション、あるいは近代全般の不公正な側面を批判しようと思うなら、自らの地域文化や偏狭なアイデンティティを超越する倫理的洞察に依拠する必要がある。」
これは、見逃せない、相当に重大なフレーズである。
ローカルな文化が互いに対立しあうだけなら、ヨーロッパ中心主義のどこに問題があるのか。そう開き直る。
相手を批判するためには、「共有可能な価値感が客観的に存在する」という考えに基づかねばならない。「包括的、普遍的価値観」に基づいて、「資本主義、グローバリゼーション、あるいは近代」を批判しなければならない。
ガブリエル氏は、資本主義や近代は、「包括的、普遍的価値観」に基づいていたものである、と表明していることになる。彼が求めるのは、「普遍性のある言葉」である。
しかし、これまで私が指摘した「自由」の問題や、「人間の自然からの解放」論や、“暁の二段階論”や、「消費」にすべてを収斂する姿勢――これらは、古代ギリシャ、ユダヤ・キリスト教の融合から生まれた西欧近代的な思考や信仰、つまりローカルから産まれた産物である。
「ヒューマニズム」に潜む「人間の自然からの解放」という自由論に普遍性の印を与えることはできないし、「経済成長」の“暁”に「自由の王国」が到来するという直線進歩主義的・ユートピア主義的な「暁の二元論」に普遍的な価値を与えることにもたじろがざるをえない。
そうした文化は、帝国主義的な支配力・武力をもって、世界各地に広げられたというべきだろう。 「普遍」とみえる「近代性、資本主義、経済成長、科学、真理、ヒューマニズム、普遍主義」は、近代に欧米が帝国主義的展開をもって世界各地に拡大させたものだ。
それを、「自らの地域文化や偏狭なアイデンティティを超越する倫理」とするのは、傲慢にすぎる。日本国がかつて帝国主義的時代に、近隣諸国に押しつけた「神道」が「普遍」でないのと同じように。
グローバルが「普遍」とは必ずしも言えない。イーロン・マスク氏やテクノ・リバタリアンたちの論も、「普遍」として奉るわけにはいかない。
※「テクノ・リバタリアン」
◯ローカルと「普遍」
たしかに日本列島も幕末期以降、欧米列強に制圧されることを防ぐべく、近代化を強力に推し進めた。同時に、欧米文明の優れた数々も吸収した。
しかし欧米文明は、列島の風土で培われた「存在観」まで壊すことはできなかった。「ある」ということ(存在)を「有り難い」と受けとめる「生成の存在観」は、今もしっかり列島に生き残る。それは、西欧の存在観(古代ギリシャとユダヤ・キリスト教文化の融合で形成された)とはまったく異なる。
私は日本列島の存在観にこそ「普遍性」があるとは主張しない。ただ、グローバル化された西欧近代的思考が欠如させ、あるいは見ようとしない点を指摘しているだけだ。
欧米と列島を比べ、その優劣を判断したいのではない。また、すべきでもない。どちらが「普遍」か、などと争うべきでもない。
ただ、ガブリエル氏が、「近代性、資本主義、経済成長、科学、真理、ヒューマニズム」を「普遍」と断定するとき、彼の視線は近代をズームアウトしてその病巣を探る点には届かない。しかし列島の存在観には、西欧的近代主義を相対化する視線が備わっている。
こうした互いの批判の中から、課題の共有化と克服への前進が生まれるのだろう。それがあえていえば、「普遍化」を互いにめざす倫理的な姿勢というべきだ。
近代原理の病理は、欧米文化(の存在観)では相対化できない。近代的人間(主観)の傲慢を照らしだす作業は、異なる存在観をもつ列島人だからこそ可能だ。
西欧的近代がすっかり忘却した「自然への負い」について、日本列島文化こそ提示することができる。
「人間の自然からの解放」論や、経済成長の“暁”に到来する「自由の王国」論という、普遍を装うローカルな論理に、日本列島というローカルから異を唱えるのも、普遍化を互いに探る作業にとって欠かせないはずだ。
◯「ハイデガーを読むのはやめなさい」
ところで、西欧文化圏内にあっても、「近代」や「ヒューマニズム」の限界を指摘する人々はいたし、今もいるだろう。その1人が20世紀の哲学者ハイデガーである。

ところが、そのハイデガーについて、ガブリエルさんは別の書『全体主義の克服』で「ハイデガーを読むのはやめなさい」と命じている。「ハイデガーは本物のナチです」「彼は筋金入りの反ユダヤ主義でした」と(同前)。
たしかに、ハイデガーはナチスに加担した時期があったし、近年発表された「黒ノート」でも、「ユダヤ的なもの」への揶揄がみられるようだ。私は、ハイデガーがむしろナチスの人種主義こそ西欧形而上学に基づくものと批判している、との見解を支持するが、黒ノートへの評価について、ここでは断定的なもの言いは避けよう。
ただ、どうあれ、ハイデガーの「西洋形而上学」批判は今日に至るも、まったく力を失っていない。ガブリエルさんが持ち上げる「近代性、資本主義、経済成長、科学、真理、ヒューマニズム」……まさにこうした概念を生みだす近代的主体(主観)に対して、ハイデガーは根底から疑いを差し出している。
「ハイデガーを読むのはやめなさい」とは、じつに危険な命令だ。
たとえば、本居宣長の皇国史観をもって「もののあわれ」論や「カミ論」が、西田幾多郎の皇道論をもって西田哲学が、ゴミ箱に捨てられては決してならないのと同じように、ハイデガーのナチス加担をもって、彼の「西洋形而上学」批判までもが捨てられてはならない。
◯「タブー」を設定してタブーを助長
「ハイデガーを読むな」という焚書扱いこそ、全体主義への一歩にならないか、危惧する。こういう言説が逆に、ナチス的思考を増殖させないだろうか。
ハイデガーを読んだら、ナチス肯定へと引きこまれてしまうから読むな、とは哲学者らしからぬ言だろう。むしろ、ハイデガーに深い闇の部分があるとすれば、それも明らかにして批判を加える、それが哲学者の仕事だろう。
タブーの設定はタブーを助長する。そうした観念の自然過程に、ガブリエルさんは自覚的ではないようにみえる。
西欧的存在観が、「自らの地域文化や偏狭なアイデンティティを超越する」ものであり、「包括的、普遍的」だ、というのは傲慢にすぎる。
人々がものごとや社会をとらえ、世界観を構成するとき、その基礎づけとなるのが存在論(存在観)である。その存在観が、列島と欧米では根底的に異なる。それはどちらが「普遍」か、を競うものではない。ただ、列島の存在観は西欧形而上学(西欧哲学)、欧米的近代の病巣に光りを当てることができる。
ハイデガーの中・後期の講義録は、そうした視点に深い示唆を与えてくれる。

「倫理」こそ問われている
◯日本列島の不幸
翻って日本列島に目を移すと、残念なことに今日に至るも、近代的思考に疑義を呈する学者・知識人をあまり見かけない。多くが、輸入して自分のものにしたつもりの西欧発近代的思考(ヨーロッパ中心主義)に依拠して、これに疑いをもたない。
不幸はさらに重なる。本来なら、こうした思潮に対して疑義を呈するのが、「伝統」「保守」の役割のはずだ。
ところが、列島の「保守」を自称する主な人たちは、たとえば哲学者和辻哲郎氏を持ち上げる。しかし、同氏は、「和風」の衣を装いながらも、じつは西欧近代主義的思考の枠から出ていない。ハイデガーの西欧形而上学批判を理解しない一方、例えば、本居宣長の「もののあわれ」論を、(近代的)主体性や男らしさを確立できておらず、「女々しい」と断じる。
こうして近代を相対化できず、西欧近代的思考の土俵上に立つ和辻哲郎氏が、「保守」を自称する人たちの一部から高く評価されるという皮肉に、今日の列島の不幸の一つが見られる。
◯「普遍」を装うローカルに、ローカルから異を唱える
『倫理資本主義の時代』に話を戻す。
マルクス・ガブリエルさんが企業に「倫理」を求める方向を冷笑するつもりは、毛頭ない。そうあるべきだ、と思う。
にもかかわらず、人々が、企業が、「資本の自己増殖運動」の力学に巻きこまれ、血を流さざるをえない必然について、もっと深くみつめるべきだろう。
人々が願う「共存共栄」の理念は、剰余価値生産主義から弾き出される。剰余価値増殖主義は、資本の自己増殖運動のもとで人間を手段として扱うし、その運動は必ず格差を拡大させる。
ゆえに、抵抗運動はたえず起こる。避けられない。
誰もが「溺れた子どもを救いたい」と願う。しかし、善意が「道徳的事実」(真理)であっても、それが共同的次元へとストレートに繋がるわけではない。
小さな「善意」が共同的次元では転倒して、恐ろしい観念の絶対化(恐怖政治)を招くこともある、ということには自覚的でなければならない。「地獄への道は善意で敷きつめられている」。そのことを自覚しない思想・哲学は無効だ。
◯「溺れる子ども」はプールの中だけではない
今日の市民社会では、剰余価値生産(資本主義)のスピードは増す一方だ。のんびりしていたら、価値とされる「差異」は差異でなくなり、商品価値を失う(剰余価値を生めない)。早く情報発信したほうが「勝ち」だ。資本の自己増殖運動のもとでは、剰余価値をできるだけ大きく、そしてそれを産む時間をできるだけ短縮させようと動く。それが資本の冷徹な論理だ。
こうした資本の苛烈な論理に、自然である人間の身体・こころは、そうやすやすとは馴染めない。とりわけ列島人は、人格と身体を、西欧的に切り分けるのが得意ではない(これは決して負性ではないが)。だから「karousi」(過労死)が国際語になってしまった。
これから社会という海に船出しようとする子どもたち、船出したばかりの若者たちは、プールではなく、市民社会の海で「溺れ」かける。
自分(という労働力)が商品として計測される(ランク付けされ)る。剰余価値増殖の猛スピードに乗ることを強いられる。
市民社会の海で溺れる子どもたち、若者たちが出てくるのも当然だ。
むしろ、このスピード社会のノリノリの空気に乗れずに弾き出されるナイーヴな感性にこそ、エールを送りたくなる。
◯倫理が問われる「人間(労働力)の商品化」
「欲望」「消費」の見直しも大切だが、働く場、働く過程の見なおしも、求められている。
もし、ガブリエルさんが「普遍性」や「倫理」を追求するなら、彼が「自由契約」と呼ぶ「雇用契約」そのものにも目を向けるべきだろう。人間の労働力が「商品」として売買されるという事態。
奴隷制のもとでは、人間自体が売買された。しかし、近代社会では、人間ではなく、その労働力が売買される。それはたしかに、大きな「進歩」である。
雇用契約のもとでは、人間と労働力が切り分けられている。たとえば工場労働の場合、人間と労働力は、是非は別として、切り分けやすかった。
しかし、モノの生産ではなく、サービスの生産(サービス産業)がますます拡大する今日、「人間」と「労働力」は、より切り分けがたい。
このとき、「労働力」が商品として(ランク付けされて)売買されることがもたらす軋みは増大するばかりだ。
かつて奴隷制に代わり「雇用契約制度」が登場した近代のはじめ、カントやヘーゲルは彼らなりに、労働契約が「人格の自由」に抵触しないかどうか、そういうテーマと格闘した。
奴隷制は、人格を否定し、人間のすべてを売買する。しかし「自由契約」である雇用契約制度は、人格と身体を分けて(いかにも西欧的だが)、身体(労働力)だけを売る。だから人格の「自由」には抵触しない――カントやヘーゲルはこう結論づけた。その論が成功したとはいえないけれど、問題と向きあった。
ところが、サービス産業が多くを占める今日、人格と身体を切り分けるのは、ますます難しい。
しかし、今日の学者・知識人さんたちはこれと向きあうことを避けて、「消費」問題に逃げこんでいるようにみえる。
ガブリエルさんが剰余価値増殖主義と「倫理」をリカップリングしようとするなら、まずもって雇用関係のもとで働く人(いいかえれば、ほとんどの人)が日々現場で突きつけられる倫理的葛藤にも目を向けるべきだろう。
雇用契約制度はそう簡単にはなくならない。しかし、「自由」を語るのであれば、「人間の人間からの解放」を語るのであれば、労働力(ほぼ人間自体)が商品化されるという、人間の心身に極めて苛酷な事態をも射程に入れて、剰余価値生産主義論(資本主義論)を深めるべきだろう。それが哲学者の「倫理」的姿勢ではないだろうか。ここを避けて掲げられる「倫理」は欺瞞に陥らないだろうか。


